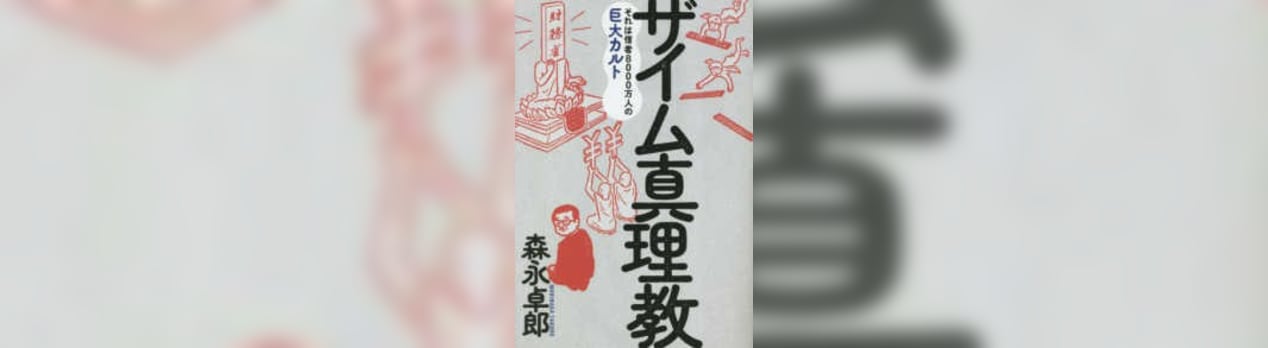森永卓郎,2023,ザイム真理教,三五館シンシャ.(4.22.24)
わたしたちは、財務省が喧伝する「日本の財政赤字は危機的水準に達している」との教義にだまされてきた。
それに加担してきたのがマスメディア、である。
わたしも、かつて朝日新聞を購読していたとき──「桜を見る会」の疑惑追及のさなかの2019年11月から12月にかけて朝日を含めた新聞記者が安倍総理(当時)と会食を重ねたことに失望し、記者が会食に参加しなかった毎日新聞に切り替えた──新聞紙面では財政危機を煽る記事がたびたび掲載されており、どうもそれらに洗脳されていたようだ。

財政赤字算出の基礎となるデータが古くなっているが、現時点での実際の数値と大きな隔たりはない。
国の借金総額が1680兆円、GDP比2.6倍の財政赤字は世界ワースト2位、国民一人あたりに換算すれば1318万円の負債──この負債は、子どもを含めた将来世代が返済しなければならず、この膨大な借金のツケを将来世代に払わせてはならない。
こうした言説は、一読、とても説得力があり、つい信じ込んでしまったとしても不思議ではない。
しかし、森永さんは、こう指摘する。
国は、国債という借金を987兆円抱えている。ただ、それだけではなく、借入金や未払金なども加えると1661兆円という負債を抱えている。これが広い意味の国の借金の総額、負債の額だ。
一方、資産のほうをみると、日本政府は現預金や有価証券などの流動資産を841兆円、土地や建物などの固定資産を280兆円も持っている。合計の資産額は1121兆円だ。こんなに政府資産を持っている国は日本以外には存在しない。つまり、日本政府は借金も多いが、その借金の3分の2ほどは資産としてキープしているのだ。
負債の1661兆円から保有資産の1121兆円を差し引くと、資産負債差額は540兆円となる。これが本当の日本政府が抱える借金なのだ。2020年度の名目GDPは527兆円だから、借金のGDP比は102%だ。GDPと同額程度の借金というのは、先進国ではごくふつうの水準だ。日本の財政が国際的にみて悪いと言う事実はまったくないのだ。
(p.56,pp.58-59)
財務を正確に把握するためには、キャッシュフローだけでなく、貸借対照表に記載される流動資産および固定資産の額を参照しなければならない。
森永さんは、国が保有する膨大な流動資産、固定資産から、日本の財政は健全である──少なくとも危機的状況にはないと断言する。
わたしは、なかでも、100兆円を超えるとされる、この世界第一位の米国債保有高がひっかかる。
トマホークやオスプレイなど、古びるか、欠陥が指摘される兵器、防衛装備品を法外に割高の価格で米国から購入する、国内の米軍基地の維持費用を世界一高い水準で負担する──いまだ米国の属国として振る舞う日本が、通貨安で家計負担が増し困窮する国民をそっちのけで、ひたすら、米国債、アメリカドルを買い、円安を加速させている。
まったく、ろくでもないことだ。
いつまで、米国の植民地のままでいるのだろうか。
マックス・ウェーバーやロバート・マートンの指摘を俟つまでもなく、官僚機構は、手段を目的化するという倒錯、セクショナリズム──自らの内集団の利益のみを追求するといった悪弊に陥る。
財務省もその例外ではなく、一円でも租税収入を増やし、歳出を抑制する──「財政均衡主義」を教義とする「緊縮財政」こそが、唯一の正義となる。
消費税の導入と税率の引き上げが、デフレ、日本経済の停滞の元凶となってきたのはまちがいない。
ただ、森永さんの考えでは、消費税の導入と税率の引き上げが、消費需要を減退させ、それが企業収益の低下と、人件費削減のための雇用の非正規化を帰結したとの見立てだが、2010年代以降の大企業の内部留保の著しい増加をふまえれば、それはちがうのではないか、と思う。
財界が政府と結託して推進してきた雇用の非正規化は、企業が、バブル崩壊による経営危機を、安易な人件費の削減により乗り切ろうとして進行したものであったが、イノベーションのための研究開発の努力を払わなくとも雇用の非正規化で収益を上げることができることにあじをしめた企業は、不良債権処理が一段落した2000年代以降も人件費の削減を推進した。
そして、消費税率の引き上げが、大衆消費財の需要を冷え込ませ、コモディティの低価格停滞(デフレ)を長期化させた。
これが真相ではないだろうか。
MMTの議論をふまえれば、森永さんの主張も、より説得力が増すように思う。
L・ランダル・レイ(島倉原監訳),2019,MMT現代貨幣理論入門,東洋経済新報社.
島倉原,2019,現代貨幣理論 MMTとは何か──日本を救う反緊縮理論,KADOKAWA.
やさしく、やわらかく、面白く、日本経済に警鐘を鳴らす本。
それは信者8000万人の巨大カルト
「大蔵省(現財務省)の奴隷だった」という自身の実体験をもとに、宗教を通り越してカルト教団化する財務省の実態をあばき、その教義を守り続けて転落し続ける日本経済&国民生活に警鐘を鳴らす、森永卓郎による警世の書。
~旧大蔵省時代を含めて、財務省が40年間布教を続けてきた「財政均衡主義」という教義は、国民やマスメディアや政治家に至るまで深く浸透した。つまり、国民全体が財務省に洗脳されてしまったのだ!(本文より)~
最近、ネットの世界では「ザイム真理教」という言葉が頻繁に使われるようになった。財務省は、宗教を通り越して、カルト教団化している。そして、その教義を守る限り、日本経済は転落を続け、国民生活は貧困化する一方になる。本書では、なぜザイム真理教が生まれ、それがどのように国民生活を破壊するのかというメカニズムを述べていこうと思う。
目次
第1章 ザイム真理教の誕生
第2章 宗教とカルトの違い
第3章 事実と異なる神話を作る
第4章 アベノミクスはなぜ失敗したのか
第5章 信者の人権と生活を破壊する
第6章 教祖と幹部の豪華な生活
第7章 強力サポーターと親衛隊
第8章 岸田政権は財務省の傀儡となった