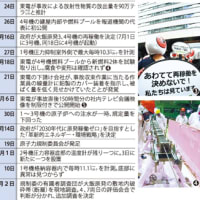竹中労が1970年に予見した、石原慎太郎が大統領になって支配しているという戯画的な近未来像はなかなか興味深い。当稿は弟の俳優・石原裕次郎について書かれたものだが、裕次郎は1987年に亡くなった。
「スター36人斬り」(2001年、ちくま文庫「芸能人別帳」に再録)より
《第7章 天下を狙う? 石原裕次郎》 の一節
198×年──ニッポン国初代大統領・石原慎太郎閣は、満18歳に達して身体健常である国民男子に、軍事訓練を含む2年間の集団生活を義務づけると布告した。いわく「これは“徴兵制度”ではない。日本の若者に、愛国、正義、独立、進取の気概を回復しようとする精神大革命である」
(いうまでもないが、以下記述するところは、当たるも八卦の戯文で、なんら責任のある文章ではない。念のため)──竹中労
そのころ、日本の若い世代は社会秩序からドロップアウト(逸脱)し、勤労意欲を失ってイッピー化しつつあった。資本主義の繁栄は無為徒食の風潮をもたらし、ブラブラ遊んで暮らす連中、野に満ち山に満ち、巷にあふれて、フリーセックスに狂い、非行、犯罪に走り、1960、70年代にゲバ学生が巻き起こした騒乱よりも、いっそう深刻、かつ重大な流砂のごとき社会不安を生起した。
そもそも、80年代に大統領制度が採用されたのは、若者ばかりではなく国民の各層に政治に対する無関心と、断絶が蔓延して、総選挙の投票率50%を割ったためであった。すなわち、議会制民主主義は原理的に崩壊し、これに代わるべき“デモクラシー体制維持”の方途が要求されるに至ったのである。
そこで、いまや自民党タカ派のスポークスマンである中曽根康弘、前に唱えた“首相公選論”が形をかえて復活し、道州制の実施とともに、国民投票による第一回大統領選挙が行われたのである。革新陣営は、東京都知事四選の長老・美濃部亮吉を、社共両党の統一候補として出馬させたが、石原の若さと人気に圧倒されて惨敗した。
この選挙における石原慎太郎の実弟、裕次郎の活躍は、特筆すべきである。かつて日活のアクション・スターだった石原裕次郎は、独立プロをおこし、68年、『黒部の太陽』という超大作をつくり、配給収入8億5千万円を稼いだ。69年、『栄光への5000キロ』『富士山頂』『ある兵士の賭け』等々を製作、しだいに巨大な資本を蓄積していった。そして70年代、アメリカのメージャーとの提携に成功“1千万ドル映画”を合作して既成の映画資本をしのぐ大プロダクションに発展した。注─(ホントニソウナラウレシイネ)
兄・慎太郎の選挙にさいして裕次郎は利用しうる限りのマスコミ媒体──映画、テレビ、新聞芸能欄、週刊誌etcを動員し、芸能人スターのキャラバンを組んで、「祖国の未来を若者の手に」という大キャンペーンを繰りひろげた。日本の元首は天皇であるべきだとする三島由紀夫を除いて、作家、文化人の多くも慎太郎の応援にはせ参じた。
日本政治史上で、かつてないショーアップされた選挙戦の結果、投票率80%を上回り、民主主義は危機を免れたのである。かくて、慎太郎・裕次郎兄弟は、「日米安保体制」をつくり上げた岸・佐藤ブラザースのあとを受けて、栄光への道を歩む。
紺地のブレザーの胸に日章旗のマークをつけた、シンタロー・ユーゲント(大統領親衛隊)に娘たちはネツを上げ、60階、70階の摩天楼そびえる新宿のビルの谷間、こっそりとひと昔前のシンナー遊びを繰り返すフーテンの群れは、ぶつくさとこうつぶやくのである。
「あの兄弟はよオ、オレたちの元祖で“太陽の季節”なんてイカス小説を書いたり、映画に出たりしたんだってよオ。信じられねえよなァ……」
(週刊読売 1970年・2月27日号)
※東京都庁第1本庁舎は地下3階、地上48階