現段階での、あたしの中での“みる”という下敷きは、以下の5段階です


①眺める
普段あたしたちが“みる”という、おおよそはここに該当するんじゃないかと。
思い出すときに、色とか形とか、数とかなかなか思い出せないの

「信号の赤は右側?左側?」「八つ手の葉はホントに八枚?」みたいに、たまに聞かれるとあれ?って思うことは、たいてい眺めている状態なんじゃないかと思います。
②みる
「あれっ?」って思うこと、“はてな?”を発見すること

せんせーが子どもたちをみる、最低ラインだとあたしは思ってる・・・。(しかし・・・
 毎日欠かさずって結構難しいのよ
毎日欠かさずって結構難しいのよ )
)③よぉくみる(笑)
いわゆる「観点をもってみる」ってやつですね。理科の観察はココに当たります。
五感でみる。触る、耳を近づける、香り、舐める、もちろん眼も使う。
道具を使う。ルーペ、定規、顕微鏡・・・。
比較する。研究の基礎ですよね。
数量的にみる。研究方法がわかんなかったら、とにかく数を数えろ!!ってやつですww
予想(疑問)を持ってみてみる。
④みつづける
③をすることによって、「これって??」「この場じゃわかんないぞ!?」って疑問を発見すると、調査段階に入ります。夏休みの自由研究って本来はこの段階だと思うし、大学の学部生くらいの初期調査はここに当たるんじゃないでしょーか?
ここで初めて時間軸が加わって、四次元でモノをみるようになるんですねぇ。
⑤みぬく
物事の本質がみえている状態だと思います。
どの分野においても、まだまだここまでは到達している気がしません、あたし自身が

だいぶ偉そうに語っておりますが、もちろん文献より(※)ですよ。
思考整理の役割も果たしてるので、書きながらあたし自身が一番学んでおります^^;
学生のときに学んできたはずなんだけどなぁ・・・

よく文系っぽいってゆわれるんだけど、一応専門は“理科”、なんですよ。。。
ホント文系向きな気がするもん最近・・・。植物の名前とか全然覚えられないし

※『自然観察のし方』ニュー・サイエンス社
「頭のカルテ」で子どもをとらえる技術












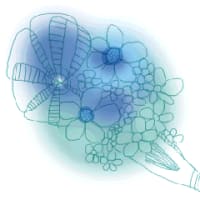







みるかぁ。
おかげで、見るについて改めて考えてたw
あっちゃこっちゃで読んだものが混ざって
どこに書いてあったか忘れたけど、
例えばりんごを見るとき、
我々は、ほぼ、ああ、りんごね、知ってるよ、りんご。
って前提で見ている。
つまり、過去の知識やイメージのフィルターで、りんごを見ている。
そのおかげで実は、りんごそのものを見れていない。
んだそうです。
りんごがりんごそのものである感動を、大人は見失っているというんです。
すげーふけーーーーーwwwwww
めったにそんな域にはいけないですねw
自分が限りなくゼロじゃなきゃなんねーんだもん。
思考をストップさせて物を見るなんて、その本を書いた人はすごすぎw
赤ちゃんの目って、どうしてあんなにパッチリとしてて、きらきらしてんだろ。
きっと余計なフィルターがないから、そのものが新鮮に飛び込んでくるんでしょうね。でも、そのフィルターって、必要ですよねぇ。。。
知っててはずす技術でもあるんでしょうかwきっとそうに違いない。
そんな事この日記読んで思っちゃいました。
なげーコメント失礼しましたw
自分の記事もコメもながーーいもので{汗}
長コメ大歓迎です{キラリ}うれしい{うさぎ}
こーゆーの、めっちゃ興味そそられまくり{ラブ}
想いが深まるときって、快感ホルモンめっちゃ出ます~{アップ}
おかげで見るについて改めて考えられましたww
赤ちゃんの目って、笑顔と同じくらい万国共通じゃないですか?{りんごちゃん}
母性本能くすぐられるのは生きる術ってのもあると思いますが、いつもフレッシュな目でものごとをみつめたいなぁ。
愛でていきたいなぁ{ふたば}
今日の記事は、このコメから触発されネタにけてーーい{パチパチ}</色>