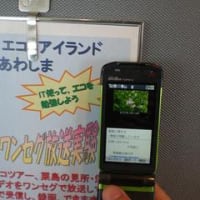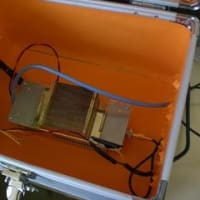オオミズナギドリは朝鮮半島、日本、山東半島(中国)、台湾などで繁殖し、東南アジアやパプアニューギニア沖にかけての海域に移動して越冬する海鳥です。日本近海では、冠島(若狭湾沖)、御蔵島(伊豆諸島)、粟島等に繁殖地があります。粟島では夏鳥として3月頃に渡来し、繁殖の後11月頃に帰って行きます。
海鳥は海洋の生態系における高次捕食者(植物プランクトンは動物プランクトンに食べられ、動物プランクトンは魚に食べられ、魚は海鳥に食べられます)です。海鳥の生態は地球環境の変化を知る手がかりとなるため、最近注目を浴びています。オオミズナギドリの生態を調査することで日本海の海洋生態系の変化を知ることにもなります。
オオミズナギドリは繁殖を開始する年齢が遅く(なかなか大人にならない)、さらに一羽のメスが一つの卵しか産みません(少子化)。今のところは絶滅の危惧に瀕しているわけではありませんが、一度数が減るとその回復にとても時間がかかってしまう鳥なので、今後も適正な繁殖環境を維持していくことが必要です。本来繁殖地にいないネコやドブネズミなど人間が持ち込むことで、繁殖地が壊滅してしまうこともあります。
オオミズナギドリの体長は50㎝ほどで、地上では小さく見えますが、翼を広げると120㎝にもなります。アホウドリなどど同様に広い海洋を渡るためです。頭部は白と黒の細かいごま塩模様、背中側は茶褐色、胴体と翼の下は白色で他の鳥と区別がつきやすいです。長い翼で海面の上昇気流を受け、海上をグライダーのように優雅に帆翔したり、時折、ひらひらと羽をはばたかせて飛んでいます。しかし、陸地から飛びたつのは苦手で、繁殖地では木や斜面の上から飛び降りるようにして飛びたってゆく姿が見られます。潜水は苦手であまり深くまで潜ることはできません。主に海面近くにいる小魚やイカを捕食しています。
繁殖地では巣穴を掘って繁殖し、オスとメスで協力しながら卵とヒナの世話をします。メスとオスは同じ色なので外見からの区別は難しいですが、鳴き声によって容易に区別することができます。オスはキューイキューイと高い声で鳴くのに対し、メスはグェ~と低い声で鳴きます。夜、繁殖地を訪れると雄と雌の鳴き交わす声が飛び交っています。親鳥は朝の暗いうちに海へ飛びたち、昼間海でエサをたらふくお腹に詰め込み、巣穴で待っているヒナのため夜暗くなってから繁殖地に戻ってきます。粟島では8月中旬以降、かわいいヒナたちに会えます。雛ははじめ、黒っぽいふわふわの羽毛で覆われていますが、親が持ってくるエサを食べ、一日に17gというハイスピードで育ち、10月には親よりも大きくなります。親鳥は10月下旬頃からあまり繁殖地にもどらなくなり、早めに南半球目指して渡りをはじめます。雛たちは十分羽が育ち、お腹が空いた11月になって親鳥をおいかけるように南へ渡りを始めます。