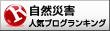(文責 : 防災士 田澤六三)
南海放送NEWS 2024年7月12日14:55配信 などによると、
12日午前3時50分頃、松山市緑町で松山城がある山の斜面が幅50メートル、高さ100メートルにわたって崩れ落ち、複数の住宅やマンションに土砂が流れ込みました。 同所での土砂崩れは少し間を置いて3回発生したという付近住民の証言があります。
巻き込まれた木造住宅に住む90代の夫と80代の妻、40代の息子の3人が、13日、見つかりましたが、いずれも死亡が確認されました。
警察によると、3人は倒壊した住宅の下敷きになるなどして、発生直後にその場で死亡したとみらる、とのことです。
付近の住民の話によるとがけ崩れが発生する前日の方が雨が烈しかったというので、調べてみました。
◆前10日間合計の降水量データでは、
平年の2.4倍ですが、それほど猛烈ではありません。
降水量(mm) 平年比 (%)
愛媛県 松山* 220.5 244
◆前日からの降水量を時系列で見ると、前日の朝4時台に 41mmというたいへん烈しい雨があり、3時間雨量 79mmでした。しかしその後7時台から23時台までは小降りとなり、ゼロも9時間ありました。土砂崩れ発生の当日夜半からまた強い雨が降り出しましたが、避難情報は出ていなかったようです。
雨が止んでも油断できない、ということでしょう。この地点は土砂災害危険区域ではなかったとのことですが、崖に近い住宅では、雨続きの時季にはなるべく2階に寝起きするなど、少しでも命の助かる方法で用心することをお勧めしたいと思います。
◆降水量 時系列データ 観測点=松山
日 時 降水量(mm)
12日 7:00 0.5
6:00 6.0
5:00 9.0
4:00 15.0
3:00 17.5
2:00 2.5
1:00 19.5
11日 24:00 11.0
23:00 4.5
22:00 0.0
21:00 0.5
20:00 3.0
19:00 0.0
18:00 0.0
17:00 0.0
16:00 0.0
15:00 0.0
14:00 0.0
13:00 0.0
12:00 0.0
11:00 3.0
10:00 5.5
9:00 4.5
8:00 2.0
7:00 3.0
6:00 18.5
5:00 19.5
4:00 41.0
3:00 0.5
2:00 0.0
1:00 17.5
10日24:00 9.0
23:00 0.0
22:00 0.0
南海放送NEWS 2024年7月12日14:55配信 などによると、
12日午前3時50分頃、松山市緑町で松山城がある山の斜面が幅50メートル、高さ100メートルにわたって崩れ落ち、複数の住宅やマンションに土砂が流れ込みました。 同所での土砂崩れは少し間を置いて3回発生したという付近住民の証言があります。
巻き込まれた木造住宅に住む90代の夫と80代の妻、40代の息子の3人が、13日、見つかりましたが、いずれも死亡が確認されました。
警察によると、3人は倒壊した住宅の下敷きになるなどして、発生直後にその場で死亡したとみらる、とのことです。
付近の住民の話によるとがけ崩れが発生する前日の方が雨が烈しかったというので、調べてみました。
◆前10日間合計の降水量データでは、
平年の2.4倍ですが、それほど猛烈ではありません。
降水量(mm) 平年比 (%)
愛媛県 松山* 220.5 244
◆前日からの降水量を時系列で見ると、前日の朝4時台に 41mmというたいへん烈しい雨があり、3時間雨量 79mmでした。しかしその後7時台から23時台までは小降りとなり、ゼロも9時間ありました。土砂崩れ発生の当日夜半からまた強い雨が降り出しましたが、避難情報は出ていなかったようです。
雨が止んでも油断できない、ということでしょう。この地点は土砂災害危険区域ではなかったとのことですが、崖に近い住宅では、雨続きの時季にはなるべく2階に寝起きするなど、少しでも命の助かる方法で用心することをお勧めしたいと思います。
◆降水量 時系列データ 観測点=松山
日 時 降水量(mm)
12日 7:00 0.5
6:00 6.0
5:00 9.0
4:00 15.0
3:00 17.5
2:00 2.5
1:00 19.5
11日 24:00 11.0
23:00 4.5
22:00 0.0
21:00 0.5
20:00 3.0
19:00 0.0
18:00 0.0
17:00 0.0
16:00 0.0
15:00 0.0
14:00 0.0
13:00 0.0
12:00 0.0
11:00 3.0
10:00 5.5
9:00 4.5
8:00 2.0
7:00 3.0
6:00 18.5
5:00 19.5
4:00 41.0
3:00 0.5
2:00 0.0
1:00 17.5
10日24:00 9.0
23:00 0.0
22:00 0.0