
埼玉県の誇る名城跡、寄居町の「鉢形城公園」。スタートは「鉢形城歴史館」より。

歴史館の裏からは広大な鉢形城跡。この時期は一面枯葉で覆われます。

深沢川を渡ります。

町指定天然記念物の「鉢形城の桜・エドヒガン」。........ 見事な逆光、血管のようですね。

鉢形城の桜・エドヒガン
エドヒガンは、バラ科の落葉高木種で、花期が早く、関東地方で彼岸の頃に咲くことから、この名前がついた。
このエドヒガンは、二本の幹が一旦伐採され、その株元から十二本の芽が成長したもので、樹高十八メートル、枝張りは、東西二十三・五メートル、南北二十一・八メートル、全体の根回りは六・五メートルほどある。
枝は笠鉾状に広がり、見事な樹形を呈している。
なお、樹勢や聞き取り調査から、樹齢は百五十年ほどと推定される。
平成二十一年三月 寄居町教育委員会

北へ行くと鉢形城跡の本曲輪(ほんくるわ)と続く「伝御殿曲輪(でんごてんくるわ)」になります。

本曲輪にはその景勝を称えた「田山花袋漢詩碑」があります。
襟帯山河好 (襟帯山河好し)
雄視関八州 (雄視す関八州)
古城跡空在 (古城の跡空しく在り)
一水尚東流 (一水尚ほ東流す)

鉢形城本丸跡碑
本曲輪(ほんくるわ)=本丸

鉢形城跡
鉢形城は、荒川に臨んだ絶壁上に位置し、 南には深沢川があって自然の要害をなしています。
文明8年(1476年)に長尾景春が築城し、その後上杉家の持城として栄えました。室町末期に至り、上杉家の家老で、この地方の豪族であった藤田康邦が、北条氏康の三男氏邦を鉢形城主に迎え入れ、小田原北条氏と提携して北武蔵から上野へかけての拠点としました。
城跡は、西南旧折原村を大手口とし、東の旧鉢形村を搦手としています。本丸、二の九、三の丸、秩父曲輪、諏訪曲輪等があり、西南部には侍屋敷や城下町の名前が伝えられており、寺院、神社があり、土塁、空掘が
残っています。
天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めの際、前田利家、上杉景勝、本多忠勝、真田安房守らに四方から攻撃さ、三ヶ月の戦いの後、落城しました。
寄居町・埼玉県
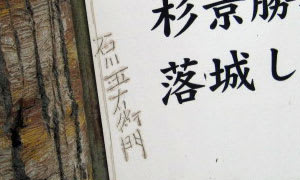
思わず笑ってしまった「石川五右衛門」の落書き。ど~いう発想なんだろう・・・・。でも、落書きはいけませんよ。

伝御殿下曲輪には「花木園」も........、開園は平日のみのようです。

二の曲輪、城山稲荷神社へと鳥居が導いてくれます。

キレイに整備された「二の曲輪」。

「三の曲輪」奥の「伝秩父曲輪」には「四阿」も復原されています。

驚くべき石積み土塁。

復原四脚門(虎口)。

諏訪神社境内へと続く。

諏訪神社
諏訪神社は、武州日尾城主(小鹿野町)諏訪部遠江守が鉢形城の家老となって出仕したとき、信州にある諏訪神社を守護氏神として分祀奉斎しました。
やがて天正18年(1590年)鉢形城の落城により、この近辺から北条氏の家臣たちが落ちていき、人々も少なくなりました。しかし城下の立原の人たちは鎮守様と崇敬し、館の跡を社地として今日の神社を造営した
ものです。
本殿は宝暦年間、その他の建造物は天保年間に造営されていて、年に三度の大祭を中心に、人々の心のよりところとなっています。
なんどかの台風にあいましたが、空掘御手洗池に深い面影を落としている欅の大木は、400年にわたる歴史の重みを静かに語りかけているようでもあります。
祭神は建御名方命、相殿に誉田別命が祀られています。これは明治42年萩和田の八万神社が合祀されたものです。
寄居町・埼玉県

すっかり逆回りをしてしまった「鉢形城公園」でした。

「北条鱗」二等辺三角形です。
 :ここです→ ブログ人マップ
:ここです→ ブログ人マップ

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます