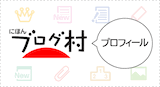全国の天気 今日の天気 明日の天気 週間天気予報 地震情報 台風情報
花粉早くも飛散中!花粉症を重症化させないためにすべき5つのこと

東京では早くも、花粉症の原因とされるスギ花粉の飛散が観測されています。都によると、飛散開始日は1月8日で、1985年の調査開始以来、最も早い飛散となりました。いまや日本人の3人に1人が悩んでいると言われる花粉症。これから2月、3月と花粉が多くなる季節に、仕事や勉強のパフォーマンスを維持するためには、どんなことに気をつけたらいいのでしょうか。専門医に聞いてみました。
くしゃみ・鼻水・鼻づまりに加えて、目のかゆみや充血、せき、喉や皮膚のかゆみ、だるさ、頭痛、熱っぽい感じなど、花粉症ではさまざまな症状がみられます。鼻から体内に侵入してきた花粉(抗原)を異物と認識し、これを排除しようとして過剰な免疫反応(アレルギー)が起きてしまうためと考えられています。
花粉症の7割は、1〜5月に多く飛散するスギの花粉が抗原だと考えられていますが、3〜5月に多くなるヒノキ花粉や、3〜10月に多いイネ花粉、8〜10月に多いブタクサ・ヨモギ・カナムグラなどの花粉が抗原になる場合もあります。どの花粉が原因なのかをつきとめるには、アレルギー反応を引き起こす抗体(IgE抗体)を血液検査で調べることが必要です。
耳鼻咽喉科医で、埼玉医大東洋医学科非常勤講師の齋藤晶さんは、「花粉症は、早めの対策で重症化させないことが大切です」と話します。前年に少しでも症状が出た人は、花粉がたくさん飛散する前から治療を始めると重症化を防ぐことができます。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では2024年から、「花粉症重症化ゼロ作戦」をスタート。ウェブサイト上に花粉症によるパフォーマンス低下度をセルフチェックできるコーナーなどを設けて、早めの受診を呼びかけています。
くしゃみ、鼻水、鼻づまりや喉の症状が強い場合は耳鼻咽喉科を、目の症状が中心の場合は眼科を、せきがひどい場合は内科を、アトピーなど他のアレルギー症状を併発している場合はアレルギー科を受診するとよいそうです。
花粉症と風邪は症状がよく似ていますが、花粉症は鼻水がサラサラして水っぽいことや、目の症状があることが特徴です。風邪と花粉症は同時にかかることもあります。また、風邪をひいている時は、花粉症の症状が出やすくなるので要注意です。
齋藤さんは「『薬は眠くなるから飲みたくない』という方もいますが、症状のごく軽い時から薬を予防的に服用することで、症状の発現を遅らせたり、症状をより軽くしたりすることが期待できます」と話します。治療薬の主流は、眠くなりにくい「第2世代抗ヒスタミン薬」です。薬局で市販薬を選ぶ場合も、仕事中の眠気が気になる人は「第2世代抗ヒスタミン薬」を選ぶとよいといいます。
漢方薬も選択肢の一つです。漢方薬には眠くなる成分が入っていないためです。花粉症や花粉症に伴う症状には、小青竜湯、辛夷清肺湯、葛根湯加川芎辛夷、葛根湯などがよく用いられます。ただし、冷えの有無などその人の体質と症状に合ったものを選ぶ必要があるほか、薬の効果を十分に得るためには2週間程度かかるので、「重症化してからではなく、早めに医師に相談することが大切です」と齋藤さんは強調します。
症状を軽減し、重症化を防ぐには、花粉とできるだけ接触しないようにすることも大切です。具体的には、
〈1〉花粉情報に注意し、花粉の飛散が多い時の外出を控える
〈2〉外出時にマスクやメガネを着用する
〈3〉表面が毛羽立った毛織物などのコートの着用は避け、帰宅後は玄関で衣服や髪をよく払う
〈4〉ふとんや洗濯物の外干しは避ける
〈5〉掃除をこまめに行い、特に窓際は念入りに掃除する
などが挙げられます。
また、アルコールやたばこは、血管を拡張させたり鼻の粘膜を刺激したりして、鼻づまりを悪化させるので、花粉の季節は、お酒の飲み過ぎや喫煙、受動喫煙を避けること。さらには、十分に睡眠を取り、乳酸菌やビフィズス菌などを積極的に取り入れて腸内環境を整え、免疫力を高めるなど、日常生活の改善に努めたいものです。
鼻の奥がムズムズしてきたら、花粉症を疑い、早めの対処を。
(読売新聞メディア局 永原香代子)
※ 2025/01/27 17:10 (大手小町(読売新聞))
の掲載文章から引用しました。参考になれば幸いです。
ブログ村ランキングに参加しています
バナーをクリックして応援お願いします
おすすめのサイト