西アフリカの大西洋岸で、さかんに奴隷貿易が行われていた18世紀、コートジボワール北東部の内陸では、3つの王国が勢力を誇っていたということを記しておく必要がある。その3王国とは、「コン帝国(Kong)」、「ジャマン王国(Gyaman)」、そして「ブナ王国(Bouna)」である。
「コン帝国」は、17世紀に、ジュラ商人(記事「北方帝国の興亡(2)」参照)の一人であった、セク・ウワタラ(Sékou Ouattara、1665年-1745年)が樹立した王国である。セク・ウワタラの家は、マリンケ族の、代々続くジュラ商人の家であった。1700年頃から、サハラ砂漠方面の交易に従事しながら、一方で武装部隊を組織し、やがて隊商の護衛などの活動を行うようになる。
護衛隊長として、隊商とともにサハラ砂漠の南縁の各地を渡り歩くうち、セク・ウワタラは各地の勢力者との関係を築いた。そして、彼らを通じて大商人たちやムスリム勢力の援護を得、1710年に今のコートジボワール北部のコン(Kong)を首都に、王国を樹立した。彼の権力の資金源は、サハラ交易、つまり北方の砂漠方面から持ち込まれる塩と綿布と、南方森林地帯で産する金とコラの実とを交換する商業活動にあった。
ところが、自然崇拝で、農耕を生業とし、土地所有するセヌフォ族地主たちは、彼のイスラム教の政権を認めず、抵抗運動を行った。セク・ウワタラは、このセヌフォ族地主たちを武力で順次制圧し、今のコートジボワール北部から、ブルキナファソの西部(ボボ・デュラソ周辺)にまたがる地域を、勢力下に収めた。コン帝国では、世襲による王が、中央政府と常備軍を備え、カフ(kafu)と呼ばれる地方首長を通して統治する、組織的な統治制度を持っていた。
「コン帝国」は、「ソンガイ帝国」の滅亡(16世紀末)以来にニジェール川流域に現れた、最大の帝国となった。多くの都市が商業で栄えたほか、首都コンにはイスラム知識人が集まり、大学も設立され、文化の花が開いた。この王国は、1897年にフランス植民地に併合されるまで、2世紀にわたり続いた。
ちなみに、コン帝国の沿革を辿ると、なんだか現代コートジボワール政治と不思議に重なる。つまり、「北方起源」の「商業」を営む「イスラム教」の部族が、「ウワタラ」という名前の指導者に率いられて、外からやってきて政権を作り、もとからいた「農業」で地主である「自然崇拝」の部族が反発する。そして、コン帝国にはたくさん勇猛果敢な武将がいたのだが、その中に何人も「ソロ」という苗字の武将がいる(特に有名なのが、ナンギン・ソロ(Nanguin Soro))。
これは、1990年代に、故ウフエボワニ大統領の跡目相続で、北部部族出身のウワタラ元首相が名乗りを上げ、都市の商業・サービス業従事者を地盤に勢力を伸ばし、これに南部部族出身で農民層を地盤にするベディエ大統領やバグボ大統領らが反発したこと、また、2002年に北部から起きた軍事蜂起の首謀者が、今のソロ首相であることなどと、奇妙に符合して興味深い。コートジボワール人の潜在意識には、コン帝国の物語が、一つの参照として働いているかもしれない。
さて、二つ目の王国、「ジャマン王国」は、17世紀の半ばごろ、今のガーナ方面にいたアカン系のアブロン族(Abron)が西へ移動し、コートジボワールの東北地域で、ボンドゥク(Boudoukou)を本拠地にして築いた国である。移民を率いたタン・ダテ(Tan Daté、生没年不詳)は、先住民であるセヌフォ族(この地方ではナファナ族と呼ばれた)やクランゴ族(Koulango)を征服して王国の基礎を築いた。それから5代目のコホソヌ王(Kohossonou)は、さらに勢力を広げ、今のコートジボワール・ガーナ国境からコモエ川までの広い地域を、王国の領域に収めた。
王国としての体制が固まり、「ジャマン王国」と呼ばれるようになったのは、1690年。この国では、農耕民族のヴォルタイック系部族であるセヌフォ族とクランゴ族、マンデ系のジュラ族、そして征服民族であるアカン系のアブロン族の、3つの系統の民族が共存していた。そして、セヌフォ族とクランゴ族が土地を支配し、ジュラ族が商業と宗教を支配し、アブロン族が貴族として政治権力と軍事を支配するという分業にあったことが注目される。
また、王家を2つの系統に分け、片方をヤカセ(Yakassé)の村に、もう片方をザンザン(Zanzan)の村に置き、交互に王様を立てるという決まりにした。この制度は、王国の安定性を高めたといえる。ジャマン王国は、1740年に東隣の強国アシャンティ王国から攻撃され、一旦はその軍門に下った。しかし国の独立性を失うことなく、アシャンティ王国が弱くなったと見れば、何度も反乱を起こすなど、活発に活動した。最後は、1875年にフランス植民地に併合されている。
三つ目の王国は、「ブナ王国」である。この王国は、先の「ジャマン王国」のちょうど北隣にあって、両国は熾烈なライバル関係にあった。現コートジボワールの北東の端にブナという町があり、そこが首都である。ブナは、南北と東西の交易路の交差点であり、昔から商業を中心に経済活動が盛んであった。16世紀ころに、今のガーナにあった「ダゴンバ王国(Dagomba)」のブンカニ(Bunkani)という王子が、この地方に移住し、ブナを本拠地にして王国を作った。以来、ブンカニの子孫が3家に分かれ、王位はその3家が順に継承するという決まりになった。
ブナの町は通商の要地であり、またブナの近辺には金鉱山もあったので、ブナ王国は周囲から常に狙われ、攻撃を受けた。とくに18世紀の初めから、ジャマン王国との抗争は果てしなく続いた。ブナ王国は、ジャマン王国を東から攻めていたアシャンティ王国と同盟を結んで挟み撃ちにする戦略を取って、国を守った。
アフリカにヨーロッパ列強が進出し、その植民地になっていく以前の歴史を調べると、このように、じつに多彩な王国と文化が栄えていたことがわかる。それは、「暗黒大陸」という表現からはほど遠い。英国人やフランス人が、19世紀にアフリカ大陸の内陸部に足を踏み入れ始めたとき、どうして「暗黒大陸」と表現したのだろうか。そのために、アフリカは未開の地で蒙昧な人々しか住んでいない地である、という通念が出来上がってしまった。
現実のアフリカには、多くの民族が住み、数々の王国が興亡史を刻んでいる。それぞれの王国は、それぞれ立派な統治制度、社会文化を持っていた。私にとっては、「暗黒大陸」どころか「色彩豊かな大陸」である。
<地図>
最新の画像[もっと見る]
-
 二つの報道
15年前
二つの報道
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
 白黒はっきりしない理由
15年前
白黒はっきりしない理由
15年前
-
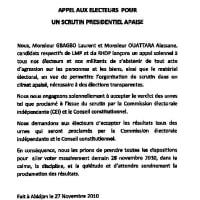 大使たちが動く(2)
15年前
大使たちが動く(2)
15年前











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます