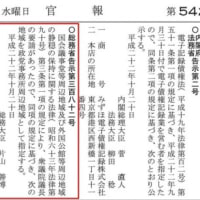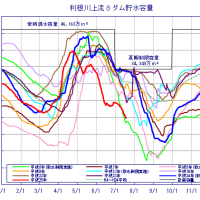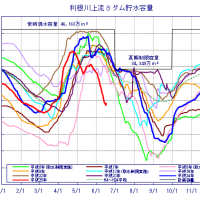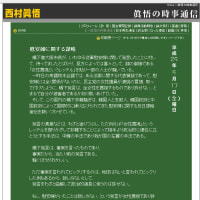ぼやきくっくり■2/27放送「アンカー」青山繁晴の“ニュースDEズバリ”
ただ、日本的には分かる(納得はしないが)。自衛隊は兵器のユーザーであって、船はその運び屋だ。だから、関係ない場面(そんなものはないのだが)では、それこそ殆ど寝ていてもかまわない、という思想が生まれてしまったのだ。商船のメーカーの感覚が伝染したというか、軍事の発想が根本的に弱いところの、現れなのだ。
追記:
自動操舵の実態や事実は確認を要する話。安定を保つための、例えば船のスタビライザーや、飛行機のタブないしトリムのような仕組みがある。自動車のオートクルーズはスピードを一定に保つだけで、解除はアクセルかブレーキを踏むだけでよい。だから自動操舵を解除しなかったのは、現状維持で直進の意思を持っていた段階では、人間の操舵とあまり意味が変わらない気もするのだ。
ところで、一番愕然とすべきなのは、イージス艦の「ぬかり」以上に、事件の警察権、捜査権を海上保安庁が握っていることだ。これは日本では、いつもの事だから気づきにくいが、およそ軍事常識とはかけ離れている。恐るべき事態なのに、今の日本には、これを変える手立ても機運もない。その状況がもたらすものが、兵器クラブとしての自衛隊なのだ。軍事において、兵器はその一部でしかないのに。

自動操舵っていうのは本来こういう戦闘艦、軍艦にはありえないことなんです。(中略)世界の海軍にとっても非常識です。というのは戦闘艦、軍艦っていうのはたくさんの人間が乗ってます。たくさんの人間で交替にやりますから、つまり必ず必要な人間は起きてますから、自動操縦にする意味がないわけです」(中略)その別な艦長に聞いたらですね、『青山さん、これははっきり言うと、この船を造る時にね、日本のメーカーで造る時に、こういうのあったら便利ですよと言われて、そのまま、そうですかとつけちゃったんですよ』と」(中略)『つけたけれども使わないはずだった』と。『まさか使う艦長がいるとは私は夢にも思わなかった。私の艦では一度も使ったことがない』と」「自動操舵」の装置があること自体が、異例というより、非常識だったのだ。軍艦は(ドックで修理中以外は)要員が少数でもなく、寝ているわけもない。航行中の(いや停泊中であっても)軍艦にオフデューティはない。「自動操舵」ははじめから必要ない装置だったのだ。
ただ、日本的には分かる(納得はしないが)。自衛隊は兵器のユーザーであって、船はその運び屋だ。だから、関係ない場面(そんなものはないのだが)では、それこそ殆ど寝ていてもかまわない、という思想が生まれてしまったのだ。商船のメーカーの感覚が伝染したというか、軍事の発想が根本的に弱いところの、現れなのだ。
追記:
自動操舵の実態や事実は確認を要する話。安定を保つための、例えば船のスタビライザーや、飛行機のタブないしトリムのような仕組みがある。自動車のオートクルーズはスピードを一定に保つだけで、解除はアクセルかブレーキを踏むだけでよい。だから自動操舵を解除しなかったのは、現状維持で直進の意思を持っていた段階では、人間の操舵とあまり意味が変わらない気もするのだ。
ところで、一番愕然とすべきなのは、イージス艦の「ぬかり」以上に、事件の警察権、捜査権を海上保安庁が握っていることだ。これは日本では、いつもの事だから気づきにくいが、およそ軍事常識とはかけ離れている。恐るべき事態なのに、今の日本には、これを変える手立ても機運もない。その状況がもたらすものが、兵器クラブとしての自衛隊なのだ。軍事において、兵器はその一部でしかないのに。