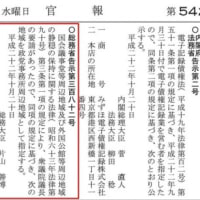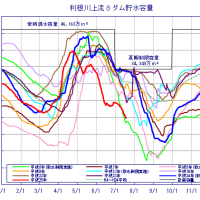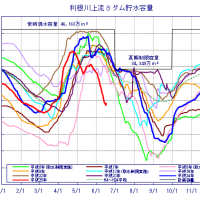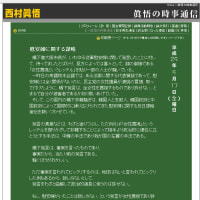池田信夫blog:相撲部屋の構造
アメリカだって、東海岸と西海岸では話が真逆なのだ。東海岸は日本に似ている。西海岸は、何というか.... IT産業の特徴と言われているものの大部分は西海岸というかシリコンバレーで自然発生していたカルチャーそのものだったりするようだ(ちょとうろ覚え
西海岸が東海岸のデジタル産業を圧倒したのは、市場を通じてであった。
ところで、供給側の話はそうかもしれないが、需要側(購買側)の特性が問題でもある。日本では、ちょっと市場が予測しづらい。ガラパゴスは需要側が作っている。市場のニーズに答えていたら、自然に日本的特殊市場になるというものだろう。しかし日本の市場が求めていたのは、例えばiPodだし、iPhoneだった。もちろん、実際はガラパゴス市場と拮抗しているけれど、イノベーションは海外からやってきた。日本発のアイデアよりは、舶来か、あるいは逆輸入である。一々(国内で)アイデアをつぶされるよりは、海外市場か、逆輸入を目指した方が早いかもしれない。

日本人も長期的関係を自覚的に選んだわけではなく、自分たちのやりやすいように組織をつくった結果、たまたまそれが20世紀後半の知識集約的な製造業に適していたにすぎない。すべてのテクノロジーを「相撲部屋」型の長期的関係に帰着させる日本人の行動様式(中略)基本的には、新しい企業が古い企業を倒すことによってしかフレーミングは変わらない。それが日本の必要とする本質的なイノベーションである。日本の社会様式が、偶然「20世紀後半の知識集約的な製造業に適していた」。うんうん、である。まあよく言われている話かもしれない。社会様式と(ここで表現したが)言っても、色々な要素の複合体なので、いざ分析となると面倒だが、本当はちゃんと分析すべきなのだろう。
アメリカだって、東海岸と西海岸では話が真逆なのだ。東海岸は日本に似ている。西海岸は、何というか.... IT産業の特徴と言われているものの大部分は西海岸というかシリコンバレーで自然発生していたカルチャーそのものだったりするようだ(ちょとうろ覚え
西海岸が東海岸のデジタル産業を圧倒したのは、市場を通じてであった。
ところで、供給側の話はそうかもしれないが、需要側(購買側)の特性が問題でもある。日本では、ちょっと市場が予測しづらい。ガラパゴスは需要側が作っている。市場のニーズに答えていたら、自然に日本的特殊市場になるというものだろう。しかし日本の市場が求めていたのは、例えばiPodだし、iPhoneだった。もちろん、実際はガラパゴス市場と拮抗しているけれど、イノベーションは海外からやってきた。日本発のアイデアよりは、舶来か、あるいは逆輸入である。一々(国内で)アイデアをつぶされるよりは、海外市場か、逆輸入を目指した方が早いかもしれない。