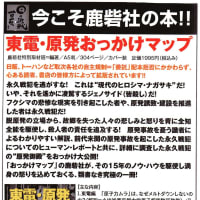もう少しアナルコ・キャピタリズムについて考えてみたい。前に、アナキズムに近い概念にリバタリニズムとサンディカリズムとがあるものの、アナキズムとの区分けを小生はよく理解していない旨を述べた。それでも小生の理解としては、リバタリニズムとは自由放任主義とでも訳されるもので、権力に対して否定的ではあり、経済思想としてはアダム・スミスの「神の見えざる手」を楽観視したものといえるという解釈をしたつもりである(これが間違っていたら、どなたかご教示願います)。一方、アナルコ・キャピタリズムとは無政府資本主義とでも訳されるのだろうか。決して小生の造語などではなく、70年代から提唱されてきた概念であり、小生は読んでいないけれどもデヴィッド・フリードマン著『自由のためのメカニズム――アナルコ・キャピタリズムへの道案内』(勁草書房)なんて本もあるくらいだ。結局、両者は同じようなものとしていいだろう。したがって、以下ではアナルコ・キャピタリズムに統一して表記する。
それがなぜグローバリゼーションに発展するのかという問いがわき起こる。これは単純な話で、企業活動というものは一国の枠内に収まらないからである。原料の調達先、人件費の低い国での工場操業、大きな市場のある資本主義国への販売と、ある企業が収益を上げるときはどうしても複数の国にまたがってしまう。したがって、そこでの関税障壁が低ければ低いほど、企業活動は活性化する。さらには関税ゼロへと向かうことになる。その裏側の、ならば農業生産物はどうなるのかという問題はさておくとし、こうして巨大企業であればあるほど国家という壁の存在が邪魔者になっていく。さらには、その国家の側の高級官僚もこうした資本主義企業の論理を内面化していくから、自国窮民の存在など忘れ、企業の論理に追随し(さらには先導し)ていくことになる。それが資本主義の必然であることは、マルクスが『資本論』第1巻第25章「近代植民理論」で予見的なラフスケッチが提示されていたように思う(その内容は忘れた)。
要するに、グローバリゼーションを正当化するイデオロギーの一つがアナルコ・キャピタリズムであるということを述べているわけである。そこで、小生にとっては半解な言葉であるが、ワン・ワールドという考えがあるのを思い出した。世界が一つになれば人類はさらに幸福になるだろうということなのだろう(再び、間違っていたらご教示を)。その語の起源も、変遷も、現在における影響力も知らないが、おそらくはユダヤ=キリスト教的な発想なのだろう。世界中の人々が同じ神様(なりイデオロギー)を信仰し、同じ言葉を話し、同じマナーを身に付け、同じものを食し、同じ嗜好なり道徳を共有すれば、平和に満ち溢れた豊かな社会が世界中に実現するというものだ。つまりはユートピア思想の一種である。このワン・ワールド思想というものがグローバリゼーションに流れ込んでいることも明らかだけれども、その過程を小生は非学にして知らない。ボリシェヴィッキもインターネットも、究極としてはワン・ワールドを目指していた(る)。そこで、その制度設計者に与えた影響がどういうものなのかを知らないということである。こういう話はちょっとふくらませるとすぐにトンでも系になってしまうので、そうではなく、実証的にきっちりと説明している書籍があったら読みたいところだ。
また脱線が始まった。脱線ついでにリバタリニズムを再度取り上げたい。リバタリニズムに似た概念にリベラリズムというものがある。こちらは日本語に訳すと自由主義ということになるのだろうか。そこで、リベラリズムというとかなり保守的なニュアンスが色濃くなる。日本の代表的なリベラリストとなるとだれなのか小生には皆目見当もつかないが、「洋行経験のある初老の裕福なじいさんで、軍部独裁には反対で社会主義にある程度の理解はあるものの、しかし結局は社会主義者ではなくどこか一家言持った人」みたいなイメージになってしまう。そうすると、小生がそのエキスでも吸おうかと思っている対象がそのリベラリストなのだということでもある。
前に林健太郎を俎上にのせたことがあったけれど、彼よりも前の世代のリベラリストというのは、かなり味わい深かったのではなかろうかと想像する。ここでの「味わい深い」とは「やっかい」の同意語になってしまうだろうけれど、例えば永井荷風なんて老境にさしかかってからは、ただの面倒くさいじじいであったにちがいない。しかしその荷風にしても、ある戒律を踏みにじるとき、なんらかの覚悟があったはずだ。その戒律とは、例えば、家制度なり明治国家なりが押し付ける立身出世であったことだろう。実は小生、『断腸亭日乗』(岩波文庫)を読んでいないので荷風の狷介ぶりをよく知らないのだけれど、ここでの主眼はそこにあるのではなく、戒律がないことをリバタリニズムはよしとするのであるが、果たしてそれでいいのかという疑念を抱いているということである。
それがなぜグローバリゼーションに発展するのかという問いがわき起こる。これは単純な話で、企業活動というものは一国の枠内に収まらないからである。原料の調達先、人件費の低い国での工場操業、大きな市場のある資本主義国への販売と、ある企業が収益を上げるときはどうしても複数の国にまたがってしまう。したがって、そこでの関税障壁が低ければ低いほど、企業活動は活性化する。さらには関税ゼロへと向かうことになる。その裏側の、ならば農業生産物はどうなるのかという問題はさておくとし、こうして巨大企業であればあるほど国家という壁の存在が邪魔者になっていく。さらには、その国家の側の高級官僚もこうした資本主義企業の論理を内面化していくから、自国窮民の存在など忘れ、企業の論理に追随し(さらには先導し)ていくことになる。それが資本主義の必然であることは、マルクスが『資本論』第1巻第25章「近代植民理論」で予見的なラフスケッチが提示されていたように思う(その内容は忘れた)。
要するに、グローバリゼーションを正当化するイデオロギーの一つがアナルコ・キャピタリズムであるということを述べているわけである。そこで、小生にとっては半解な言葉であるが、ワン・ワールドという考えがあるのを思い出した。世界が一つになれば人類はさらに幸福になるだろうということなのだろう(再び、間違っていたらご教示を)。その語の起源も、変遷も、現在における影響力も知らないが、おそらくはユダヤ=キリスト教的な発想なのだろう。世界中の人々が同じ神様(なりイデオロギー)を信仰し、同じ言葉を話し、同じマナーを身に付け、同じものを食し、同じ嗜好なり道徳を共有すれば、平和に満ち溢れた豊かな社会が世界中に実現するというものだ。つまりはユートピア思想の一種である。このワン・ワールド思想というものがグローバリゼーションに流れ込んでいることも明らかだけれども、その過程を小生は非学にして知らない。ボリシェヴィッキもインターネットも、究極としてはワン・ワールドを目指していた(る)。そこで、その制度設計者に与えた影響がどういうものなのかを知らないということである。こういう話はちょっとふくらませるとすぐにトンでも系になってしまうので、そうではなく、実証的にきっちりと説明している書籍があったら読みたいところだ。
また脱線が始まった。脱線ついでにリバタリニズムを再度取り上げたい。リバタリニズムに似た概念にリベラリズムというものがある。こちらは日本語に訳すと自由主義ということになるのだろうか。そこで、リベラリズムというとかなり保守的なニュアンスが色濃くなる。日本の代表的なリベラリストとなるとだれなのか小生には皆目見当もつかないが、「洋行経験のある初老の裕福なじいさんで、軍部独裁には反対で社会主義にある程度の理解はあるものの、しかし結局は社会主義者ではなくどこか一家言持った人」みたいなイメージになってしまう。そうすると、小生がそのエキスでも吸おうかと思っている対象がそのリベラリストなのだということでもある。
前に林健太郎を俎上にのせたことがあったけれど、彼よりも前の世代のリベラリストというのは、かなり味わい深かったのではなかろうかと想像する。ここでの「味わい深い」とは「やっかい」の同意語になってしまうだろうけれど、例えば永井荷風なんて老境にさしかかってからは、ただの面倒くさいじじいであったにちがいない。しかしその荷風にしても、ある戒律を踏みにじるとき、なんらかの覚悟があったはずだ。その戒律とは、例えば、家制度なり明治国家なりが押し付ける立身出世であったことだろう。実は小生、『断腸亭日乗』(岩波文庫)を読んでいないので荷風の狷介ぶりをよく知らないのだけれど、ここでの主眼はそこにあるのではなく、戒律がないことをリバタリニズムはよしとするのであるが、果たしてそれでいいのかという疑念を抱いているということである。