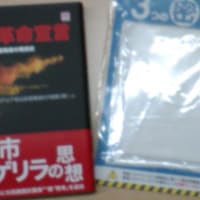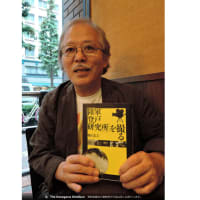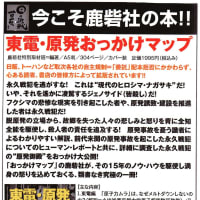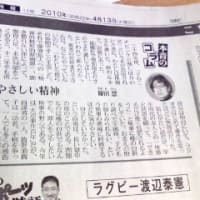世の中には、新刊書籍から専門雑誌からネットまで網羅的に目配りをしている人がいて、そういう人の話を聞いていると尊敬してしまう。小生の場合、ここ十数年、雑誌を講読したことがない。まだ若い時分、出張の多かったときは、暇つぶし用に雑誌(主になつかしの『噂真』)を買って、安いビジネスホテルの狭いバスタブにつかりながら、缶ビールを飲みつつ読んでいたものであるけれど、どういうわけかはわからないが、書籍とちがって雑誌は読んでも内容をすぐに忘れてしまうのだ。
酔っていても本を読むことはあるけれど、翌朝になって「あれっ?なにが書いてあったっけ?」と思い起こすことは少ない(内容が難しくてまったく理解できない場合は多い)。しかし、雑誌の場合は翌日になると読んだ内容がほとんど思い出せない。同じ活字媒体というのに、不思議なものである。無意識の領域で、雑誌に対する差別意識でも働いているのだろうか。それと、毎週なり毎月なり買うのも面倒くさく、おかげで、ご恵投いただく『紙の爆弾』以外の雑誌はほとんど読んでいない。
超零細とはいえ、一応は出版社のオヤジという立場なので、雑誌も読まないとはなにごとか!というお小言を頂戴してもかまわないのであるけれど、ただしかし、雑誌を読んでないからといって、これまで困ったことは一度もない。電車のなかで中吊り広告をながめておけば、それで十分である。また、ああした広告というのは作りが上手だから、購買意欲を高めるためのキャッチコピーが面白い。それを眺めて、内心でクスッと笑っておけば、それでなんだかわかったような気になってしまう。
かなり以前のことであるが、Oさんという方に、「最近はどういうものを読まれるのですか?」とたずねたことがあった。するとOさん、突然口調が熱くなり、「僕は月刊誌の熱心な読者なんだよ」と答えた。少し意外な感がして、「月刊誌ってなんかの専門誌ですか?」とまたたずねる。すると、「そうじゃなくて、僕は『諸君!』(現在廃刊)とか『正論』をいつも読んでいるんだ」。ニセ左翼非暴力主義者のOさんが、そういう保守系の月刊誌の読者?こちとら、ハア?てなもんだ。
そこから始まるOさんの熱い説明を聞いて納得したのだけれど、要するに保守論壇を批判するためには、保守派の言説をきっちりと把握しなければならないじゃないかということである。これには、なるほどねえと感心した。さらにOさんの素晴らしいところは、「したがって腹巻くん、君も保守系のオピニオン誌くらい目を通しておかないとまずいじゃないか」とは言わなかったところである。そんな行為はただの苦行でしかなく、それを他者に押し付けようなどとはしないのだ。そしてOさんは、その研究(?)成果として拉致問題についての書籍を上梓されたのだから、保守系雑誌の解読にかなりの精力を費やされたことであろう。
これに似て非なる話で、Hさんというすでに亡くなられた方と小生は懇意であった。あるとき、某所で待ち合わせることになった。こちらが先にその場所に着いたので、詰碁の本でも見ていたのか、普通になにかの本を読んでいたのかは覚えていない。だいたい、どこで待ち合わせたのかも忘れちゃった。うすら覚えだけれど、雨の日だったような気もする。Hさんも予定時間ギリギリに姿を現した。そして、小生が書籍様のものを熱心に眺めている姿を目にしたのだろう。開口一番、「腹巻くん、これあげるから、これを読みなさい」と、手にしていた雑誌を手渡された。
その上から目線の物言いにいささかムッとしつつ渡された雑誌を見れば、『軍事研究』なるこれまで手にしたことのない専門誌である。「きみはこういうものを読んだことがないだろ」とHさんは言葉を続ける。確かに読んだことはない。しかし、その言い方が気に入らない。そこで反発気味に、「はい、読んだことがないので、どこをどういうふうに読んだらいいんですか?」と、疑問系で憤懣をぶつけてみた。
するとHさんは、「そんなことはどうでもいいから。家に帰ってゆっくり読めば、資本主義の断末魔の喘ぎが聞こえてくるよ」と答える。フーン、そういうものですかと、その場は二人して某件(内容は忘れた)に向かうことになった。そして帰宅後、手渡されたその『軍事研究』を一生懸命に読んでみたのであるが、どこに資本主義の喘ぎがあるのかいっちょんわからんとばい。「Hのオッサン、なん言いよっとや!」というのがそのときの気分ではあったけれど、おそらくはそうではないのである。Hさんとしては、小生の視界を少しでも広げてやろうという親心ではなかったのか、といまでは想像する。
ここまで記してきてふと気がついたのだけれど、上記二つのエピソードは以前にもこの場に記したことがあるかもしれない。同じ話を何度も述べるのはかなり気がひけるのだけれど、Hさんの命日が近くなってきたので、ついつい昔話を思い出してしまった。Hさんとはかなり激しい口論をしたこともある。しかし、小生のそういう生意気さを、Hさんには受け入れてもらえたものだと信じたい(そうでないとしても、Hさんへのこちらの敬意が変わるわけではない)。
酔っていても本を読むことはあるけれど、翌朝になって「あれっ?なにが書いてあったっけ?」と思い起こすことは少ない(内容が難しくてまったく理解できない場合は多い)。しかし、雑誌の場合は翌日になると読んだ内容がほとんど思い出せない。同じ活字媒体というのに、不思議なものである。無意識の領域で、雑誌に対する差別意識でも働いているのだろうか。それと、毎週なり毎月なり買うのも面倒くさく、おかげで、ご恵投いただく『紙の爆弾』以外の雑誌はほとんど読んでいない。
超零細とはいえ、一応は出版社のオヤジという立場なので、雑誌も読まないとはなにごとか!というお小言を頂戴してもかまわないのであるけれど、ただしかし、雑誌を読んでないからといって、これまで困ったことは一度もない。電車のなかで中吊り広告をながめておけば、それで十分である。また、ああした広告というのは作りが上手だから、購買意欲を高めるためのキャッチコピーが面白い。それを眺めて、内心でクスッと笑っておけば、それでなんだかわかったような気になってしまう。
かなり以前のことであるが、Oさんという方に、「最近はどういうものを読まれるのですか?」とたずねたことがあった。するとOさん、突然口調が熱くなり、「僕は月刊誌の熱心な読者なんだよ」と答えた。少し意外な感がして、「月刊誌ってなんかの専門誌ですか?」とまたたずねる。すると、「そうじゃなくて、僕は『諸君!』(現在廃刊)とか『正論』をいつも読んでいるんだ」。ニセ左翼非暴力主義者のOさんが、そういう保守系の月刊誌の読者?こちとら、ハア?てなもんだ。
そこから始まるOさんの熱い説明を聞いて納得したのだけれど、要するに保守論壇を批判するためには、保守派の言説をきっちりと把握しなければならないじゃないかということである。これには、なるほどねえと感心した。さらにOさんの素晴らしいところは、「したがって腹巻くん、君も保守系のオピニオン誌くらい目を通しておかないとまずいじゃないか」とは言わなかったところである。そんな行為はただの苦行でしかなく、それを他者に押し付けようなどとはしないのだ。そしてOさんは、その研究(?)成果として拉致問題についての書籍を上梓されたのだから、保守系雑誌の解読にかなりの精力を費やされたことであろう。
これに似て非なる話で、Hさんというすでに亡くなられた方と小生は懇意であった。あるとき、某所で待ち合わせることになった。こちらが先にその場所に着いたので、詰碁の本でも見ていたのか、普通になにかの本を読んでいたのかは覚えていない。だいたい、どこで待ち合わせたのかも忘れちゃった。うすら覚えだけれど、雨の日だったような気もする。Hさんも予定時間ギリギリに姿を現した。そして、小生が書籍様のものを熱心に眺めている姿を目にしたのだろう。開口一番、「腹巻くん、これあげるから、これを読みなさい」と、手にしていた雑誌を手渡された。
その上から目線の物言いにいささかムッとしつつ渡された雑誌を見れば、『軍事研究』なるこれまで手にしたことのない専門誌である。「きみはこういうものを読んだことがないだろ」とHさんは言葉を続ける。確かに読んだことはない。しかし、その言い方が気に入らない。そこで反発気味に、「はい、読んだことがないので、どこをどういうふうに読んだらいいんですか?」と、疑問系で憤懣をぶつけてみた。
するとHさんは、「そんなことはどうでもいいから。家に帰ってゆっくり読めば、資本主義の断末魔の喘ぎが聞こえてくるよ」と答える。フーン、そういうものですかと、その場は二人して某件(内容は忘れた)に向かうことになった。そして帰宅後、手渡されたその『軍事研究』を一生懸命に読んでみたのであるが、どこに資本主義の喘ぎがあるのかいっちょんわからんとばい。「Hのオッサン、なん言いよっとや!」というのがそのときの気分ではあったけれど、おそらくはそうではないのである。Hさんとしては、小生の視界を少しでも広げてやろうという親心ではなかったのか、といまでは想像する。
ここまで記してきてふと気がついたのだけれど、上記二つのエピソードは以前にもこの場に記したことがあるかもしれない。同じ話を何度も述べるのはかなり気がひけるのだけれど、Hさんの命日が近くなってきたので、ついつい昔話を思い出してしまった。Hさんとはかなり激しい口論をしたこともある。しかし、小生のそういう生意気さを、Hさんには受け入れてもらえたものだと信じたい(そうでないとしても、Hさんへのこちらの敬意が変わるわけではない)。