カトリック河原町教会で開催された、「詞が開いた心の扉~奈良少年刑務所の社会製管用プログラムから~」(死刑をやめよう宗教者ネットワーク主催)に参加してきました。
以前に、このブログでも紹介した、作家寮美千子さんの講演です。

講演内容は、以前に伺ったものと基本的に同じなので、詳細は前回の記事をご覧ください。
リンクはこちら http://blog.goo.ne.jp/tsuji-defender/d/20121124
実際に受刑者と向き合い、その教育に携わってこられたという実体験に基づく話、
そして、寮さんの人への優しさや情熱があふれる感動的な講演でした。
弁護士も何人か来ていましたが、もっと多くの弁護士がこの話を聞くべきだと思います。
今年は、京都弁護士会の刑事委員会の委員長だから何か企画しよう!
さて、寮さんが指導に行っておられた奈良少年刑務所というのはこんなところです。

まるで、ディズニーランドかUSJかと思うような門構えです。
中の建物は、こんな感じです。

奈良少年刑務所の建物は、明治41年に完成、山下啓次郎という司法相の建築家の設計です。
レンガ造りの建物なのですが、このレンガは受刑者たちが焼いたレンガ、すべて手焼きのレンガで、一枚一枚色合い、風合いが異なるということです。
東京駅の丸の内口の赤レンガ駅舎が話題になっていますが、東京駅の駅舎のレンガはすべて工業レンガ、工場で機械生産されたレンガで、とても手焼きレンガの風合いにはおよばないそうです。
どうして、刑務所にこれほど素敵な建物が建てられたかというと、明治時代、外国との間の不平等条約の撤廃というのが政府の大きな課題でした。
不平等条約の大きな一つが「治外法権」
日本政府は、外国人が犯罪を犯しても、日本の裁判所で裁判をすることができませんでした。
日本の刑事司法が整備されておらず、刑務所も極めて劣悪なものしかなかったため、外国は、自国の国民を日本の裁判を受けさせることを拒んでいたのです。
そこで、不平等条約の撤廃を外国にアピールするために立派な監獄が作られました。
同じような問題は今でもあります。
現在でも、日本には死刑度があるために、外国に逃亡した犯罪者をするという条約を日本はほとんど締結できていません。
そのため、日本で殺人事件を犯した犯罪者は、外国に逃げてしまえば、日本の警察に引き渡されることがありません。
死刑廃止国からすれば、自国で同じ犯罪を犯しても死刑にはならないのに、日本に引き渡してしまうと、死刑で殺されてしまうかもしれないということになれば、それは引き渡すことはできませんよね。
死刑制度があるために、日本が司法権を行使できないという場面があるのです。
さて、立派な監獄は、明治の五大監獄といわれ、千葉、金沢、奈良、長崎、鹿児島にありました。
しかし、その後、次々と建て替えが行われてしまい、当時の建物が残っているのは奈良だけだそうです。
奈良少年刑務所も、文化財指定などがされていないため、いつ取り壊されてもおかしくない状況だそうです。
こうした建物はぜひ残して行ってもらいたいものです。
そういえば、裁判所も立派な建物がいっぱいあったのですが、次々に建て替えられて現代的なビルになってしまっているところがたくさんありますね。
奈良少年刑務所は、奈良市内で比較的便利な所にあるので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。
年に一度、『奈良矯正展』というのが開催されて、一般の人も中を見ることができるようです。
そういう私も、一度も見たことがないので、ぜひ見学に行ってみたいと思います。


















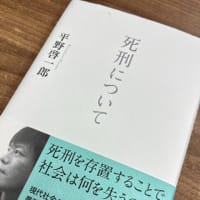
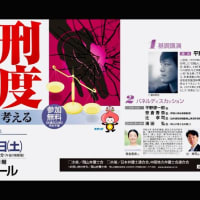
みちこ→美千子です。よく間違われます。
『空が青いから白をえらんだのです 奈良少年刑務所詩集』
http://amzn.to/soragab
ぜひ、お聴きしたかったです。
見学もできればいいなと思います。
以前の記事でを読んで『空が青いから白をえらんだのです 奈良少年刑務所詩集』をすぐに買って読みました。
その時からずっと、いつか朗読できればと思っています。
綴られているお母さんへの思い…。
この少年たちの「これから」を思わずにはいられません。
次の機会があるときには、あらかじめブログでも告知しますね。
寮さんの講演、ぜひ、聞いてみてください。
よろしくお願い致します。