
「ハロウィン」とは、毎年11月1日に行われる「万聖節(ばんせいせつ)」の前夜祭。
毎年10月31日に行われ(今年の31日は月曜日)、
本来は秋の収穫を祝い、悪霊を追い出すお祭りです。
そして、11月1日の「万聖節(ばんせいせつ)」とは、
キリスト教であらゆる聖人を記念する祝日で、
カトリック教会では「諸聖人の祝日」と呼ばれているそう。
また、プロテスタント教会では「聖徒(せいと)の日」と呼び、
死者を記念するのだとか。
本場アメリカでは、カボチャをくりぬき、
目・鼻・口などをつけた
「おばけカボチャの提灯(ジャック-オ-ランタン)」を飾り、
夜には怪物に仮装した子供たちが近所を回り、
お菓子をもらったりします。
これはもともと、家のまわりを徘徊し、
人間にとりつこうとする悪霊たちが、
その姿を見て驚いて逃げるようにするためだったそう。
お菓子をもらうようになったのはわりと最近のことなのだとか。
青字は、Weekly Mixing! ハッピーハロウィンより引用
つまり、今日がハロウィーン当日なのです。
まあ、日本で言うお盆のようなものなんですね~。
聖者と死者を弔い、悪霊を追い払う儀式みたいです。
かぼちゃをくりぬいたランタン(ジャック・オー・ランタン)は、
さしずめお盆の送り火という所でしょうか?

「トリック・オア・トリート(Trick or Treat)」
(いたずらか?もてなしか?)
と子供たちが近所の家々をお化けのかっこうをしてまわり、
お菓子をいただきます。
もし、お菓子をくれないとか、留守だとその家のガラス窓に
石鹸を塗りたくるいたずらをしちゃってもいいんだとか・・・。
(実は私は、小さい時学校の関係でハロウィンパーティを
やってました。ランタンも作りました。)
この習慣は、クリスマスの時期の酒宴
(古い英語で wassailing と呼ばれる) の習慣に似た、
soulingと呼ばれるヨーロッパの習慣から発展したと思われる。
11月2日の死者の日に、キリスト教徒は「魂のケーキ」
(soul cake)――干しぶどう入りの四角いパン――を
乞いながら、村から村へと歩いた。
物乞いをするときには、亡くなった親類の霊魂の天国への道を
助けるためのお祈りをすると約束した。
魂のケーキの分配は、サウィン祭のとき徘徊する幽霊に
食べ物とワインを残す古代の風習に代わるものとして、
キリスト教会によって奨励された。
(略)
古代ケルトのドルイド教では、新年の始まりは冬の季節の
始まりである11月1日のサウィン祭であった。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「ハロウィン」より青字引用

わかりますか?
11月1日は、「諸聖人の祝日」
11月2日は、「死者の日」なのです。
ハロウィンは、諸聖人を讃えると共に死者の弔いを
行った日なんです。
古代ケルト人までさかのぼると、ずいぶん昔からのお祭りなんですね・・・。
ちょっと、話がそれますが・・・。(日本の田舎の話・・・。)
先日、私の家には実家の母が滞在し、
俳句の好きな母と吟行の旅に出ていましたが、
その中で蛇塚なるものを見ました。
江戸の頃、大飢饉があり何万人も餓死したのだそうです。
それからほどなく、その土地に赤い蛇が何匹も出た。
その蛇たちは、飢饉で餓死した人たちが
供養をもとめていた出ていたとの事。
そこで、そこに塚を作り供養したら赤い蛇は出なくなった。
その塚の下に穴のようなくぼみがあるのですが、
何千人の行き倒れの餓死した人々の死体をいっしょに
埋めた場所なんだそうです。
私と母は、その塚の前で手を合わせてきました。
安らかにお眠りくださいますようにと・・・。
おそらく、飢饉や餓死はアメリカにもヨーロッパにも
あったことでしょう。
いろんな事情で物乞いをする人も、いたのだと思います。
ちょっとしめっぽくなっちゃいましたが・・・。
楽しいハロウィンももちろん賛成ですが、
万聖節を考えると・・・。
そんな、亡くなった人たちの供養のため祈るのも
いいのではないかなあなんて感じたのでした。
それから、偉大なる土地の精霊たちに・・・。
敬意をこめて・・・。
お盆ですからね~。
ジャック・オ・ランタン(かぼちゃ提灯)の作り方♪
毎年10月31日に行われ(今年の31日は月曜日)、
本来は秋の収穫を祝い、悪霊を追い出すお祭りです。
そして、11月1日の「万聖節(ばんせいせつ)」とは、
キリスト教であらゆる聖人を記念する祝日で、
カトリック教会では「諸聖人の祝日」と呼ばれているそう。
また、プロテスタント教会では「聖徒(せいと)の日」と呼び、
死者を記念するのだとか。
本場アメリカでは、カボチャをくりぬき、
目・鼻・口などをつけた
「おばけカボチャの提灯(ジャック-オ-ランタン)」を飾り、
夜には怪物に仮装した子供たちが近所を回り、
お菓子をもらったりします。
これはもともと、家のまわりを徘徊し、
人間にとりつこうとする悪霊たちが、
その姿を見て驚いて逃げるようにするためだったそう。
お菓子をもらうようになったのはわりと最近のことなのだとか。
青字は、Weekly Mixing! ハッピーハロウィンより引用
つまり、今日がハロウィーン当日なのです。
まあ、日本で言うお盆のようなものなんですね~。
聖者と死者を弔い、悪霊を追い払う儀式みたいです。
かぼちゃをくりぬいたランタン(ジャック・オー・ランタン)は、
さしずめお盆の送り火という所でしょうか?

「トリック・オア・トリート(Trick or Treat)」
(いたずらか?もてなしか?)
と子供たちが近所の家々をお化けのかっこうをしてまわり、
お菓子をいただきます。
もし、お菓子をくれないとか、留守だとその家のガラス窓に
石鹸を塗りたくるいたずらをしちゃってもいいんだとか・・・。
(実は私は、小さい時学校の関係でハロウィンパーティを
やってました。ランタンも作りました。)
この習慣は、クリスマスの時期の酒宴
(古い英語で wassailing と呼ばれる) の習慣に似た、
soulingと呼ばれるヨーロッパの習慣から発展したと思われる。
11月2日の死者の日に、キリスト教徒は「魂のケーキ」
(soul cake)――干しぶどう入りの四角いパン――を
乞いながら、村から村へと歩いた。
物乞いをするときには、亡くなった親類の霊魂の天国への道を
助けるためのお祈りをすると約束した。
魂のケーキの分配は、サウィン祭のとき徘徊する幽霊に
食べ物とワインを残す古代の風習に代わるものとして、
キリスト教会によって奨励された。
(略)
古代ケルトのドルイド教では、新年の始まりは冬の季節の
始まりである11月1日のサウィン祭であった。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「ハロウィン」より青字引用

わかりますか?
11月1日は、「諸聖人の祝日」
11月2日は、「死者の日」なのです。
ハロウィンは、諸聖人を讃えると共に死者の弔いを
行った日なんです。
古代ケルト人までさかのぼると、ずいぶん昔からのお祭りなんですね・・・。
ちょっと、話がそれますが・・・。(日本の田舎の話・・・。)
先日、私の家には実家の母が滞在し、
俳句の好きな母と吟行の旅に出ていましたが、
その中で蛇塚なるものを見ました。
江戸の頃、大飢饉があり何万人も餓死したのだそうです。
それからほどなく、その土地に赤い蛇が何匹も出た。
その蛇たちは、飢饉で餓死した人たちが
供養をもとめていた出ていたとの事。
そこで、そこに塚を作り供養したら赤い蛇は出なくなった。
その塚の下に穴のようなくぼみがあるのですが、
何千人の行き倒れの餓死した人々の死体をいっしょに
埋めた場所なんだそうです。
私と母は、その塚の前で手を合わせてきました。
安らかにお眠りくださいますようにと・・・。
おそらく、飢饉や餓死はアメリカにもヨーロッパにも
あったことでしょう。
いろんな事情で物乞いをする人も、いたのだと思います。
ちょっとしめっぽくなっちゃいましたが・・・。
楽しいハロウィンももちろん賛成ですが、
万聖節を考えると・・・。
そんな、亡くなった人たちの供養のため祈るのも
いいのではないかなあなんて感じたのでした。
それから、偉大なる土地の精霊たちに・・・。
敬意をこめて・・・。
お盆ですからね~。
ジャック・オ・ランタン(かぼちゃ提灯)の作り方♪


















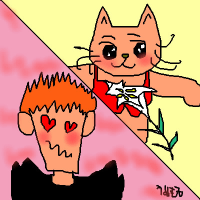

ハロウィンですね。今日は・・。
おばけが出てきたり、魔女が出てきたり、ハロウィンは日本のお盆のようなものですね。
日本に定着するのは、そういう意味ではなく、仮装してお菓子をもらうというものになりそうな気がします。クリスマスのように・・。
いまブログに追記させていただきました。
亡くなられた方の供養と言う意味はいいですね。
単なるお祭りとしか、知らなかった私は
勉強になりました。
ただのお祭りでなく、大人はきちんと意味を理解し
亡くなられた方の供養と、改めて生かされている
と言う事実を感謝したいです。
(知ってるね。)
子供のころ、ランタンを作り、ろうそくに火を灯すのが大好きでした。
お化けの変装も考えて作るのが楽しくてね~。
(もしや・・・私は、アキバ系もイケルのか???)
otacoさんの絵、うまいね~。夢があります。
子供はお化けもお菓子も魔法も好きですもんね・・・。
ちなみに、小さい時は魔法使いになりたかった私でした~。
いろんな宗教行事やその土地のお祭りなどから生まれていったみたいです。
死者の霊を供養するのは、お盆と同じです。秋ですから、収穫祭の意味もあったのですね~。
お祭りは人の心にもカラダにもいいんだそうです。
大好きな、レオ・バスカリア博士の言葉です。
学生の頃、
1日にミサを、11月最初の日曜日に
キリシタン殉教の地で
ミサを行った記憶が蘇りました。
11月1日、「諸聖人の祝日」の前日はお祭りではなく
”やはり”ボランティア活動でしたよ。
これは、ホラではないです。念のため
卵に色とりどりの色をつけてお祝いするよね?
アレ、記憶が正しければ、七面鳥のクランベリーソースがけを食べるのもツイスターじゃなかったか???
ブッシュ大統領の好物だったような・・・?
ボランティア活動をするのは、すばらしいねっ!
ホラ貝吹いてお祝いしてあげます♪
「ぶう~っぶう~っ♪」
天然ピュアなあなたがすきよ。
竜巻に巻かれて飛んで行けぇぇぇ
スヌーピーのお話の中にも、イースターのワンちゃんというのがありました。
ツイスターというのも、卵なんですね。
これって、カトリックとプロテスタントの違い??
http://www.isedelica.co.jp/info/easter/easter.htm
ゲームもあるわねー、ツイスター。(下の画像・・・ちょびっとセクシー
http://www.tanteifile.com/mission/000/030/035/
こういう意味だったとは・・・。
勉強になりました。
歴史を知らずにただ騒ぐだけでは
大人じゃないですね。
・・・といっても、ウチはとうとう何もしませんでしたが・・・・
たまたま偶然カボチャスープを食べた位ですかね・・・。