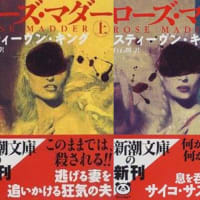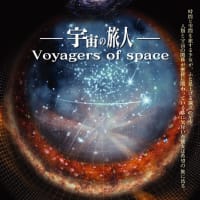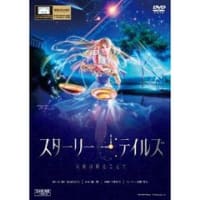新潮文庫 1985年刊 480円
下巻を、先日漸く読了。
途中、大分と違う本に手を出してしまっていたため、すっかりと遅くなって
しまった。
上巻のレビュー時にも書いたが、本書では、作者の織り成す虚実の糸をその
語り口に織り込むことで、作者の主張をより明確に浮き彫りにする、という
オーソドックスな方法を採用している。
#もっとも、事実だけであれば、それはルポルタージュになってしまうが。
その代表的な存在が、マリー・アントワネットと同じイニシャルを持つ
マルグリット・アルレーと、アニエス(元)修道女である。
マルグリットは、マリーのミラーのような存在として、庶民の側からマリーを
糾弾し、憎み、関わっていく。
そのもっとも大きな舞台として、作者は首飾り事件とコンシェルジュリ牢獄からの
脱獄という二つの見せ場を用意する。
首飾り事件では、マルグリットは偽王妃としてロワール大司教に拝謁の栄を賜る
という形で関与する。
#勿論実際には、この役はニコルという娼婦が割り当てられた。
彼女は、その後の裁判で、意味も分からず単に言われるがままに演じただけと
判決が下され、無罪となっている。
史実では、首飾り事件の主役は言うまでも無くラ・モット伯爵夫人であるが、
作者は更にその黒幕として、カリオストロも登場させている。
この辺りは、歴史的にも確たる情報がある訳でもなく、真偽の判断は誰にも
つけられない部分である。
#ラ・モット伯爵夫人は裁判でカリオストロ主犯説を主張したが、認められ
なかった(これは事実)。
また、ラ・モット伯爵夫人は有罪判決を受けて投獄中のサルペルオール監獄
から脱獄。イギリスへ逃亡し、そこで嘘で塗り固めた首飾り事件の回想録を
出版。マリー・アントワネットが実は(当時の庶民的感覚では『やはり』と
なるのかもしれないが)主犯だとか、本当はレズビアンだとか、それこそありと
あらゆる罵詈雑言(しかし、生活に困窮した庶民の溜飲を下げるための
ベクトルとは見事に合致)を盛り込んだそれは、マリーをとてつもない醜聞に
叩き込むことになる。
しかも、裁判を通じてベルサイユの豪奢な生活が庶民に改めて露呈し、
第三身分の平民の不平不満の潮位を一気に押し上げる原動力にもなった。
#その後、フランス革命期に、亡命先のイギリスで死亡したが、その死因に
ついては精神錯乱を起こした上の事故という話と、自殺説。他殺説と今だ
特定されていない。死しても尚、人を惑わし続ける夫人ではある。
そのラ・モット伯爵夫人の行いはともかく、生命力たるや凄まじいものがある。
もっとも、上記のようなラ・モット伯爵夫人に関する逸話は、殆ど本書では
触れられることは無い。この魅惑的な伯爵夫人も、作者にはさらりと流して
しまう存在でしかないことが、僕にとっては不満が残る一因でもある。
そしてマルグリットも、どちらかといえば巻き込まれ型で事件に参加した
こともあり、いまひとつ精彩を欠いている。
これは、最後の山場であるコンシェルジュリからの脱獄計画に際しても
そうである。
マルグリットは、事件を感知し密告、更にスパイとして脱獄を計画中の
王党派に潜入するという動きを起こすが、やはりいずれも巻き込まれ型の
枠を出ておらず、マリーを憎むという強い意志こそは光彩を放つものの、
その存在そのものについてはあまり魅力的な造形と為り得ていない。
ただ、フェルセンを首魁とする王党派の策謀により、マルグリットを
王妃の身代わりとして断頭台に送り、その隙にマリーを救出しようと
する作戦は、すんでのところで成功しそうであった。
それが不首尾に終わったのは、子供達を残して一人脱獄する積りは無いと
するマリーの意思故であった。
しかも計画を聞かされたマリーは、自分の身代わりになる女性を是非
救ってやって欲しいと、計画を伝えに来た自分付きの召使ロザリーに
諭すのである。
こうしてマルグリットは、憎んで余りあるマリーに、その命を救われる
という状況に陥る。
このことはマルグリットのあずかり知らぬ話として作者のペンは進んで
いくが、全てを知る読者からは人がどれほどの激情に駆られて行動した
としても、計り知れない大きな運命の中で転がされていくようなことは
確かに有るのだ、と知らされる。
これを、どう捕らえるべきであろうか。
歴史の歯車の中で、人がどれほど意思を持とうと、結局は大きなうねりに
翻弄されていくだけ、という意図なのか。
それとも過度に作中人物を彫り下げず、距離感を保って描いていこうとした
作者の手法が、人物描写の不足のように思わせてしまうものなのか。
これは、マルグリットの対極に位置するマリーにしても同じである。
上巻ではひたすら能天気なマリー。
下巻では、革命の渦に飲み込まれながらも、必死で王家としてのプライドを
維持し続けようとするマリー。
作者は丹念にそのマリーの生と死を追いながら、マリーの奥深いところには
決して踏み込んでいないような気がする。
そうした氏の乾いた文体は、まるで200年余りを経て尚あの時代から迸る
エネルギーの奔流に巻き込まれまいとするガードにも思える。
が、僕としては、もっとどろどろとそれぞれの作中人物の内面を照らし出す
ような文章が好みなのだが。
(その2)アニエス編。そして集大成へと続く。
下巻を、先日漸く読了。
途中、大分と違う本に手を出してしまっていたため、すっかりと遅くなって
しまった。
上巻のレビュー時にも書いたが、本書では、作者の織り成す虚実の糸をその
語り口に織り込むことで、作者の主張をより明確に浮き彫りにする、という
オーソドックスな方法を採用している。
#もっとも、事実だけであれば、それはルポルタージュになってしまうが。
その代表的な存在が、マリー・アントワネットと同じイニシャルを持つ
マルグリット・アルレーと、アニエス(元)修道女である。
マルグリットは、マリーのミラーのような存在として、庶民の側からマリーを
糾弾し、憎み、関わっていく。
そのもっとも大きな舞台として、作者は首飾り事件とコンシェルジュリ牢獄からの
脱獄という二つの見せ場を用意する。
首飾り事件では、マルグリットは偽王妃としてロワール大司教に拝謁の栄を賜る
という形で関与する。
#勿論実際には、この役はニコルという娼婦が割り当てられた。
彼女は、その後の裁判で、意味も分からず単に言われるがままに演じただけと
判決が下され、無罪となっている。
史実では、首飾り事件の主役は言うまでも無くラ・モット伯爵夫人であるが、
作者は更にその黒幕として、カリオストロも登場させている。
この辺りは、歴史的にも確たる情報がある訳でもなく、真偽の判断は誰にも
つけられない部分である。
#ラ・モット伯爵夫人は裁判でカリオストロ主犯説を主張したが、認められ
なかった(これは事実)。
また、ラ・モット伯爵夫人は有罪判決を受けて投獄中のサルペルオール監獄
から脱獄。イギリスへ逃亡し、そこで嘘で塗り固めた首飾り事件の回想録を
出版。マリー・アントワネットが実は(当時の庶民的感覚では『やはり』と
なるのかもしれないが)主犯だとか、本当はレズビアンだとか、それこそありと
あらゆる罵詈雑言(しかし、生活に困窮した庶民の溜飲を下げるための
ベクトルとは見事に合致)を盛り込んだそれは、マリーをとてつもない醜聞に
叩き込むことになる。
しかも、裁判を通じてベルサイユの豪奢な生活が庶民に改めて露呈し、
第三身分の平民の不平不満の潮位を一気に押し上げる原動力にもなった。
#その後、フランス革命期に、亡命先のイギリスで死亡したが、その死因に
ついては精神錯乱を起こした上の事故という話と、自殺説。他殺説と今だ
特定されていない。死しても尚、人を惑わし続ける夫人ではある。
そのラ・モット伯爵夫人の行いはともかく、生命力たるや凄まじいものがある。
もっとも、上記のようなラ・モット伯爵夫人に関する逸話は、殆ど本書では
触れられることは無い。この魅惑的な伯爵夫人も、作者にはさらりと流して
しまう存在でしかないことが、僕にとっては不満が残る一因でもある。
そしてマルグリットも、どちらかといえば巻き込まれ型で事件に参加した
こともあり、いまひとつ精彩を欠いている。
これは、最後の山場であるコンシェルジュリからの脱獄計画に際しても
そうである。
マルグリットは、事件を感知し密告、更にスパイとして脱獄を計画中の
王党派に潜入するという動きを起こすが、やはりいずれも巻き込まれ型の
枠を出ておらず、マリーを憎むという強い意志こそは光彩を放つものの、
その存在そのものについてはあまり魅力的な造形と為り得ていない。
ただ、フェルセンを首魁とする王党派の策謀により、マルグリットを
王妃の身代わりとして断頭台に送り、その隙にマリーを救出しようと
する作戦は、すんでのところで成功しそうであった。
それが不首尾に終わったのは、子供達を残して一人脱獄する積りは無いと
するマリーの意思故であった。
しかも計画を聞かされたマリーは、自分の身代わりになる女性を是非
救ってやって欲しいと、計画を伝えに来た自分付きの召使ロザリーに
諭すのである。
こうしてマルグリットは、憎んで余りあるマリーに、その命を救われる
という状況に陥る。
このことはマルグリットのあずかり知らぬ話として作者のペンは進んで
いくが、全てを知る読者からは人がどれほどの激情に駆られて行動した
としても、計り知れない大きな運命の中で転がされていくようなことは
確かに有るのだ、と知らされる。
これを、どう捕らえるべきであろうか。
歴史の歯車の中で、人がどれほど意思を持とうと、結局は大きなうねりに
翻弄されていくだけ、という意図なのか。
それとも過度に作中人物を彫り下げず、距離感を保って描いていこうとした
作者の手法が、人物描写の不足のように思わせてしまうものなのか。
これは、マルグリットの対極に位置するマリーにしても同じである。
上巻ではひたすら能天気なマリー。
下巻では、革命の渦に飲み込まれながらも、必死で王家としてのプライドを
維持し続けようとするマリー。
作者は丹念にそのマリーの生と死を追いながら、マリーの奥深いところには
決して踏み込んでいないような気がする。
そうした氏の乾いた文体は、まるで200年余りを経て尚あの時代から迸る
エネルギーの奔流に巻き込まれまいとするガードにも思える。
が、僕としては、もっとどろどろとそれぞれの作中人物の内面を照らし出す
ような文章が好みなのだが。
(その2)アニエス編。そして集大成へと続く。