米国に在って、日本、ヨーロッパに無いものにショートオーバルコースがあります。ロードレース中心だったヨーロッパでは、最初から馴染まないものだったでしょう。日本では、ギャンブルレースのイメージが強すぎるでしょう。しかし面白いものらしいですね。INDYカーだと20秒台で1周1マイルを廻ります。その目まぐるしさは、ちょっとライブで見てみたい。競艇、オートレースなどのギャンブルレースの(ギャンブルを抜きにした)レースとしての良さが、少しずつ認識されています。余計な先入観無しにショートオーバルの良さを味わってみたいです。下は、アメリカのフェニックス1マイルオーバルです。面白い事に、フェニックスは市街地を閉鎖してF1を開催し、1マイルオーバルでINDYカーを楽しんでいた訳です。陸上競技場、サッカースタジアムより少し大きく、競馬場位の大きさ。これで楽しめれば、これで良いじゃない。という所でしょうか。ちなみに、パイクスピークにも1マイルオーバルがあるそうでです。つまり、オーバルレースを楽しむ一方で、あの有名なヒルクライムも楽しんでいる訳です。いかにもアメリカ人らしい楽しみ方です。


米国 Phenix International Speedway
ところで、1963~1965年頃、まだダートだったギャンブルレース場(0.5マイル)でストックカーレースが行われました。主催は、NACの塩澤進午氏。アメリカンレースを正確に認識していればこそ、ギャンブルレース場という一面的なイメージに拘らず、開催できたのでしょう。今のもてぎは、立派過ぎるかもしれません。

800mダートの頃の川口オートレース場
昭和40年代にまだ4輪ギャンブルレースが
行われていた
ところで、この4輪ギャンブルレーサー。トヨタ博物館に保管されている筈です。それ以外に地方の博物館で持っていたかな?どちらにしても数台が残っているだけでしょう。後はスクラップでしょうね。ギャンブルという色眼鏡で見ると無視されがちですが、歴史の一こまとして記録されるべきだと思います。戦後まもなくの黎明期には、旧オオタなども製作にかかわっています。つまり、戦前の多摩川レースや、小規模な国産車製作の歴史からのつながりも含めて記録されるべきだと思います。
-----------------------------------2009/2/25------------
以上は2年前に書いたものですが、読み返してそれ程変なことは書いていないと思います。そこで、米国でのダートオーバルを振り返ってみたいと思います。
米国でのダートオーバルレースとミジェットカーの文化的背景が感じられる風景を。米国の田舎道にチョコンと存在している「博物館」。中に昔のミジェットカーが展示してあります。近くにダートオーバルコースも存在しているみたいです。「草レース場」と「田舎の博物館」というところでしょうか。草の根のレース文化ですね。
何故か、1969年にマリオアンドレッティがINDYに勝ったホーク・フォードが展示してあります。この博物館の目玉でしょう。
参照させていただいたサイト----->ココ
現在のミジェットカーレースを以下に

 現在のミジェットカーは、ロールケージ付き。もてぎでこれと似た形のものが導入された筈ですが。
現在のミジェットカーは、ロールケージ付き。もてぎでこれと似た形のものが導入された筈ですが。
Midget Racing On Clay
-----------------------------------2011/9/7------------










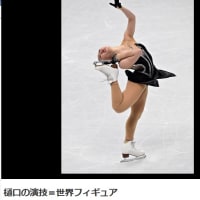






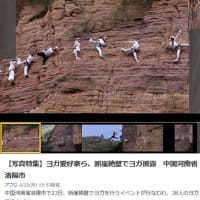




2011/7/2
2010/3/17
日本だと、ちょっと前でカローラを年間出場するとなれば1千万はラクにかかるというのですから。ビックリしました。そりゃかかり過ぎだよ、と。そんなんじゃあ広がりようがないなあとつくづく思いました。