人間は、現代の競争社会に生きながら、常に他者と戦っています。他者を陥れることで、自分を優位に立たせようとします。ところが、戦いは勝者を生む一方で敗者を生み、必ず禍根を残します。この連鎖は、断ち切られることなく続いていき、さらなる戦いの種を撒き散らしながら、大きくなっていくのです。これが人間の戦いの歴史であると考えます。
しかし、戦わなくて済むかというと、けっしてそういうわけでもありません。既に戦いの連鎖が始まってしまっている以上、そこでまったく戦わないなどという選択肢はないのです。残念ながら、人間は戦っていかなければならないということも、また事実でしょう。
それでは、人間はどのように戦っていかなければならないのでしょうか。そのヒントは、古来の戦う人々の生き方にあると思います。
日本には「武士」という戦う人々がいました。そして武士には、武士として生きるべき道、武士道というものがあります。これに対して、西洋にも戦う人がいました。騎士です。そして騎士にも、日本の武士道と同じように騎士道というものがあるといいます。
ところで武士にしても、騎士にしても同じ「戦士」ではありますが、その精神は全く異なるのではないかと思います。以下、端的に比較してみました。
騎士道には十戒というものがあります。
1.不動の信仰と教会の教えへの服従
2.教会擁護の気構え
3.弱者への敬意と憐れみ、弱者を擁護する確固たる気構え
4.愛国心
5.敵前からの退却の拒否
6.封主に対する厳格な服従。ただし神に対する義務に反しない限り
7.異教徒に対する休み無き、慈悲無き戦い
8.真実と誓いに忠実であること
9.惜しみなく与えること
10.悪の力に対抗して、何時いかなる時も、どんな場所でも正義を守ること
もともと騎士道は、キリスト教を守る戦士のための戒律であるため、「弱者への敬意と憐れみ」といったキリスト教的思想が入ると同時に、「教会の守護」や「教会への服従」のほか「異教徒との戦い」といった考え方が取り込まれています。
これに対して、武士道にはさまざまな考え方、解釈があるため一概には言えませんが、例えば梅谷忠洋氏著の「武士道の智恵」では、武士道を以下10の言葉で表しています。
1.仁:苦しんでいる人の隣にいて、苦しみを共にすること
2.義:相手に迷惑を掛けないこと
3.礼:他人に対する思いやりを形で表現すること
4.智:知っているだけでなく行動に移すこと
5.信:義と誠を身につけることで自ずとついてくるもの
6.勇:社会や他人に不愉快な思いをさせないこと
7.誠:嘘をつかないこと
8.名誉:名を汚さぬ心
9.廉恥:自分の未熟を悟り、恥を知ること
10.忠義:義があれば自ずとたどりつくもの
この武士道と騎士道を比較すると、以下のことが言えると思います。
1.他者の位置づけ
武士道にも、騎士道にも同じように「他者」が出てきます。騎士道の場合には「弱者」、「悪」、「異教徒」、「封主」、「教会」というように、同じ「他者」についても、いくつかの分類がなされています。これに対して、武士道では「弱者」も「強者」もなく、「善」も「悪」もなく、「仲間」も「敵」もありません。あるのは単に「他人」、少し表現を変えるとしても「社会」、あるいは「相手」といった程度です。そこにはその「他者」とは何であるかを問題にしておらず、すべての「他者」は等しく「他者」であるのです。
2.意思の所在
人間は意思を持つ生物ですが、武士と騎士では、明らかに意思の所在が異なります。武士は自らの意思をもち、それに伴う責任において行動をとります。これに対して、騎士は自分の意思を持たず、行動規範を他人に預けてしまっています。教会は明らかに他者ですが、それが正しいかどうかの自ら判断することは許されておらず、その教会や教えに対する不動の信仰心は、まずそれありきである。教会や封主に対する厳格な服従も然り。そこには、自ら考えるということが許されておらず、その姿はほとんど機械に等しいのです。
3.戦うことの意味
騎士道では「教会の擁護」、「封主への服従」、「異教徒の殲滅」、「悪への対抗」といった理由を挙げつつ、これに対する慈悲なき戦いこそが正義であると位置づけています。決められた正義のために多くの人々を殺す、そのことこそが騎士としての価値になっています。これに対して、武士道のなかにはそもそも「戦う」という言葉がありません。敢えて言うなら「名誉」を守るため、名を汚さぬために最後の手段として戦うことがある、といったところでしょうが、決して「戦え」と言っているわけではないのです。
以上のことを整理すると、端的に表現すれば、騎士とは自ら考えることを許されず、与えられた正義のために、ひたすら多くの人を殺す、いわば戦闘マシーンです。これに対して、武士とは尊厳ある意思をもった人間であり、常に自らの正義を問い詰め、またそれを他人に押し付けることはなく、好んで戦わず、しかし尊厳や名誉を守るためには、やむを得ず剣を抜く戦士であるということができるでしょう。
競争原理で成り立っている現代社会において、人間は戦っていかなければなりません。けれども、騎士のように自らの正義について、真剣に問い詰めることもなく、ひたすら人を陥れていくような戦い方をしていては、この戦いの連鎖はけっして断ち切れないと思うのです。
戦いの連鎖を断ち切っていくためには、人間ひとりひとりが、常に武士の心持ちでいることが大切です。人間としての尊厳をもち、自ら考え、そもそも戦うべき相手が誰なのかを問い詰めていくという思考を続けていくことが必要であると思います(「打ち克つべき相手」参照)。すべての人間が騎士ではなく、武士のような戦い方ができる戦士になったとき、人類の戦いの歴史には終止符が打たれるはずです。















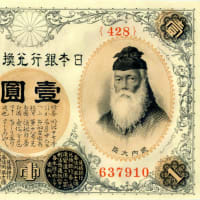
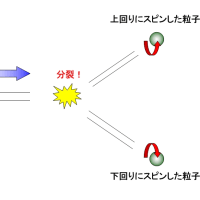
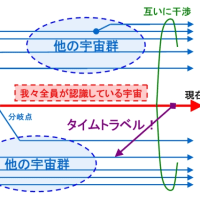
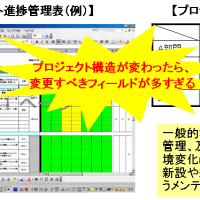
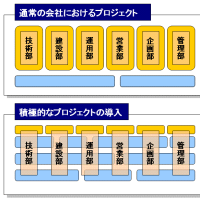





騎士はまず守護者であって弱者を守るものです。
弱者の保護は主君と同等の重さでした。
5、6ですが騎士は複数の領主と契約を結び主君は複数いました。したがって主君同士が戦う場合、当然、自分で判断しなくてはなりませんし、日本の武士のような絶対忠誠はありません。契約が切れると戦闘中であっても戦闘を放棄することができました。
また、機械的判断で行動するとありますが、最後は神の声に耳を傾けます。それこそ自分の良心であり、自己判断でした
また騎士は9番の「与える者」です。このことは「気前のよさ」にあらわれますが、いうなれば自己犠牲をする者です。
そのほかにも寛容、誠実、礼儀、崇高、公正といった言葉が並びます
一方武士の忠誠と保護は主君に対してであって、弱者にではありません。農民を大事にするのは彼らが封建社会の生産者であるからいなくなると困るという現実的な理由です。
「騎士道」をそのように運用されるのであれば、非常によいのではないかと思います。そしてまた、どんなに良いことを言っても、突き詰めれば、解釈や運用の問題になるもかもしれません。
これから先も、しばらく止まぬであろう戦争や紛争において、「弱者」を守るという理由で、「他の弱者」を守ろうとする人々を殺す行為が正当化されてはならないし、それを積極的に認めようとするが故に、「神の声」が利用されてはならないと思います。
おっしゃるとおり、その「神」なるものが特定の宗教から出るものではなく、「最後は神の声に耳を傾けます。それこそ自分の良心であり、自己判断でした」というところが、とても大切なポイントのような気がします。