動画コンテンツの配信サイトである「ニコニコ動画」には、いろいろなアマチュアの人々によって掲載された動画像がたくさんあります。そのなかには「演奏してみた」、「歌ってみた」、「踊ってみた」といったカテゴリーで、いわゆるプロではない人々が楽器を演奏したり、歌ったり、踊ったりした様子を撮影したようなものも数多く掲載されています。それらの作品に使用される楽曲のほとんどは、JASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されるべきものであり、本来的には著作権の問題があるのですが、今のところ(一部目立つものを除いて)著作権者に甘く見ていただいているといったところのようです。今後のネット社会における著作権を巡る問題については、あらためて整理するとして、同サイトには、アマチュアながら音楽に関わる優れた才能の持ち主が集まり、それぞれの作品を掲載し、またそれらが互いに融合しながら、多くの人々を楽しませています。
それらの才能の持ち主のうち、「ドの人」という人がいます。「ドの人」というのは、あるピアノを演奏する人なのですが、その人のピアノは「ド」がひとつ壊れていて、演奏されるピアノの映像には「ぶっ壊れてるド↓」という表示があり、視聴者からは「ドの人」と呼ばれているのです(最近、新しいピアノに変わったみたいです)。私自身も「ドの人」の演奏は好きで、いろいろな楽曲の作品を聞きます。聞く人が聞けば、「やはりドがもったいない」ということらしいのですが、私レベルが聞いている限り、ピアノが壊れているかどうかも分からないほど、素晴らしい演奏だったと思うのです。
ところで私は、この「ドの人」の作品を見ているときに、これからのネット社会におけるアーティストのあり方について、ひとつの確信を得たことがあります。「ニコニコ動画」では、動画コンテンツを視聴しているときに、コメントを入力することができ、さらにそれらを他の視聴者と共有できるため、動画コンテンツを見ながら、その瞬間、他の視聴者がどう思っているかを知ることができます。最近は、新しいピアノに変わったせいか、あまり見られなくなりましたが、「ドの人」が出始めた頃は、「ぶっ壊れてるド」を残念がるコメントが多くありました。なかには「うp主(「ドの人」のこと)にピアノを送る!」、「ピアノ買ってあげよう!」といったものも、かなりあったのを覚えています。
もちろん、口先だけのコメントで、実際にピアノを買ってあげるなんていうことを考えているわけではないかもしれません。しかし私は、おそらくそうしたコメントをした人々が、「この人にもっといいピアノで演奏してもらいたい」という気持ちがあったのは事実でしょうし、さらに「いいピアノで演奏してもらうために、多少お金を払ってあげてもいい」と思ったりしたことも事実ではないかと思うのです。
もしそうだとしたら、このことは非常に重要なことです。コンテンツを楽しむ人々は、そのコンテンツが有料で、視聴料が設定されているからお金を払うわけではなく、そのコンテンツが素晴らしいと感じ、それに感動して「ありがとう」、「これからも頑張ってください」という思いを込めて、お金を払いたいと思っているかもしれないということです。
高度に経済システムが発達してしまっている現代社会において、お金を払うというのは、サービスの提供者に対する消費者の義務であるという側面ばかりに目を奪われがちですが、本来大切なのは、消費者(あるいは、この場合は視聴者)が提供されたものの価値を認め、それを素晴らしいと思う気持ちであり、その気持ちをお金で表現した結果が、「お金を払う」という行為であるということを忘れてはならないはずです(「報酬は感謝・感動の証」参照)。
けれども、非常に残念なことに現在のシステムでは、そうした視聴者の思いをかたちとして表現することは、なかなか難しいのです。つまり「お金」という対価で、それに報いるには、著作権という法的問題に加え、それに縛られているメディアシステム全体に問題があるため、それらによって感動している人々の気持ちは、かたちである「お金」として表現され得ず、またそういう人々に感動を提供している才能の持ち主も、それに報われないでいる状況に陥っているわけです(「「才能の無駄遣い」の克服」参照)。
これまでのコンテンツは、システムの技術的要件(コンテンツの制作や配信技術)のため、限られた人々によってしか制作され得ませんでしたし、それを二次利用されることの弊害が大きかったため、そうした被害を防ぐために、著作権によって守られてきました。それは時代の要求であっただろうし、これまで十分に機能してきたのだと思います。しかし、時代は大きく変わりつつあります。コンテンツの制作技術については、PCやソフトウェアの汎用化と普及により、その裾野が大きく広がり、またメディア技術としてのインターネットもブロードバンド化されると共に普及率が高まっているため、既存のメディアを凌ぐ力を持つようになりました(「通信と放送の融合」参照)。
これらのことは、コンテンツ業界において、これまでプロとして活躍されている方々以外で、アマチュアの人々にも、広く活躍の場が整いつつあることを意味しているわけであり、また社会システムは、それらの価値を積極的に認めていくべき時代に入っていることを意味していると思うのです。
こうした新しい時代において、コンテンツの二次利用等、複次利用にはかつてのようなマイナス効果だけではないと思います。今のプロのクオリティではなくても、アマチュアの人々には、多くの人々を十分に楽しませるセンスと技術を備えており、また事実上、そういう現象が無視できない流れとして可視化してしまっている以上、一次的な著作権を有している方々は、むしろこれらの人々の能力や活力をうまく使いながら、さらに多くの人々に喜んでもらえるような仕組みを作り上げていくことを考えていただきたいと思うのです。
例えば、「ドの人」の例を挙げると、「ドの人」は「エヴァンゲリオン」というアニメの「残酷な天使のテーゼ」というテーマ曲を演奏していますが、視聴者のなかには、そのピアノで弾かれたものをアニメの本編に使って欲しいという人もいるようです。それをそのまま鵜呑みにしろというわけではありませんが、例えばそういう要望に応えた別のアマチュアが、「ドの人」のピアノに合わせて、そういう動画を作ったとして、それによって、さらに多くの人々が喜ぶとするならば、それはそれで良いことだと考えてもいいのではないかと思うのです(「楽曲をMP3で欲しい」という要望もありますから、そういう要望に応えようとするとなると、音楽業界の仕組みも変えていかなければならないかもしれません)。
もちろん、これまでコンテンツ・メディア業界を引っ張ってきた方々には、そうした新しい仕組みに対する抵抗感があるだろうことは理解します。また、今まで築き上げられてきたコンテンツの著作権を無視するかのような、新しい流れには絶対に賛同できないという点も十分に分かります。したがって、この問題は今日時点ですぐに決着がつく話ではありません。
ただし、本来コンテンツ・メディア事業というのは、より多くの人々に喜んでもらうというのが本質でしょう。そして、真に「多くの人々に喜んでもらおう」と考えている人が作ったコンテンツは、著作権等を抜きにして、多くの人々から愛されるでしょうし、その創作活動は、必ず多くの人々から支持をされ、結果として「お金」につながっていくようになると思うのです。
その点を踏まえた上で、これからのコンテンツ・メディア業界を考えるときに、上記のような①コンテンツ・メディアシステムの発達、②視聴者に喜んでもらえる価値の提供の2点をけっして忘れてはならないと思うのです。また、こうした問題については、異業界含めて日本の社会全体で考えていくことが肝要であると考えます。そして、その先にある全員参加型のコンテンツ制作体制は、日本の優れた文化を世界に広めていくきっかけになっていくでしょうし、その構築こそがこれからの日本を活気づける非常に大きな鍵になると思うのです。















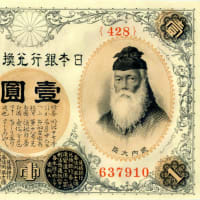
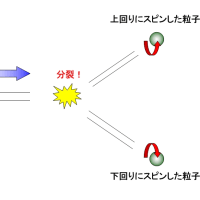
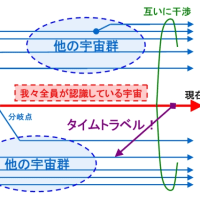
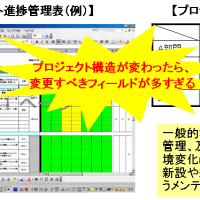
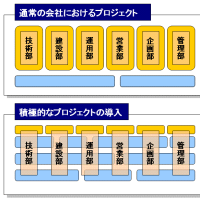





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます