大停電 3時間後復旧 千葉県警クレーン船作業員事情聴く 毎日新聞 2006.8.15
-----転載ここから
調べでは、送電線に接触したのは「三国屋建設」千葉事務所(同県船橋市)の380トンのクレーン船で同所長(43)と操縦士(30)が乗り、しゅんせつ工事に備えて船を固定するための金属製のくいをつり上げる作業をしていた。タグボートには乗組員(23)が乗っていた。クレーンのアームのほぼ中央に黒く焦げた接触痕が確認された。
現場付近には高圧線への注意を呼び掛ける看板が設置されており、同社の内規では「安全を確認できない場合はクレーンを下げて運航する」と定められている。調べに対して3人は「今回の現場に行ったのは初めてで、送電線があるのは知らなかった」と話している。
同社の木股健二会長は「午前6時ごろからクレーン船を動かしていた。操縦士はベテランで、普段は高さを確認していた」と話している。
-----転載ここまで
たまたまお盆で帰省中の出来事だったが、知った時には既にかなり復旧していた。影響を受けた人も多かっただろうだけに、復旧の早さはさすがだと思う。予め想定した手順があったのだろうか。
一方の三国屋建設。本社は茨城にあり、ISO9001を取得している。この9月には更新時期を迎えているから、そろそろ更新審査直前の出来事だったのではないだろうか。まさか千葉営業所は、拡大審査の対象になっていなかったのだろうか?
事故当日の天候も悪くなかったようだし、遵守すべき作業手順に違反して、航行中にクレーンを上げて作業をしていたことが原因だとすれば、効率よく作業を済ませようとして事故を起こした東海村の原子力発電所の臨海事故と同じ構図である。これまでもしばしばやっていた・・・、それまで問題は見られていなかった・・・、本来の手順じゃないと知りつつ継続して行っていた・・・、それが取り返しのつかない大事故に発展した。
経験も十分ある作業員だったというが、教育が徹底されていなかったともいえる。油断もあったのだろうか。安全確認を怠ってしまったその原因は何か。たいした理由ではないと思うのだが、得てしてそんな時に事故は起きるものだ
-----転載ここから
調べでは、送電線に接触したのは「三国屋建設」千葉事務所(同県船橋市)の380トンのクレーン船で同所長(43)と操縦士(30)が乗り、しゅんせつ工事に備えて船を固定するための金属製のくいをつり上げる作業をしていた。タグボートには乗組員(23)が乗っていた。クレーンのアームのほぼ中央に黒く焦げた接触痕が確認された。
現場付近には高圧線への注意を呼び掛ける看板が設置されており、同社の内規では「安全を確認できない場合はクレーンを下げて運航する」と定められている。調べに対して3人は「今回の現場に行ったのは初めてで、送電線があるのは知らなかった」と話している。
同社の木股健二会長は「午前6時ごろからクレーン船を動かしていた。操縦士はベテランで、普段は高さを確認していた」と話している。
-----転載ここまで
たまたまお盆で帰省中の出来事だったが、知った時には既にかなり復旧していた。影響を受けた人も多かっただろうだけに、復旧の早さはさすがだと思う。予め想定した手順があったのだろうか。
一方の三国屋建設。本社は茨城にあり、ISO9001を取得している。この9月には更新時期を迎えているから、そろそろ更新審査直前の出来事だったのではないだろうか。まさか千葉営業所は、拡大審査の対象になっていなかったのだろうか?
事故当日の天候も悪くなかったようだし、遵守すべき作業手順に違反して、航行中にクレーンを上げて作業をしていたことが原因だとすれば、効率よく作業を済ませようとして事故を起こした東海村の原子力発電所の臨海事故と同じ構図である。これまでもしばしばやっていた・・・、それまで問題は見られていなかった・・・、本来の手順じゃないと知りつつ継続して行っていた・・・、それが取り返しのつかない大事故に発展した。
経験も十分ある作業員だったというが、教育が徹底されていなかったともいえる。油断もあったのだろうか。安全確認を怠ってしまったその原因は何か。たいした理由ではないと思うのだが、得てしてそんな時に事故は起きるものだ











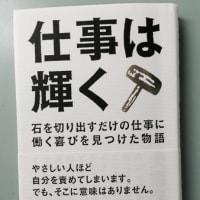
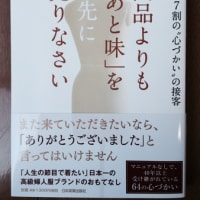
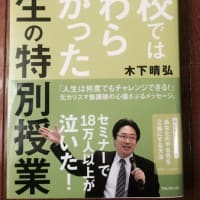
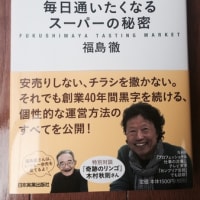
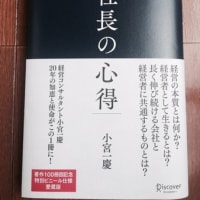
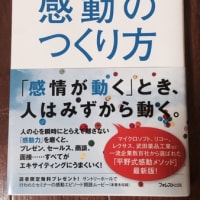
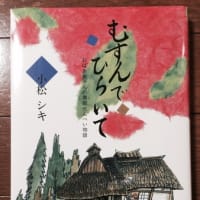
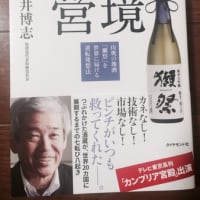
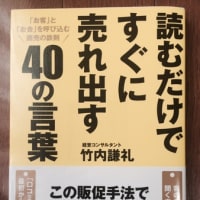
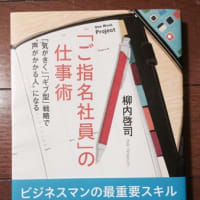




-----転載ここから
首都圏の大規模停電を巡り、国土交通省は15日、送電線に接触したクレーン船を扱っていた「三国屋建設」(茨城県神栖市)の元請けで、千葉県浦安市から浚渫(しゅんせつ)工事を請け負っていたゼネコン大手「大林組」の担当役員を呼んで事情聴取した。
大林組は国交省に対し、接触現場は浚渫場所から約1キロ・メートルも離れた場所で、「なぜ、そんな場所でクレーンを操作したか、わからない」と説明。施工現場に移動する前の事故で、元請けとしての責任の範囲外だと主張した。
また、北側国交相は15日の閣議後会見で、国交省として、〈1〉建設業法〈2〉船舶航行〈3〉河川管理のそれぞれの観点から、問題がなかったか、行政処分を視野に再発防止に向けた調査を進める方針を明らかにした。
(読売新聞) - 8月15日13時14分更新
-----転載ここまで
委託先が適切な作業をしていないという構図は、ふじみ野市から請け負っていた太陽管財に問題があったというプールでの事故と似ている。
事業を下請けに出すのはいいが、任せたら責任の所在まで放棄する、いわば丸投げでは事件はなくならないということだろう。
任せるにも基準が必要だし、任せた後も適切な管理(評価や見直し)が必要であるという、ISO9001的には「アウトソーシング」が問われているのだろう。
-----転載ここから
旧江戸川の浚渫(しゅんせつ)工事現場に向かうクレーン船が送電線に接触し、大規模停電が発生したことを受け、同工事を発注した千葉県浦安市は15日、元請けのゼネコン大手「大林組」との工事契約を解除した。
また、同社を6か月間の指名停止とした。
同市は、停電が社会的に大きな影響を及ぼしことを考慮し、契約解除などを決めた。
(読売新聞) - 8月15日22時14分更新
-----転載ここまで
7年前にも那珂川で同様の事故を起こしていた三国屋建設も是正処置や予防処置としての再発防止が不十分だったと思うし、そんな三国屋建設を管理できていなかった大林組が問われるのも、やむをえないと思う。
大林組にしてみれば、自分たちのしたことじゃないのに・・・という思いが強いかと思う。
しかし「任せる・依頼する」ということは、自分たちの仲間として意識すべきという教訓をもたらすのではないか。工事依頼側からすれば、大林組に発注すると、信頼のおけない下請けに仕事を任せて、事故につながるおそれもある、というイメージを持つのだから。
そして契約した以上、最終責任は最初の依頼主にあるというのがISO9000の基本概念ではなかろうか。最終製品はやはり依頼主の責任であることを踏まえると。
わが国ではほとんどの企業にこのような基本的な事柄が全く理解されていないように思われる。本当に内部監査担当者は何をしているのかと言いたい。
事件や事故は、似た構図が背景にあるのが興味深く感じております。ということは、そこを押さえておけば防げたのではないか、と思うのです。
新たな出来事が起こるたびに、「またか!」と思うし、それは自分の周囲にもあてはまるのでしょう。
内部監査が機能していれば・・・、というのは同感です。事故が防げた、当たり前のことができた、マイナスが発生しなかった、これは隠れたISO9001の機能(メリット)だと思います。
ところで、今回の場合は、浦安市と大林組、どちらに問題があったとお考えでしょうか。
難しいのは、依頼者は提出された資料からしか事業主を評価できないところもあるでしょうね。契約前に立ち入り検査することは不可能でしょうし、契約後であってもなんらかの不備が生じない限り無理だし、権限もどの程度地方自治体にあるのでしょうか。インターネットが発達した現在、各自治体が共同して正直に情報交換できるようになれば、可能になるかなとも期待してますが。
ただ言えることは、浦安市が直ちに大林組との契約を解除し、短期間とはいえ指名停止を行ったことは今後の同様な事故の再発防止(元請けの責任)に繋がるのではと期待しています(各依頼者がこのような措置を取ることで)。