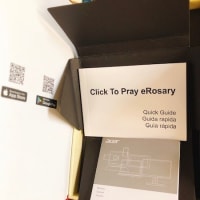“サードウェーブ”の次、“フォースウェーブ”とも言われる『コンビニコーヒー』。
あんなに安くて、でもなぜ高級ホテルの珈琲よりも美味しく感じるのか?
その謎(?)が、非常にわかりやすく、そしてまるで小説のように面白く、あっという間に読んでしまうと思います。
そしてまた、なぜコンビニにより味が違ったり、美味しく感じたり苦く感じたりするのか。
もちろん、使っている豆自体が違うというのも当然ありますが、それ以外にも実は、機械式とはいえ淹れ方自体が違っていたりするのです。
ドリップ方式か、エスプレッソ方式か。
普段、皆さん自身も疑問に思っているであろうことが、この1冊ですべてわかってしまいます。
コンビニコーヒー好きの人は特に是非、読んでほしい1冊です。
あまりコンビニコーヒーを飲まない人は、読むとコンビニ巡りして逆に飲みたくなってしまうかも?

著者の“コーヒーハンター”川島良彰さんは、ご存知の方も多いと思いますが『Mi Cafeto』のオーナーです。
ミカフェートのコーヒー豆との出会いはもう6年前、伊勢丹新宿店でシャンパンボトル入りで売っていた『Grand Cru Café(グランクリュカフェ)』でした。
今ではどのコーヒー豆屋さんより一番長いお付き合いかもしれません(それよりも前からコーヒー豆を買っているお店はありましたが、私の舌が肥えるたびに(笑)、変わっていきましたw)。
私が勝手に心の中で『コーヒーの師匠』と思っているお一人です(ゴメンナサイw)。
川島さんの場合、ただ単に《美味しいコーヒー豆を自分で現地で探してきて日本で紹介》したり《その豆を最高の状態で日本で焙煎》とか、そういうことはとっくのとっくに飛び越えています(ほとんどのコーヒー屋さんはその両方を自分自身で行うこと自体難しいことだったりしますが)。
《コーヒー原産国でもない日本人がコーヒー原産国のコーヒー農家の人たちにコーヒーの種からの育て方や弱った苗をやり直したり植え方や畑の作り方を教えたり》、《日本に輸入されるほとんどのコーヒー豆は温度・湿度管理していないドライコンテナで40日も50日もかけて船便で配送されるところを、川島さんのところの豆はちゃんと空輸もしくはリーファーコンテナ(低温管理できるコンテナ。空輸できない国などや豆の品質により選択)で日本まで配送》など、飛び抜けてコーヒー豆の品質やその生産、流通などすべての面において知識だけでなく実際の長い経験として知っており、そして今現在もそれらのために海外を飛び回っています。日本のコーヒー屋さんと一口に言っても豆の扱い方は千差万別だ、ということですね。
ドライコンテナで輸入されたコーヒー豆を、それから日本で一生懸命お金をかけて低温管理しても意味がない、というのもうなずけます。


はい、恒例の《目次だけ》(笑)
コーヒー好きの人にとっては本当に面白いので、ぜひ読んでみてください。
たかがコーヒー、されどコーヒー!
コーヒのことをいろいろな角度から見るだけで、たくさんの面がのぞけて楽しいです☆