先日は日本に男色を持ち込んだのは空海だったかも、という所まで。
しかししかししかーし!
史料上の初出は『日本書紀』、そして確実な史料初出は『往生要集』だそうな。
日本書紀っつーと話がえらーく遡ってしまいますな(笑)
日本書紀(720年)~往生要集(985年)の成立までは250~60年。
そして往生要集~台記(1155年)の成立までが160~70年。
因みに空海が帰国した年が806年。
日本書紀の記述によると、男色→罪、とまでは行かなくても、肯定的に見られるものではなかったようです。
まあ、日本は元々農村社会ですからな。
子を生さない同性愛(の流行)は共同体の存続を危ぶませる、という点から頷くことができます。
じゃあ、そんな世界でどーして男色が広まったんでしょーか…?
服藤早苗氏によると、9世紀10世紀の頃に男女の婚姻関係や性関係が大きく変容した所に原因があるようです。
男女の性愛が不平等になり、逆に対等な人間同士の性愛が模索され、そのひとつが男色だったのではないか、と。
な、なるほど。
戦国時代では織田信長や武田信玄、伊達政宗が小姓を寵愛した事が有名ですが、この頃には
女性との交渉→子供を残すための方策
同性との交渉→真実の愛
という概念があったそうです。
全てが全てこうではなかったと思いますが、こう言われてみれば何となく納得がいきます。
(平安と戦国では時代が大分下ってしまいますが、基本的な部分というのは大きくは変わらないのではと思います)
しかし…
信長と森蘭丸、信玄と春日源助(高坂弾正)、政宗と只野作十郎。
主君⇔家臣 の間で"対等"(もしくは対等に近い)の関係が保たれるんだろうかという疑問が残ります。
信長に関しては寡聞にして知りませんが、後者2人は相手に宛てたラブレター?が残っています。
どっちもかなり有名ですな(笑)
※信玄→源助
某には言い寄ってましたが、腹痛だとか言われていつも振られてました。
まして寝た事なんてありません。
でももう浮気しません。ごめんなさい。
※政宗→作十郎
浮気してたなんて疑ってごめんなさい。酔った勢いでつい口が滑りました。
貴方が体を傷付ける時に傍にいたら、脇差にすがり付いてでも私は止めたでしょう。
(*作十郎は潔白を証明するために自傷した)
大雑把過ぎですか。そうですか。あんまり気にしちゃいけません(笑)
上記2つとも手紙が現存していますが、…特徴、といっていいのかどうか。
どちらも丁寧にも敬語で書かれているんですね。
内容も内容ですが、手紙を見る限り上下関係が成立していない。
対等、といえば対等だったんだろうか。
さてさて…?
しかししかししかーし!
史料上の初出は『日本書紀』、そして確実な史料初出は『往生要集』だそうな。
日本書紀っつーと話がえらーく遡ってしまいますな(笑)
日本書紀(720年)~往生要集(985年)の成立までは250~60年。
そして往生要集~台記(1155年)の成立までが160~70年。
因みに空海が帰国した年が806年。
日本書紀の記述によると、男色→罪、とまでは行かなくても、肯定的に見られるものではなかったようです。
まあ、日本は元々農村社会ですからな。
子を生さない同性愛(の流行)は共同体の存続を危ぶませる、という点から頷くことができます。
じゃあ、そんな世界でどーして男色が広まったんでしょーか…?
服藤早苗氏によると、9世紀10世紀の頃に男女の婚姻関係や性関係が大きく変容した所に原因があるようです。
男女の性愛が不平等になり、逆に対等な人間同士の性愛が模索され、そのひとつが男色だったのではないか、と。
な、なるほど。
戦国時代では織田信長や武田信玄、伊達政宗が小姓を寵愛した事が有名ですが、この頃には
女性との交渉→子供を残すための方策
同性との交渉→真実の愛
という概念があったそうです。
全てが全てこうではなかったと思いますが、こう言われてみれば何となく納得がいきます。
(平安と戦国では時代が大分下ってしまいますが、基本的な部分というのは大きくは変わらないのではと思います)
しかし…
信長と森蘭丸、信玄と春日源助(高坂弾正)、政宗と只野作十郎。
主君⇔家臣 の間で"対等"(もしくは対等に近い)の関係が保たれるんだろうかという疑問が残ります。
信長に関しては寡聞にして知りませんが、後者2人は相手に宛てたラブレター?が残っています。
どっちもかなり有名ですな(笑)
※信玄→源助
某には言い寄ってましたが、腹痛だとか言われていつも振られてました。
まして寝た事なんてありません。
でももう浮気しません。ごめんなさい。
※政宗→作十郎
浮気してたなんて疑ってごめんなさい。酔った勢いでつい口が滑りました。
貴方が体を傷付ける時に傍にいたら、脇差にすがり付いてでも私は止めたでしょう。
(*作十郎は潔白を証明するために自傷した)
大雑把過ぎですか。そうですか。あんまり気にしちゃいけません(笑)
上記2つとも手紙が現存していますが、…特徴、といっていいのかどうか。
どちらも丁寧にも敬語で書かれているんですね。
内容も内容ですが、手紙を見る限り上下関係が成立していない。
対等、といえば対等だったんだろうか。
さてさて…?












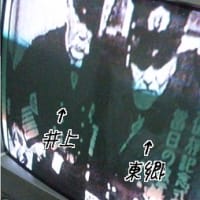

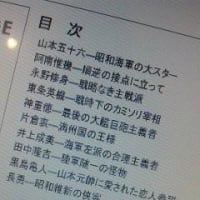
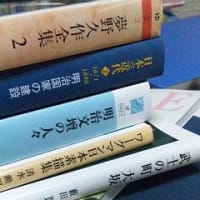








深くて長いハナシを一足飛びにかいつまんでわかりやすく聞かせてもらった感じです(^^)
信玄、政宗おぬしもか~ び、びっくりです ヒジハラさんの現代語訳読ませていただくと、彼等のイメージと違うのでおもしろすぎる~
でもどうして大正からアブノーマルになったんでしょう?基督教の影響でしょうか?
よかった~
話があっちこっちとんで、申し訳ないです
実は信玄も政宗も結構有名です。
上杉謙信もそうですし、前田利家もそうですね。
恐らく一般受けしないからTVでもあまり取り上げないし、学術書でもかする程度なんでしょうか。
確かにキリスト教の影響は大きいと思いますが、西洋とよりよく付き合うため、という理由もあったんじゃないかと…
結構奥深いですねえ
ちょっと思ったんですが、もしかすると男色って、その昔、男性の仕事が「集団で狩猟」だった頃、集団内の意識や結束を固めて狩りの成功率を上げるために生じたものかもしれませんね。お互い心が絆で結ばれていれば、それだけ意思伝達の効率が高くなるから、みたいな。
……と、いきなり考古学的見地まで遡ってみました(爆)。
こんばんわ!
確かに兵学校の話なんか読んでいても、結構微妙だ、と思うようなのもありますよね~(笑)
起源、となるとどうなるんでしょうね??
どうもよく分かりませんが…ただ社会の仕組みが結構進んできた段階で出てきたのは確かなようです。
教育、社会的な経験諸々という所で男女間の格差?が相当開いてしまい、"女性→子供を生むための道具"といった認識が生まれてきた段階で出てきた状況らしい。
これは日本もヨーロッパも同じみたいですよ。
人間の社会って基本的な所ではそうそう変わらないのかも知れませんね。