「こんにちは」というのは昼間の挨拶の言葉だ。手紙にも使う。それをたまたま「こんにち歯」と書いたらどうなるか。こんにちの歯、こんにちの前歯、乱杭歯などを意味し、少しでも「こんにちわたしは歯をあなたに突き立てています」、「あなたに防備しています」というようなサインになるだろうか。というようなくだらないことをある日考えた私は、こんなつまらないことを人に言ってはいけない、馬鹿だと思われてしまう、いやそれならまだいいが、このひとはなぜこんなことを言いたいのかとしげしげと観察されたら大変だと思い、もう1年ぐらい黙っている。
一体そのことと愛憎詩となんの関係があるのかと思われるだろうが、「愛憎詩」すなわち愛するほど憎い、憎いほど愛する詩というと何も思い浮かばない私は困り果てて、荒川洋治の『一時間の犬』(1991年・思潮社)を書棚から手に取った。2006年の春に思潮社の詩集の専門店、池袋の「ぱろうる」が閉店するにあたり購入し、なぜしばらく経って読んだのか思い出せないが、2007年3月13日火曜日に読了した詩集である。 読了日がわかるのは、私は読了した日付を巻末に必ず書き込み、感動した詩行に線を引き、場合によっては感動した理由を本の中にも書きつけておく癖があるからだ。それにもかかわらずこの『一時間の犬』には読了日が記されているだけで、線が引かれていない。2009年の荒川洋治詩集『実視連星』(思潮社)に非常に感銘を受け特にその手法に衝撃を受けた記憶があるので、なぜだろうと気になり、感動する詩行に線を引くべく最初から『一時間の犬』を精読し直した。ところがやはり線を引くことができない。それは感動しないということではなく、ここに線を引こうとすると不十分だという気がし、では次の詩行のここにと思うとやはりその行に不足を感じ、次行へ次行へと読まされてゆくうちに、あっという間に読み終わってしまう詩集なのである。別の言い方をすれば、どの詩もこういうことは普通詩のテーマに選ばないのではないかとか、この感じ方は感じても言わないものなのではないかと思うところがあり、私が日常社会の不文律に縛られすぎるのか、感動する詩行を定めかねる詩集と言えるかもしれない。けれどもぐいぐいと読まされてしまうのだからどの詩もインパクトは強いわけで、与える感動の種類が、日頃私が感銘を受ける詩と違うということではないかと思う。
現代詩とは何かということと関わる命題がこの荒川洋治詩集『一時間の犬』には潜んでいるような気もするし、そのようなこの詩集を愛憎詩と仮に名付けさせていただくことにする。「こんにち歯」と書いてみたい衝動が起こるたびにその気持ち抑えこんでいる私は、笑いがこみ上げてくるほどではなく、おかしくなりかけることがあるのだが、『一時間の犬』と向き合うときにも同様で、ユーモアの手前のおかしさの片鱗がどの詩にもある。ユーモアにしてくれればいいものを、ユーモアになりきらないところでよくも筆を止めてくれたなという感触が憎詩の部分と言えようか。1篇ご紹介しておきたい。
鯉 荒川 洋治
ゆうべ女の肩を借りて吐いた毒も
ゆうべ男の歯を借りて割れたリンゴも
いまは口のあたり ひざの周囲で
カラカラかわいて
雨風に打ち込まれて
風景の一助となりすましても 人の
駆けつけるところはあるようだ
あんたの馬鹿! 夜ごとの馬鹿 捨てぜりふと
大地の線だけふっくらとして
人を潤わせた日の どの家屋もいまや
取材を待ちうけるさだめだ
ある花ない花かきあつめ
「どうぞ」と 近所のゲタまで飛ばして
土足の通路をととのえ 五万 五〇万の声を
さし招くと一旦 門をとざす
それから緋鯉を放つのだった
すべてを吐く
最も好きな詩行を強いて抜き出せば、「ある花ない花かきあつめ/「どうぞ」と 近所のゲタまで飛ばして」部分だろうか。つかこうへい演出の舞台を思い出させる訳のわからないリズムと勢いである。愛詩の理由としておこう。しかし最後のほうにゆくと、なんのこっちゃという終わり方に導かれる。おまえごとき読者にわかってたまるかというようなこのおつな構えが荒川洋治氏の本領でもある。
一体そのことと愛憎詩となんの関係があるのかと思われるだろうが、「愛憎詩」すなわち愛するほど憎い、憎いほど愛する詩というと何も思い浮かばない私は困り果てて、荒川洋治の『一時間の犬』(1991年・思潮社)を書棚から手に取った。2006年の春に思潮社の詩集の専門店、池袋の「ぱろうる」が閉店するにあたり購入し、なぜしばらく経って読んだのか思い出せないが、2007年3月13日火曜日に読了した詩集である。 読了日がわかるのは、私は読了した日付を巻末に必ず書き込み、感動した詩行に線を引き、場合によっては感動した理由を本の中にも書きつけておく癖があるからだ。それにもかかわらずこの『一時間の犬』には読了日が記されているだけで、線が引かれていない。2009年の荒川洋治詩集『実視連星』(思潮社)に非常に感銘を受け特にその手法に衝撃を受けた記憶があるので、なぜだろうと気になり、感動する詩行に線を引くべく最初から『一時間の犬』を精読し直した。ところがやはり線を引くことができない。それは感動しないということではなく、ここに線を引こうとすると不十分だという気がし、では次の詩行のここにと思うとやはりその行に不足を感じ、次行へ次行へと読まされてゆくうちに、あっという間に読み終わってしまう詩集なのである。別の言い方をすれば、どの詩もこういうことは普通詩のテーマに選ばないのではないかとか、この感じ方は感じても言わないものなのではないかと思うところがあり、私が日常社会の不文律に縛られすぎるのか、感動する詩行を定めかねる詩集と言えるかもしれない。けれどもぐいぐいと読まされてしまうのだからどの詩もインパクトは強いわけで、与える感動の種類が、日頃私が感銘を受ける詩と違うということではないかと思う。
現代詩とは何かということと関わる命題がこの荒川洋治詩集『一時間の犬』には潜んでいるような気もするし、そのようなこの詩集を愛憎詩と仮に名付けさせていただくことにする。「こんにち歯」と書いてみたい衝動が起こるたびにその気持ち抑えこんでいる私は、笑いがこみ上げてくるほどではなく、おかしくなりかけることがあるのだが、『一時間の犬』と向き合うときにも同様で、ユーモアの手前のおかしさの片鱗がどの詩にもある。ユーモアにしてくれればいいものを、ユーモアになりきらないところでよくも筆を止めてくれたなという感触が憎詩の部分と言えようか。1篇ご紹介しておきたい。
鯉 荒川 洋治
ゆうべ女の肩を借りて吐いた毒も
ゆうべ男の歯を借りて割れたリンゴも
いまは口のあたり ひざの周囲で
カラカラかわいて
雨風に打ち込まれて
風景の一助となりすましても 人の
駆けつけるところはあるようだ
あんたの馬鹿! 夜ごとの馬鹿 捨てぜりふと
大地の線だけふっくらとして
人を潤わせた日の どの家屋もいまや
取材を待ちうけるさだめだ
ある花ない花かきあつめ
「どうぞ」と 近所のゲタまで飛ばして
土足の通路をととのえ 五万 五〇万の声を
さし招くと一旦 門をとざす
それから緋鯉を放つのだった
すべてを吐く
最も好きな詩行を強いて抜き出せば、「ある花ない花かきあつめ/「どうぞ」と 近所のゲタまで飛ばして」部分だろうか。つかこうへい演出の舞台を思い出させる訳のわからないリズムと勢いである。愛詩の理由としておこう。しかし最後のほうにゆくと、なんのこっちゃという終わり方に導かれる。おまえごとき読者にわかってたまるかというようなこのおつな構えが荒川洋治氏の本領でもある。










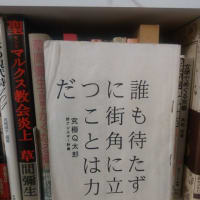
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます