その1はこちら。
前記事では、渡邊教授の発言を紹介するところを優先してしまったため、字数がギリギリになってしまった。そこで、渡邊教授の重要な発言に関して、その2として、さらにつっこんで考えてみる。
おそらく、渡邊教授の発言としても最も重要なのはこれであろう。
https://twitter.com/#!/ynabe39/status/144350825278480384
大学が「言論の府」だというのは「大学の中ではどんなおかしなことを言ってもいい場所」だということです。教員や学生が「おかしなことを言ったこと」によって大学がその教員や学生を追放したり処分したりしてはいけない。(続く)
12月7日
https://twitter.com/#!/ynabe39/status/144351354033410049
(続き)もちろん,大学の教員や学生が言った「おかしなこと」で大学の外にいる人に被害や苦痛を与えた場合には,その被害者から告発されれば責任を負わなければなりません。しかしその責任や被害の大きさについて判定し,罰を与える能力は大学にはない。
12月7日
私の主張の最重要部分は、「大学で教員になっている者は、大学でオーソライズされている分野でのみ、『言論の自由』が最大限に尊重される」というものである。
「『言論の自由』が最大限に尊重されること」というのは、
・「その教員の言論が、犯罪として認定されるまでは、その職位(教授、准教授など)と学位(博士、修士など)が脅かされないこと」
と定義する。この中には、渡邊教授が抗議している、
・「大学によるあらゆる処分(訓告・戒告・罰金も含む)」も、「職位や学位が脅かされること」に入る。
かなり注意深く定義をしたので、この定義が不当だという批判はおそらくないだろう。
争点になるのは、
「大学でオーソライズされている分野でのみ」
に関してだと思う。
「オーソライズ」とは、英語のauthorizeのことで、「~を正式に認める」「~に権限を与える」という意味の他動詞である。
どのくらいの抽象度で書けばいいのか、さっきからかなり迷っているのだが(苦笑)、もう今回の原発事故の話にしてしまおう。要するに、
・目に見えない「放射線」というものの危険度に関して、「放射線の性質や危険度」について知らない、知ろうとしない人間が、
「大学教授」という肩書きだけは最大限に利用して、さも自分の発言に真実味があるかのように語ることの是非である。
ああ、いい例を思いついた。例えば「政治学」の「教授」が、「放射線の危険度」について語るとき、信用度はどのくらいあるのか?ということだ。専門が、「放射線に関する学問」でないのだから、その「教授」がどのくらい「放射線」について「知っているか、知ろうとしているか」による、というのが、最も誠実な答えであろう。私は、専門が放射線に関するものでないからと言って、ただちにその人の放射線に関する発言が信用ならない、と言っているわけでもない。
では、専門が「経済学」ならどうだろうか?「放射線」という分野から見ると、「政治学」の方が何となく近く見えてしまうから不思議である。しかし、「数字を扱う」という観点から見れば、「政治学」よりも、「経済学」が「専門」の学者の方が、より冷静に放射線については語れるだろうという期待を、少なくとも私は持つ。
ではさらに、専門が「数学」ならどうだろうか?これなら、「数字」だけでなく、「数式」を扱うプロフェッショナルであると推測できる。したがって、例えば放射線について学ぶときに必要な「距離の2乗に反比例」などの概念も、我々素人にもわかりやすく説明してくれるだろうなどという期待も持てるだろうと、我々素人は期待するだろう。ただ、「危険度」についてはどれくらい信用できるかわからない。どのくらい、その数学者が、放射線の危険性を理解している、または理解しようとしているかによるだろう。
そこで、専門が「火山学」ならどうだろうか?ということである。wikipediaによると、「この記事は不十分だ」という保留事項がありながらも、
・火山学(かざんがく、英: volcanology)は、火山、溶岩、マグマなどの地質学的現象を研究する学問。
とある。一応、理系に所属する学問であろうが、火山や溶岩などの分類には、いわゆる「文系」的な、広範な知識や分類に関する技術を持っているものと期待できるだろう。降下している放射性物質を、例えば「火山灰」と同様の拡散、降下、蓄積をするものとして捉えるのであれば、その比喩の範疇内では、定量的に正しい推測ができると期待もできる。
ただ、放射性物質が、火山灰と同様な物理的振る舞いをするのか(放射性物質は崩壊するが、火山灰は崩壊しない)という点にはいつも気をつけていなければならないし、何より、「放射線」という、実際に空間を飛んでいる目に見えない「線」に関しては、火山学に「それに該当するもの(英語では"counterpart"と言う)」が一見見当たらないので、単に
・理系の「学者」、あるいは「教授」だから信頼できる
という結論にはならない。そこは「数学」が専門の「教授」と同様に、ある程度の疑わしさが存在すると推測できる。
その一方で、ある学者を学者としてオーソライズする際に、どこまで「学位」を取得しているか、ということも、その人物の学者としての信頼度に関わってくる。一般的に、理系の博士号は、博士課程を修了し、博士論文を提出し、
・一人で研究が行える
という基準を満たせば、文系の博士号よりは取りやすいと言われていた。特に、2000年代に入るまでは、「理系の博士号は博士課程修了時に取れて当然、文系の博士号は名誉の称号みたいなもので、博士課程修了時には取れないもの」とまで言われていた。
ただ、残念なことに、wikipediaで「早川由紀夫」を調べてみても、
・1985年3月 東京大学大学院理学系研究科地質学修了
とあるだけで、博士号、あるいは修士号を取れたのかについての情報が得られない。群馬大学の早川由紀夫研究室のこのページやこのページだけでなく、「早川由紀夫 学位論文」でぐぐっても、どの学位まで取れたのかがわからない。
ここまでで、一般的な「理系」の「研究者」であれば、「専門の火山学でさえ、どの学位まで取れたかわからないのに、何を信用せよと言うのか」という反応をするのが一般的だと思うが(私が大学在学中の理系の同僚や、ぶぶさんなどのご発言から推測)、私は理系ではないので、この点はあえて無視することとする。なぜなら、私自身が自信を持って、理系の学者の「オーソライズされ度合い」を判断することができないからだ。
ここまでで、彼の専門が「火山学」であることは、必ずしも彼の放射線や放射性物質に関する発言が正しいことを保証しないということを、できるだけ理詰めで説明してきた。
次に、彼が放射線あるいは放射性物質に関して、どのくらい正しい知識を持っているかが問題になるのだが、これは当ブログで先週、この記事に引用した以下のツイートを示すことが最重要であろう。
URL:https://twitter.com/#!/HayakawaYukio/status/144184464132673536
魚拓:http://twittaku.info/view.php?id=144184464132673536

文章:
「セシウムまみれの干し草を牛に与えて毒牛をつくる行為も、セシウムまみれの水田で稲を育てて毒米つくる行為も、サリンつくったオウム信者がしたことと同じだ。福島県の農家はいま日本社会に向けて銃弾を打ってる。」7月11日 http://t.co/QUyTV0kC
(ここまで)
なおかつ、あの岩上安身氏が収録したUstreamの映像取材で、彼自身が、
・「ボクは医学-生き物に関しては何もわからん」
と明言している。この映像の、48分30秒あたりのところである。
http://www.ustream.tv/recorded/19024757
この二つの「事実」だけで、早川教授は放射線あるいは放射性物質に関して、素人同然であると結論づけるしかないのだが、ここもあえてもう少し細かく分析してみる。ツイッターでの発言だ。
>セシウムまみれの干し草を牛に与えて毒牛をつくる行為
どのくらいのセシウム含有量をもって、「セシウムまみれ」としているのか、どのくらいの毒性をもって「毒牛」としているのか、この発言からは全くわからないし、それを補足するようなツイートも見当たらない。
>セシウムまみれの水田で稲を育てて毒米つくる行為
これも上と同様である。「定量的な観点」が全くないのだ。
>サリンつくったオウム信者がしたことと同じだ。
サリンは「体重60 kgのヒトが1680 mg(約1.5 mL)のサリンを経皮吸収すると、その半数が死亡する(wikipediaより)」とあるように、微量でも猛烈な毒性を示すことが定量的に示されているのに対し、このツイートにはそういう観点からの記述が一切見られない。
「早川マップがあるじゃないか!」
と反論する方もいるだろうが、早川マップは、飛んでいる線量についてのものばかりで、彼の専門が生きるであろう、放射性物質の降下、積算量についてはほとんど見当たらないし、改訂もなされていない。「放射能汚染地図 5訂版」を見ても、空間線量だけなのだ。これだけでは、彼の火山学の知見はほとんど生かせないとしか推測のしようがない。なぜなら、放射線は、火山灰とは違い、蓄積するものではないからである。もともとの「しくみ」が異なるものに対して、
「福島第一原発から放出された放射能の分布は、火山灰に関する私の専門知識を応用してうまく理解することができます。」(彼のブログの「プロフィール」より)
と書かれていても、何をどう応用すれば、どううまく理解できるかの説明が、少なくとも私にはどこにも見つけることができない。放射性物質の積算量に関するマップがないというのがその象徴である。
彼のツイートの極めつけがこれである。
>福島県の農家はいま日本社会に向けて銃弾を打ってる。
「銃弾を打ってる」という言葉づかいは、「殺そうとしている」という意味を比喩的に述べていると解釈していいだろう。上記に指摘したように、
1 定量的な観点からの記述や補足説明が全くないままに、
2 火山学が生かせるのかどうかわからない「空間線量」のマップだけを何度も改訂し、
3 1と2の成果を合わせ、「福島県の農家が他の日本人を殺そうとしている」という主旨のツイートを行っている。
という現実が、大学で守るべき「言論の自由」の範囲に入るのか、という問題である。帯広畜産大学の渡邊教授には申しわけないが、「教授」という肩書きがついている分だけ、素人がこういう発言を行っている以上に、根拠がないのに信用されやすくなるという意味で、公共の福祉を大きく害する可能性がある発言であると、私基準では言わざるを得ない。
特に、福島県産のコメに、規制値を下回っているものが十分な量だけ存在しているという「事実」と明確に矛盾している。
「事実と矛盾していることが明らかならば、彼の発言を問題視する必要はない」と反論する人もいるだろうが、「事実と矛盾していること」が「明らか」だと思っていない人が早川教授の発言を支持しており、その支持している人々が無視できないほどの数は存在している(例えば彼のフォロワーの数)ということが問題であるのだから、この事実の明確さを共有できていない点こそが問題なのだ。したがって、上のような反論は、
「お前らはそう思っていればいいさ!俺たちは別な風に思っているから!」
という態度表明と同じであって、何ら「反論」になっていない。そして、その問題点をこじれさせているのが、早川教授の「根拠のない」発言なのである。
早川教授なりの根拠があり、その根拠が、彼の専門である火山学に照らしても、ある程度の確率で「正しい」と判断されうるものであれば、その結果がどれだけ私たち素人にとって衝撃的なもの、危険なもの、腹が立つものであっても、渡邊教授のおっしゃるように、「学問の自由」「言論の自由」という概念で彼の発言は守るべきだと私も考えるが、
1 「ボクは医学、生き物に関して何もわからん」と公言する「教授」が、
2 専門外のことに関し、根拠もなく「福島の牛とコメは他の日本人を殺そうとするものだ」という主旨の発言を不特定多数が見られる状態になっている
という状況は、どう見ても「公共の福祉の侵害」という法理が優先するものであると結論づけざるを得ない。
したがって、大学側による処分は、学問の自由、あるいは言論の自由という法理で、棄却できないものだという結論になる。
少なくとも、無制限に学問の自由、言論の自由という法理で、早川教授の発言は守ることができない、ということを、できるだけ論理的に立論してみた。問題点や穴があったらご指摘いただきたい。










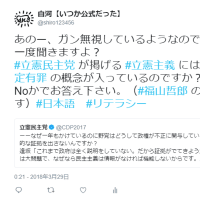
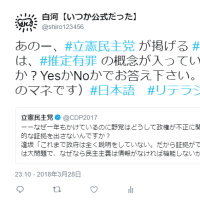

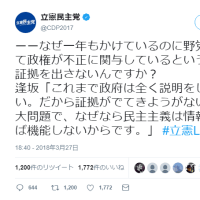
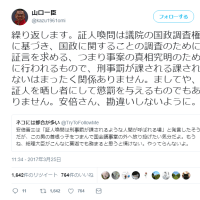
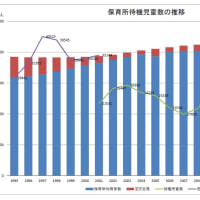
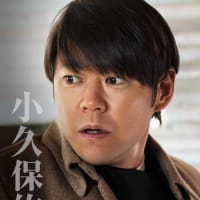



早川氏は、あの、初期の、衝撃的な汚染地図、あれがすべてで、読売にも載ったりして、盤石と思われていたと思います。今回、そんなひどいことを言うはずが・・と、逆に驚いた次第です。
ログインしましたので、今後もよろしくお願いいたします。
gooのID取るのもめんどくさいというのに、よくぞお取り下さいました!感謝感激でございます。
レモンさんのサイトも拝見させていただきました。日々、ホンネで記事を書いていて良かったとしみじみ思いました。レモンさんにもお礼を言わねばですね!
早川教授には日本語が通じないと思ったので、彼を擁護した渡邊教授にツイッターで質問しましたが、その結果としても、やはり大学がオーソライズしている「専門」が何か、ということが重要だという結論は変わりませんでした。私の中では。
彼の専門である「火山学」の知見が、「放射性物質」ならぬ、「放射線(飛んでる線)」に生かせる論理的な筋道が浮かびません。ハヤカワマップも、5訂版を出しておきながら、熊谷市あたりの「やや高いスポット」の存在を隠していたりする点を見ると、彼の行動原理は「国やマスコミがやらないから私がやる」ではないようですね。積極的に、彼自身が達成したい政治的な目的があるようです。それは彼自身の以前の論文からも窺えました。
仕事が忙しくて昨日は記事が書けませんでしたが、また彼についても書きたいと思います。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
早川マップの放射線量は地上1m程度での測定値です。この値は地表に積もった放射性物質の量に比例(おおざっぱにですけど)します。
原発が爆発したときに大気中に飛散した放射性物質粒子の挙動(どのように空中を飛び、地上に落下するかという意味で)と、火山の噴火時に大気中に飛散した火山灰の挙動は似ているので、「福島第一原発から放出された放射能の分布は、火山灰に関する私の専門知識を応用してうまく理解することができます。」という点においては早川氏の言っていることは間違ってはいないと思いますよ。彼が、火山灰の挙動のシミュレーションとかを専門にしているなら、ですけどね。
まあ、この記事の結論に影響を及ぼすものではないんですけど、気になったので。
>放射性物質粒子の挙動(どのように空中を飛び、地上に落下するかという意味で)と、火山の噴火時に大気中に飛散した火山灰の挙動は似ているので、「福島第一原発から放出された放射能の分布は、火山灰に関する私の専門知識を応用してうまく理解することができます。」という点においては早川氏の言っていることは間違ってはいないと思いますよ。
私もそう思っていたのですが、だとすると、なぜ「線量」のマップばかりをひたすら改訂し続け、「降下量」あるいは「積算降下量」のマップを作っていないのかが不自然でなりません。今では、どちらも文科省のHPから、文科省が作成したものが見られるというのに。
この不自然さから、
>「福島第一原発から放出された放射能の分布は、火山灰に関する私の専門知識を応用してうまく理解することができます。」
という発言に対し、「どのように?」とツッコミを入れざるを得なくなっております。
どう考えられますか?