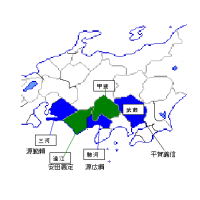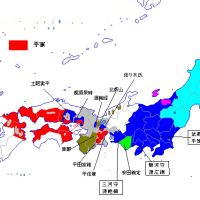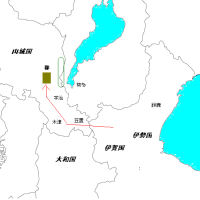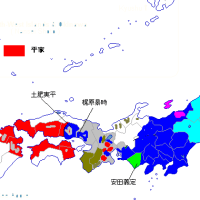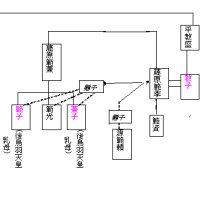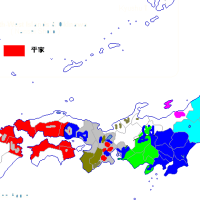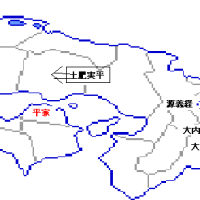一条能保室
彼女は女性です。
当時の女性の多くの常として名前が知られていません。(当時の女性の名前についての考察はこちら)
「平治物語」では坊門姫と呼ばれています。
この激動の時代に源義朝の娘として生まれ
それゆえに時代の荒波を直に浴びながらも多くの子供を産み育てた女性です。
一条能保も彼女の夫であるがゆえに激動期の歴史に少なからず関わることになります。
そして、彼女の子孫が後に大きく歴史に関わることになるのです。
彼女もそれなりに激動の人生を送ったものと思われます。
女性であるがゆえに戦場に立つこともなく
女性も政治的に発言することが可能だった時代にも関わらず
その方面には何の痕跡も残さなかった彼女ですが
史料のあちらこちらに彼女が確かに存在した証を遺しています。
頼朝の姉説の場合 久安元年(1145年)生 ※
頼朝の妹説の場合 久寿2年(1155年)生
父 源義朝、母 熱田大宮司藤原季範の娘(「尊卑分脈」他)
夫 一条能保 (「尊卑分脈」「吾妻鏡」他)
同母兄弟 頼朝、希義
※彼女ついては頼朝の姉説と妹説の二つがあります。
そのそれぞれの根拠
姉説
「吾妻鏡」建久元年(1190年)4月20日条に13日一条能保室が難産の為46歳で死去したとの記事がある。逆算すると1145年生まれで頼朝の2歳姉となる。
妹説
「吾妻鏡」では頼朝の「妹」と記載されている。
古態本「平治物語」で彼女の乳母夫後藤実基が1159年現在6歳の彼女を連れていたとの記載がある。(この計算ならば1154年生まれになりますが)
それぞれに対する反論はこうです。
姉説に対する反論
46歳の難産死は無理があるのではないのか
吾妻鏡46歳の死没は36歳の誤記ではないのか
妹説に対する反論
「妹」というのは当時においては「姉妹」をさす言葉なので年上の女兄弟も含まれる。
(現に北条政子を義時の「妹」と記していた当時の文書もある)
この場合特に改竄の必要もない部分なので
「軍記物」の記載よりは「吾妻鏡」の記載を優先するべき。
さて、私は彼女を頼朝の「姉」としました。
このように考えるのには次のような理由があります。
姉説に反論での46歳(満44-45歳)の難産死は無理という部分がありますが
妹説では逆の「無理」があるのです。
彼女の娘と考えられる九条良経室が
正治2年(1200年)7月13日に34歳で死亡したとの記事が「明月記」にあります。
逆算すると九条良経室は1167年生まれです。
1167年に出産したならば
一条能保室1155年生まれの場合満11-12歳で出産です。
出産するにはその約10か月前に妊娠出産可能な体になっていなければなりません。そうすると「妊娠」した時期はまだ満11歳にもなっていない可能性もあり
個人差もありますが、10-12歳では初潮を迎えている可能性は当時の栄養状況から考えて低いのではないのかと考えられます。
また、体の成熟度を考えてもその年齢で妊娠できてもリスクが非常に高く無事出産にたどりつくかどうか・・・
当時も初出産年齢は数え年15歳を越えてからの方が多いようです。
数46歳の難産死も無理があるかもしれませんが
藤原道長の妻倫子は40過ぎてから出産していますし
当時も後白河法皇の寵を受けた丹後局が40歳くらいで出産しています。
また、現在でもそのくらいの年齢の出産はたまに見かけます。
そのように考えると
妊娠出産の可能性は
満44-45歳(数え46歳)の難産死>満11-12歳(数え13歳)の出産
と思われますので私は一条能保室を「姉」と設定しました。
彼女は女性です。
当時の女性の多くの常として名前が知られていません。(当時の女性の名前についての考察はこちら)
「平治物語」では坊門姫と呼ばれています。
この激動の時代に源義朝の娘として生まれ
それゆえに時代の荒波を直に浴びながらも多くの子供を産み育てた女性です。
一条能保も彼女の夫であるがゆえに激動期の歴史に少なからず関わることになります。
そして、彼女の子孫が後に大きく歴史に関わることになるのです。
彼女もそれなりに激動の人生を送ったものと思われます。
女性であるがゆえに戦場に立つこともなく
女性も政治的に発言することが可能だった時代にも関わらず
その方面には何の痕跡も残さなかった彼女ですが
史料のあちらこちらに彼女が確かに存在した証を遺しています。
頼朝の姉説の場合 久安元年(1145年)生 ※
頼朝の妹説の場合 久寿2年(1155年)生
父 源義朝、母 熱田大宮司藤原季範の娘(「尊卑分脈」他)
夫 一条能保 (「尊卑分脈」「吾妻鏡」他)
同母兄弟 頼朝、希義
※彼女ついては頼朝の姉説と妹説の二つがあります。
そのそれぞれの根拠
姉説
「吾妻鏡」建久元年(1190年)4月20日条に13日一条能保室が難産の為46歳で死去したとの記事がある。逆算すると1145年生まれで頼朝の2歳姉となる。
妹説
「吾妻鏡」では頼朝の「妹」と記載されている。
古態本「平治物語」で彼女の乳母夫後藤実基が1159年現在6歳の彼女を連れていたとの記載がある。(この計算ならば1154年生まれになりますが)
それぞれに対する反論はこうです。
姉説に対する反論
46歳の難産死は無理があるのではないのか
吾妻鏡46歳の死没は36歳の誤記ではないのか
妹説に対する反論
「妹」というのは当時においては「姉妹」をさす言葉なので年上の女兄弟も含まれる。
(現に北条政子を義時の「妹」と記していた当時の文書もある)
この場合特に改竄の必要もない部分なので
「軍記物」の記載よりは「吾妻鏡」の記載を優先するべき。
さて、私は彼女を頼朝の「姉」としました。
このように考えるのには次のような理由があります。
姉説に反論での46歳(満44-45歳)の難産死は無理という部分がありますが
妹説では逆の「無理」があるのです。
彼女の娘と考えられる九条良経室が
正治2年(1200年)7月13日に34歳で死亡したとの記事が「明月記」にあります。
逆算すると九条良経室は1167年生まれです。
1167年に出産したならば
一条能保室1155年生まれの場合満11-12歳で出産です。
出産するにはその約10か月前に妊娠出産可能な体になっていなければなりません。そうすると「妊娠」した時期はまだ満11歳にもなっていない可能性もあり
個人差もありますが、10-12歳では初潮を迎えている可能性は当時の栄養状況から考えて低いのではないのかと考えられます。
また、体の成熟度を考えてもその年齢で妊娠できてもリスクが非常に高く無事出産にたどりつくかどうか・・・
当時も初出産年齢は数え年15歳を越えてからの方が多いようです。
数46歳の難産死も無理があるかもしれませんが
藤原道長の妻倫子は40過ぎてから出産していますし
当時も後白河法皇の寵を受けた丹後局が40歳くらいで出産しています。
また、現在でもそのくらいの年齢の出産はたまに見かけます。
そのように考えると
妊娠出産の可能性は
満44-45歳(数え46歳)の難産死>満11-12歳(数え13歳)の出産
と思われますので私は一条能保室を「姉」と設定しました。