ピュッー
いきなり顔に尿が飛んできた。
藤七の子━━生まれて半年も経っていない新太郎のむつきを外した瞬間のことだった。
新太郎の男の印の先から勢い良く放たれたそれは範頼の顔を直撃した。
「参ったなあ」
尿でぬれた顔を直垂の袖でぬぐいつつ範頼はぼやいた。
「今お召し変えをお持ちします。」
と藤九郎の妻小百合は侍女を走らせた。
「ほほほ、私も以前、そう、かなり以前に同じ目にあったことがございます。」
小百合の傍らに控えていた年老いた尼は穏やかな口調で語り始めた。
「男の赤子をむつきを替えるときは用心が必要でございます。
女子の場合は下に流れるのみですが、男の子の場合は前に飛び出しますゆえ。」
「蒲殿、お召し替えもよろしいのですが、まずは赤子の新しいむつきをあててはくれませぬか」
と小百合の娘━━瑠璃は範頼にはっきりと物申した。
「ああ、済まぬ」
と言って、範頼はあわてて新しいむつきをあてようとするのだが
今度は新太郎が動いてうまくあてることができない。
「蒲殿、やはり私がやります」
結局、此度のむつきの交換も瑠璃の世話になることになってしまった。
その様子を微笑ましげに老尼は眺めている。
「お祖母さまも、このような経験をなされましたの?」
と瑠璃はむつきを替える手を休めずに尋ねた。
「ええ、ありましたとも。
私も、何度鎌倉殿に尿をあびせられたことか・・・」
「あの鎌倉殿に?」
「ええ、そうですよ。この尼は鎌倉殿の乳母になる前まで男の赤子を育てたことが無かったもので。
そなたの母達を育てたのと同じつもりで鎌倉殿のむつきを替えていたら
今の蒲殿のような目に会ってしまったのじゃ」
むつきを替え終えて、新太郎を抱いた瑠璃は不思議な顔で祖母比企尼を見つめる。
「けれど、いくら尿をかけられても、どのようないたずらをされましても
怒る気にはなれませんでしたなあ。
本当にあの頃の鎌倉殿は愛しうて、愛しうて。」
「私は、比企殿のように赤子の頃からはお仕えできませんでしたが、
『八田、八田はおらぬか』と私の後を追ってくる鎌倉殿がまた
可愛くてたまりませなんだ。」
比企尼のとなりには、同じく頼朝の乳母であった小山政光の妻八田局がいた。
「あの頃を思えば」
「ご立派になられましたなあ」
と二人の乳母は感慨にふけっている。
範頼は呆然と二人を見詰めている。
むつきをつけた兄、乳母を追い回す兄。
自分からは想像がつかない。
知っている兄は父の嫡子で、弓の名手で、いつでも冷静沈着な憧れの人だった。
現在兄の元に集っている人々も「鎌倉殿」としての頼朝しか知らぬであろう。
しかし、この女性達は他の人が知らぬ兄を熟知している。
━━ 乳母とは、すごいものだな。
と思う。
前回へ 次回へ

いきなり顔に尿が飛んできた。
藤七の子━━生まれて半年も経っていない新太郎のむつきを外した瞬間のことだった。
新太郎の男の印の先から勢い良く放たれたそれは範頼の顔を直撃した。
「参ったなあ」
尿でぬれた顔を直垂の袖でぬぐいつつ範頼はぼやいた。
「今お召し変えをお持ちします。」
と藤九郎の妻小百合は侍女を走らせた。
「ほほほ、私も以前、そう、かなり以前に同じ目にあったことがございます。」
小百合の傍らに控えていた年老いた尼は穏やかな口調で語り始めた。
「男の赤子をむつきを替えるときは用心が必要でございます。
女子の場合は下に流れるのみですが、男の子の場合は前に飛び出しますゆえ。」
「蒲殿、お召し替えもよろしいのですが、まずは赤子の新しいむつきをあててはくれませぬか」
と小百合の娘━━瑠璃は範頼にはっきりと物申した。
「ああ、済まぬ」
と言って、範頼はあわてて新しいむつきをあてようとするのだが
今度は新太郎が動いてうまくあてることができない。
「蒲殿、やはり私がやります」
結局、此度のむつきの交換も瑠璃の世話になることになってしまった。
その様子を微笑ましげに老尼は眺めている。
「お祖母さまも、このような経験をなされましたの?」
と瑠璃はむつきを替える手を休めずに尋ねた。
「ええ、ありましたとも。
私も、何度鎌倉殿に尿をあびせられたことか・・・」
「あの鎌倉殿に?」
「ええ、そうですよ。この尼は鎌倉殿の乳母になる前まで男の赤子を育てたことが無かったもので。
そなたの母達を育てたのと同じつもりで鎌倉殿のむつきを替えていたら
今の蒲殿のような目に会ってしまったのじゃ」
むつきを替え終えて、新太郎を抱いた瑠璃は不思議な顔で祖母比企尼を見つめる。
「けれど、いくら尿をかけられても、どのようないたずらをされましても
怒る気にはなれませんでしたなあ。
本当にあの頃の鎌倉殿は愛しうて、愛しうて。」
「私は、比企殿のように赤子の頃からはお仕えできませんでしたが、
『八田、八田はおらぬか』と私の後を追ってくる鎌倉殿がまた
可愛くてたまりませなんだ。」
比企尼のとなりには、同じく頼朝の乳母であった小山政光の妻八田局がいた。
「あの頃を思えば」
「ご立派になられましたなあ」
と二人の乳母は感慨にふけっている。
範頼は呆然と二人を見詰めている。
むつきをつけた兄、乳母を追い回す兄。
自分からは想像がつかない。
知っている兄は父の嫡子で、弓の名手で、いつでも冷静沈着な憧れの人だった。
現在兄の元に集っている人々も「鎌倉殿」としての頼朝しか知らぬであろう。
しかし、この女性達は他の人が知らぬ兄を熟知している。
━━ 乳母とは、すごいものだな。
と思う。
前回へ 次回へ











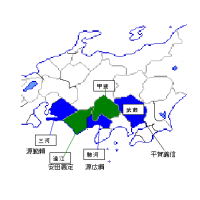
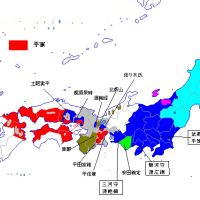
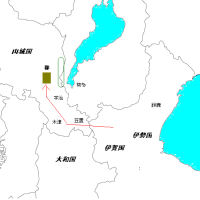

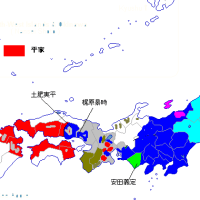
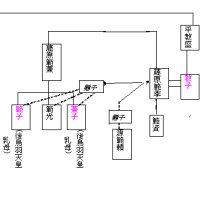
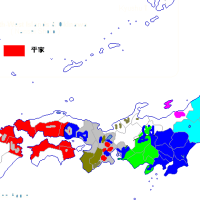
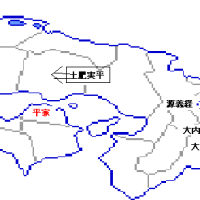
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます