範頼が三河に戻った頃には養和元年(1181年)の秋もすっかり深まっていた。
範頼が三河を留守にしている間代わりにそこに駐留していた安達盛長、和田義盛がまず範頼を出迎えた。
和田義盛とは平常に話をすることができた。
しかし、安達盛長との対面においては奇妙な緊張が走っていた。
盛長は人当たりが良い。
なのに盛長に対して範頼は妙に緊張する。
将来の妻の父、つまり舅になる人物になってしまったがゆえである。
盛長の範頼を見る目も複雑なものとなっている。
今まで何気なく普通に話していた男性二人が瑠璃という一人の女性を挟んで奇妙な緊張感を生じる関係になってしまった。
そのような二人を周囲は面白おかしく見つめている。
「さあ、さあ祝宴じゃ。鎌倉殿と蒲殿の再会と蒲殿の嫁迎えを寿ぐ祝宴じゃ。」
和田義盛が大きな声で誘った。
気まずい二人は半ば強引に祝宴へと送り込まれる。
いつもは酒がでるといつの間にか多くを飲み干して正体無く酔ってしまう範頼である。
しかし、今回は全く酒が進まない。
一方いくら飲んでも酒に溺れない盛長は今回は周囲に酒を勧めることも無く一人で黙々と杯を飲み干している。
そして延々と娘の昔話を周囲にしている。
酔って同じ話ばかりくどくどと繰り返す。
周囲はいい加減呆れて盛長から離れていく。
盛長の話を聞くのは自然範頼となる。
範頼は姿勢を正したまま延々と盛長の昔話を聞く。
そしてしまいにはこう言い出した。
「いーか、よーく聞け
娘は俺の宝だ。目の中に入れてもいたくねー かわいー娘だ。
娘を泣かしたりしたら、わしゃーおめえをぜってーにゆるさねーからな。
いーか ぜっていに娘を幸せにしろよ、このばかやろーが。」
背筋をピンと伸ばし、体のあちらこちらを緊張させながら
酒に酔って眠りこむ直前の盛長の言葉を範頼は受け止めていた。
冷たい夜風が当たらぬよう、範頼は自分の衣を盛長にそっと掛けて杯を一つ飲み干した。
盛長の頭には白髪が多く、顔のあちらこちらに皺が刻まれている。
その寝顔には寂しさがあった。
前回へ 次回へ

範頼が三河を留守にしている間代わりにそこに駐留していた安達盛長、和田義盛がまず範頼を出迎えた。
和田義盛とは平常に話をすることができた。
しかし、安達盛長との対面においては奇妙な緊張が走っていた。
盛長は人当たりが良い。
なのに盛長に対して範頼は妙に緊張する。
将来の妻の父、つまり舅になる人物になってしまったがゆえである。
盛長の範頼を見る目も複雑なものとなっている。
今まで何気なく普通に話していた男性二人が瑠璃という一人の女性を挟んで奇妙な緊張感を生じる関係になってしまった。
そのような二人を周囲は面白おかしく見つめている。
「さあ、さあ祝宴じゃ。鎌倉殿と蒲殿の再会と蒲殿の嫁迎えを寿ぐ祝宴じゃ。」
和田義盛が大きな声で誘った。
気まずい二人は半ば強引に祝宴へと送り込まれる。
いつもは酒がでるといつの間にか多くを飲み干して正体無く酔ってしまう範頼である。
しかし、今回は全く酒が進まない。
一方いくら飲んでも酒に溺れない盛長は今回は周囲に酒を勧めることも無く一人で黙々と杯を飲み干している。
そして延々と娘の昔話を周囲にしている。
酔って同じ話ばかりくどくどと繰り返す。
周囲はいい加減呆れて盛長から離れていく。
盛長の話を聞くのは自然範頼となる。
範頼は姿勢を正したまま延々と盛長の昔話を聞く。
そしてしまいにはこう言い出した。
「いーか、よーく聞け
娘は俺の宝だ。目の中に入れてもいたくねー かわいー娘だ。
娘を泣かしたりしたら、わしゃーおめえをぜってーにゆるさねーからな。
いーか ぜっていに娘を幸せにしろよ、このばかやろーが。」
背筋をピンと伸ばし、体のあちらこちらを緊張させながら
酒に酔って眠りこむ直前の盛長の言葉を範頼は受け止めていた。
冷たい夜風が当たらぬよう、範頼は自分の衣を盛長にそっと掛けて杯を一つ飲み干した。
盛長の頭には白髪が多く、顔のあちらこちらに皺が刻まれている。
その寝顔には寂しさがあった。
前回へ 次回へ











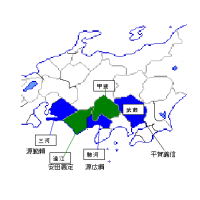
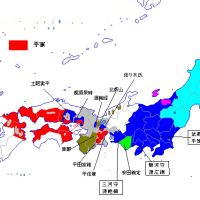
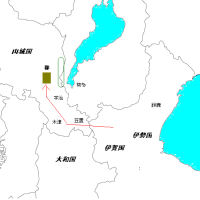

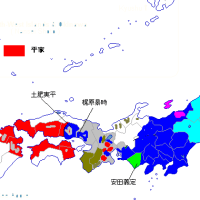
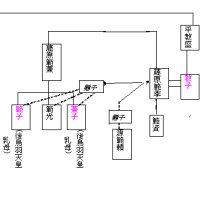
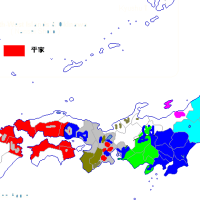
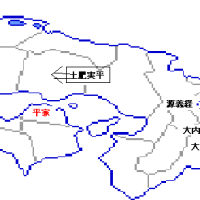
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます