山々の間を切り開いた崖に挟まれた道を通り過ぎるとそこは鎌倉。
範頼にとっておよそ二ヶ月ぶりの鎌倉だった。
先日ここを経ったときにはまだ寒く感じられた浜風が今は春の潮の香を運んでいる。
そしていままで鎌倉に入ったときと違う気持ちが範頼の心の中に芽生えている。
それは、「なつかしさ」だった。
会いたい人がそこに待つなつかしさ。
そう、妻の瑠璃が我が家で待っているのである。
婚儀から数日だけしか共に過ごしていない妻。
それでも、かけがえの無いひと。
鎌倉に入っても妻が待つ我が家への道のりがひときわ程遠く感じられた。
大蔵御所で一通りの儀礼と手続きを済ますと、範頼は急いで我が家へと戻った。
瑠璃は、門の前で待ち構えていた。
夫の無事な姿を見つけると顔がぱっと明るくなった。
範頼も馬を急がせる。
瑠璃だけではない。館に仕える者達が暖かく迎え入れる。
その一行の中に何故か藤七が新太郎の手を引いて待ち構えている。
瑠璃は、自ら夫の足を洗い体を拭き清め着替させた。
その日は、範頼、当麻太郎、吉見次郎などの無事の帰還を祝って宴が張られた。
当麻太郎と吉見次郎は大酒を飲み、大いに歌い踊った。
雑色たちも別の部屋で盛り上がっている。
だが、宴で真っ先に酔って潰れるはずの範頼はこの日は例によって食事を大量に平らげたが、酒は一口あてただけでであまり飲まない。
近くで瑠璃の目が光っていた。
その瑠璃に範頼は意味ありげな視線を送る。瑠璃は恥ずかしそうに見つめ返す。
範頼を除く皆が酔っ払って夫々の部屋に戻った後で、瑠璃は自ら女達の指揮をとって片づけを始めた。
そういえば郎党達の部屋の支度も全て瑠璃が差配していた。
その夜瑠璃は忙しかった。
結果範頼一人で少し待たされることになる。
「殿、お待たせいたしました。」
そういって瑠璃が寝所にはいってきたのはかなり夜が更けてから・・・
ようやく二人きりになれた。
「待ったぞ。」
と範頼は少し不機嫌に答えた。
夜は更けていった。
明け方近くなって瑠璃は範頼に忙しく働いていた訳を語る。
「志津がまた妊りました。」
「は?」
「こたびはつわりが酷いので、無理はさせれません。今は少し休ませています。」
侍女頭の志津が動けないため、館のことは瑠璃一人が取り仕切らなければならなかったのである。
「そうだったのか・・・」
藤七が新太郎を連れて館にいた理由がやっとわかった。
━━ それにしても藤七のやついつの間に・・・
「瑠璃」
「殿、もう夜が空けまするが・・・」
「かまわぬ、私達も藤七や志津に負けてはおられぬ。」
「朝餉の支度が・・・」
「今日は遅れても構わぬ。」
翌朝、二日酔いさめやらぬ郎党や従者たちは日がかなり高くなるまで腹を空かせることになった。
前回へ 目次へ 次回へ

範頼にとっておよそ二ヶ月ぶりの鎌倉だった。
先日ここを経ったときにはまだ寒く感じられた浜風が今は春の潮の香を運んでいる。
そしていままで鎌倉に入ったときと違う気持ちが範頼の心の中に芽生えている。
それは、「なつかしさ」だった。
会いたい人がそこに待つなつかしさ。
そう、妻の瑠璃が我が家で待っているのである。
婚儀から数日だけしか共に過ごしていない妻。
それでも、かけがえの無いひと。
鎌倉に入っても妻が待つ我が家への道のりがひときわ程遠く感じられた。
大蔵御所で一通りの儀礼と手続きを済ますと、範頼は急いで我が家へと戻った。
瑠璃は、門の前で待ち構えていた。
夫の無事な姿を見つけると顔がぱっと明るくなった。
範頼も馬を急がせる。
瑠璃だけではない。館に仕える者達が暖かく迎え入れる。
その一行の中に何故か藤七が新太郎の手を引いて待ち構えている。
瑠璃は、自ら夫の足を洗い体を拭き清め着替させた。
その日は、範頼、当麻太郎、吉見次郎などの無事の帰還を祝って宴が張られた。
当麻太郎と吉見次郎は大酒を飲み、大いに歌い踊った。
雑色たちも別の部屋で盛り上がっている。
だが、宴で真っ先に酔って潰れるはずの範頼はこの日は例によって食事を大量に平らげたが、酒は一口あてただけでであまり飲まない。
近くで瑠璃の目が光っていた。
その瑠璃に範頼は意味ありげな視線を送る。瑠璃は恥ずかしそうに見つめ返す。
範頼を除く皆が酔っ払って夫々の部屋に戻った後で、瑠璃は自ら女達の指揮をとって片づけを始めた。
そういえば郎党達の部屋の支度も全て瑠璃が差配していた。
その夜瑠璃は忙しかった。
結果範頼一人で少し待たされることになる。
「殿、お待たせいたしました。」
そういって瑠璃が寝所にはいってきたのはかなり夜が更けてから・・・
ようやく二人きりになれた。
「待ったぞ。」
と範頼は少し不機嫌に答えた。
夜は更けていった。
明け方近くなって瑠璃は範頼に忙しく働いていた訳を語る。
「志津がまた妊りました。」
「は?」
「こたびはつわりが酷いので、無理はさせれません。今は少し休ませています。」
侍女頭の志津が動けないため、館のことは瑠璃一人が取り仕切らなければならなかったのである。
「そうだったのか・・・」
藤七が新太郎を連れて館にいた理由がやっとわかった。
━━ それにしても藤七のやついつの間に・・・
「瑠璃」
「殿、もう夜が空けまするが・・・」
「かまわぬ、私達も藤七や志津に負けてはおられぬ。」
「朝餉の支度が・・・」
「今日は遅れても構わぬ。」
翌朝、二日酔いさめやらぬ郎党や従者たちは日がかなり高くなるまで腹を空かせることになった。
前回へ 目次へ 次回へ











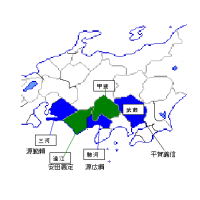
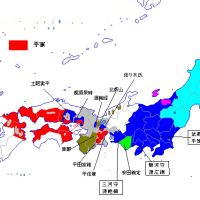
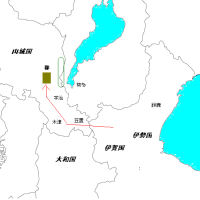

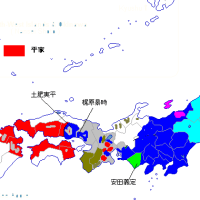
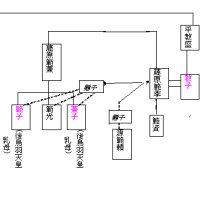
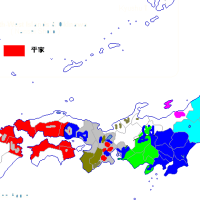
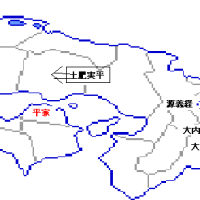
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます