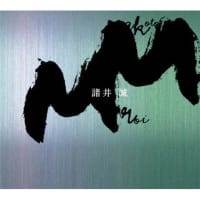7月に入ると待望のミラノ・ピッコロ座の公演がありました(世田谷パブリックシアター)。演目はおなじみの「アルレッキーノ=二人の主人を一度にもつと」で、演出はジョルジュ・ストレーレルです。16世紀イタリアに起源をもつ「コンメディア・デッラルテ=伝統仮面喜劇」を現代に甦らせた名舞台で、60年にわたり世界40カ国、2600回もの公演を重ねています(私も学生時代に日本公演をテレビで見ています)。
8月と9月は何もなく、10月に入ります。二期会の「蝶々夫人」(東京文化会館)はすでに見たことのある栗山昌良さんの演出。このオペラの筋立てには日本国民としては腹立たしい場面もありますが、音楽の美しさは否定のしようがなく、ついつい引き込まれてしまいます。
10月と言えば、東京オペラシティのコンサートホールで行われた狂言風オペラ「魔笛」はじつに面白かった。狂言と言うものが私にとっては未知のものだっただけに、その表現力の奥深さに感心しました。テーマはモーツァルトの魔笛、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン管楽ゾリスデンが魔笛の主要アリアを演奏しつつ、舞台の上ではザラストロや夜の女王、パパケーノなどに扮した狂言役者が楽しい芝居を展開します。ミラノ・ピッコロ座との共通点もあり、大いに楽しみました。茂山千之丞、茂山あきら、茂山正邦、茂山逸平、茂山童司などが出演。
ロン・カーターが新アルバムのプロモーションを兼ねて来日し、ブルーノート東京で約1週間のライブを行いました。スイングジャーナルからの依頼で、ライブを見た翌日にロン・カーターへのインタビュー取材を行いました。スイングジャーナル12月号に書いた原稿は以下のものです。
激しい風雨が通り過ぎた翌日のブルーノート東京・午後1時、ステージも客席も薄明かりの中に包まれていて、これから数時間後に巻き起こる喝采をそっと待ち続けているようだ。静かな午後の時間が流れるバックステージの片隅で、ロン・カーターはゆっくりと語り始めた。
「昨年、自伝を出版したんだ。表紙の写真を撮ったのはキャロル・フリードマン、今年リリースしたニュー・アルバム“ロン・カーターの世界”と同じものだ」。その写真は、深い濃度をもつモノクロの仕上がりで、ベースのネックに顔を寄せて目を伏せているロン・カーターの姿は、追憶の風景に祈りを捧げているようで印象的だ。
今回のアルバムは、彼のプロ・デビュー50周年記念となっている。「プロとしてのキャリアの始まりはチコ・ハミルトンのバンドだった。大学生の頃、チコが町にやって来た。バンドのチェリストが抜けることになったので、ニューヨークに来たら連絡しろと言う。いざニューヨークへ行くと、チェロの代わりにベーシストが辞めていた。そこで、お前はベースを弾け!とチコに言われた。その時から私はベーシストになってしまった」。
なんと、ベーシストとしてのプロ・デビューの動機は意外なものだった。その後に、マイルス・デイビス・クインテットの黄金時代が始まる。ベーシストとしての名声を不動のものとした後の活躍は今さら挙げるまでもないだろう。「ベースの世界における自分の位置にはとらわれていない。それは、聴衆やジャーナリストが決めることだ。自分はあくまで自分の耳に聞こえる音を素直に表現する。ライブが終わり、今日は最善を尽くせたと感じることが最も大切だと思う」。
ニュー・アルバム、“ロン・カーターの世界”は、厳格なテンションとエレガントな品格を併せ持ったロン・カーター自身をそのまま音に表したような仕上がりだ。盟友、ボブ・フリードマンのアレンジも冴えている。室内楽的な美しさ、ジャズ本来の楽しさ…。「ほとんどが1テイクで録音した。オーバー・ダビングなどは一切行っていない。アルバムのコンセプトは、ジャズ・クラブの演奏と同じ雰囲気をCDに収録することだった」。メンバー構成は、ピアノ・トリオにパーカッションを加えたカルテット。「サウンドが色彩的になったと思う。大切なのは、彼が発する音の中に演奏家の人間性が表されていることだ」。今回のメンバーを起用した意図を聞くとロン・カーターらしい答えが返ってきた。「リハーサル、ステージ、空港…とにかく、遅刻をしない人を選んだ(笑)」、そしてこう続けた。「私自身のコンセプトを理解し、それを共有できるミュージシャンたちを集めた。皆、私に信頼を寄せてくれている」。
ありきたりな質問とは知りつつ、インタビューの最後に日本の聴衆に対する印象を聞いた。「音楽への深い愛情と豊かな知識に溢れている。ミュージシャンひとりひとりの歴史まで理解している。ハービーのこと、ウエインのこと、トニーのこと、そして、私のことも…」。しばしの間、沈黙が訪れた。ロン・カーターは、自伝の表紙を飾るあのモノクロ写真のようにそっと目を伏せた。
10月にはもうひとつスイングジャーナルの仕事があり、ヤロン・ヘルマン・トリオを取材しました。その原稿は次のようなものです(掲載は12月号、今年は他に、井上陽介さん、鈴木良雄さんのインタビュー=11月号、マイク・デル・フェローへのメール・インタビュー=12月号などを行いました)。
今年の4月、感動的なソロ・パフォーマンスを披露したヤロン・ヘルマンが、今度は自己のトリオを率いて来日した。「ストンピン」や「メッセージ・イン・ア・ボトル」、「ライラ・ライラ」など、日本では今年9月にリリースされたアルバム「ア・タイム・フォー・エヴリシング」に収められた曲を中心としたプログラムだが、レコーディング時のメンバーとは異なり、ベースにシモン・タイユ、ドラムスにはセドリック・ベックというイスラエル出身のリズム・セクションがステージに上がった。
ソロの時と同じように、最弱音から強奏まで、ヘルマンのピアノはまったく音が濁ることがない。澄みわたる抒情を基調としつつ、88個の鍵盤を駆使してピアノの機能を最大限に引き出すアグレッシブな演奏は、タイユとベック二人の好サポートを得てさらにパワーアップした。特に繊細なシンバル・ワークが冴えるベックのドラムスは、ビートを刻むというよりもメロディを歌っているようで、ヘルマンが奏でる旋律線に寄り添いながら、見事な調和を生み出していた。
このトリオを、クラシック音楽のコンサートが開かれることの多いすみだトリフォニーホールで聞けたことは収穫だった。PAを使わない音場のバランスは、彼ら自身が互いの音を聞きながら調整し合っているようで、常に最良の状態に保たれている。その室内楽的なアンサンブルはじつに心地よい。ヘルマンは、このホールの優れた残響性能を巧みに利用し、音の残像を極上のアコースティックの中にいつまでも浮遊させていた。空間に放たれた音の表情が、これほど豊かに感じられる体験は滅多にあるものではない。
アルバムからの選曲の他には、「煙が目にしみる」「虹の彼方に」といったスタンダードが披露され、最良の音空間に水をさす騒々しいMCは、最後まで一言もなかった。
10月は他にキム・ドクス+山下洋輔に行きましたが、このデュオの意味が私にはよく分かりませんでした。また、浜離宮朝日ホールで聞くキム・ドクスのチャンゴの音が、客席にはかなり刺激的な音として伝わり、私には少々キツイ体験でした。
11月には二期会の「カプリッチョ」を見ました。リヒャルト・シュトラウス最晩年の作品ですが、このオペラがこれほど美しい音楽に彩られているとは認識していませんでした。伯爵令嬢マドレーヌを演じた佐々木典子さんは本当に素晴らしかったです。
ジュリエット・グレコの公演(オーチャードホール)は、座席の位置も前の方で彼女の一挙手一投足を凝視することが出来ました。実際、すでに老境にある彼女の様子を見ていると、あの美しくエレガントな姿を今のうちに目に焼きつけておくべきと思いました。前回の来日のときと比べても、歌うというよりは、語るという感じが多くなっている印象がありましたが、それもまたシャンソンの魅力です。
12月に入るとレ・ヴァン・フランセの演奏会がありました。フルートのエマニュエル・パユを擁するフランスの木管アンサンブルです。マルティヌー、ラヴェル、プーランクなどが演奏されました。
8月と9月は何もなく、10月に入ります。二期会の「蝶々夫人」(東京文化会館)はすでに見たことのある栗山昌良さんの演出。このオペラの筋立てには日本国民としては腹立たしい場面もありますが、音楽の美しさは否定のしようがなく、ついつい引き込まれてしまいます。
10月と言えば、東京オペラシティのコンサートホールで行われた狂言風オペラ「魔笛」はじつに面白かった。狂言と言うものが私にとっては未知のものだっただけに、その表現力の奥深さに感心しました。テーマはモーツァルトの魔笛、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン管楽ゾリスデンが魔笛の主要アリアを演奏しつつ、舞台の上ではザラストロや夜の女王、パパケーノなどに扮した狂言役者が楽しい芝居を展開します。ミラノ・ピッコロ座との共通点もあり、大いに楽しみました。茂山千之丞、茂山あきら、茂山正邦、茂山逸平、茂山童司などが出演。
ロン・カーターが新アルバムのプロモーションを兼ねて来日し、ブルーノート東京で約1週間のライブを行いました。スイングジャーナルからの依頼で、ライブを見た翌日にロン・カーターへのインタビュー取材を行いました。スイングジャーナル12月号に書いた原稿は以下のものです。
激しい風雨が通り過ぎた翌日のブルーノート東京・午後1時、ステージも客席も薄明かりの中に包まれていて、これから数時間後に巻き起こる喝采をそっと待ち続けているようだ。静かな午後の時間が流れるバックステージの片隅で、ロン・カーターはゆっくりと語り始めた。
「昨年、自伝を出版したんだ。表紙の写真を撮ったのはキャロル・フリードマン、今年リリースしたニュー・アルバム“ロン・カーターの世界”と同じものだ」。その写真は、深い濃度をもつモノクロの仕上がりで、ベースのネックに顔を寄せて目を伏せているロン・カーターの姿は、追憶の風景に祈りを捧げているようで印象的だ。
今回のアルバムは、彼のプロ・デビュー50周年記念となっている。「プロとしてのキャリアの始まりはチコ・ハミルトンのバンドだった。大学生の頃、チコが町にやって来た。バンドのチェリストが抜けることになったので、ニューヨークに来たら連絡しろと言う。いざニューヨークへ行くと、チェロの代わりにベーシストが辞めていた。そこで、お前はベースを弾け!とチコに言われた。その時から私はベーシストになってしまった」。
なんと、ベーシストとしてのプロ・デビューの動機は意外なものだった。その後に、マイルス・デイビス・クインテットの黄金時代が始まる。ベーシストとしての名声を不動のものとした後の活躍は今さら挙げるまでもないだろう。「ベースの世界における自分の位置にはとらわれていない。それは、聴衆やジャーナリストが決めることだ。自分はあくまで自分の耳に聞こえる音を素直に表現する。ライブが終わり、今日は最善を尽くせたと感じることが最も大切だと思う」。
ニュー・アルバム、“ロン・カーターの世界”は、厳格なテンションとエレガントな品格を併せ持ったロン・カーター自身をそのまま音に表したような仕上がりだ。盟友、ボブ・フリードマンのアレンジも冴えている。室内楽的な美しさ、ジャズ本来の楽しさ…。「ほとんどが1テイクで録音した。オーバー・ダビングなどは一切行っていない。アルバムのコンセプトは、ジャズ・クラブの演奏と同じ雰囲気をCDに収録することだった」。メンバー構成は、ピアノ・トリオにパーカッションを加えたカルテット。「サウンドが色彩的になったと思う。大切なのは、彼が発する音の中に演奏家の人間性が表されていることだ」。今回のメンバーを起用した意図を聞くとロン・カーターらしい答えが返ってきた。「リハーサル、ステージ、空港…とにかく、遅刻をしない人を選んだ(笑)」、そしてこう続けた。「私自身のコンセプトを理解し、それを共有できるミュージシャンたちを集めた。皆、私に信頼を寄せてくれている」。
ありきたりな質問とは知りつつ、インタビューの最後に日本の聴衆に対する印象を聞いた。「音楽への深い愛情と豊かな知識に溢れている。ミュージシャンひとりひとりの歴史まで理解している。ハービーのこと、ウエインのこと、トニーのこと、そして、私のことも…」。しばしの間、沈黙が訪れた。ロン・カーターは、自伝の表紙を飾るあのモノクロ写真のようにそっと目を伏せた。
10月にはもうひとつスイングジャーナルの仕事があり、ヤロン・ヘルマン・トリオを取材しました。その原稿は次のようなものです(掲載は12月号、今年は他に、井上陽介さん、鈴木良雄さんのインタビュー=11月号、マイク・デル・フェローへのメール・インタビュー=12月号などを行いました)。
今年の4月、感動的なソロ・パフォーマンスを披露したヤロン・ヘルマンが、今度は自己のトリオを率いて来日した。「ストンピン」や「メッセージ・イン・ア・ボトル」、「ライラ・ライラ」など、日本では今年9月にリリースされたアルバム「ア・タイム・フォー・エヴリシング」に収められた曲を中心としたプログラムだが、レコーディング時のメンバーとは異なり、ベースにシモン・タイユ、ドラムスにはセドリック・ベックというイスラエル出身のリズム・セクションがステージに上がった。
ソロの時と同じように、最弱音から強奏まで、ヘルマンのピアノはまったく音が濁ることがない。澄みわたる抒情を基調としつつ、88個の鍵盤を駆使してピアノの機能を最大限に引き出すアグレッシブな演奏は、タイユとベック二人の好サポートを得てさらにパワーアップした。特に繊細なシンバル・ワークが冴えるベックのドラムスは、ビートを刻むというよりもメロディを歌っているようで、ヘルマンが奏でる旋律線に寄り添いながら、見事な調和を生み出していた。
このトリオを、クラシック音楽のコンサートが開かれることの多いすみだトリフォニーホールで聞けたことは収穫だった。PAを使わない音場のバランスは、彼ら自身が互いの音を聞きながら調整し合っているようで、常に最良の状態に保たれている。その室内楽的なアンサンブルはじつに心地よい。ヘルマンは、このホールの優れた残響性能を巧みに利用し、音の残像を極上のアコースティックの中にいつまでも浮遊させていた。空間に放たれた音の表情が、これほど豊かに感じられる体験は滅多にあるものではない。
アルバムからの選曲の他には、「煙が目にしみる」「虹の彼方に」といったスタンダードが披露され、最良の音空間に水をさす騒々しいMCは、最後まで一言もなかった。
10月は他にキム・ドクス+山下洋輔に行きましたが、このデュオの意味が私にはよく分かりませんでした。また、浜離宮朝日ホールで聞くキム・ドクスのチャンゴの音が、客席にはかなり刺激的な音として伝わり、私には少々キツイ体験でした。
11月には二期会の「カプリッチョ」を見ました。リヒャルト・シュトラウス最晩年の作品ですが、このオペラがこれほど美しい音楽に彩られているとは認識していませんでした。伯爵令嬢マドレーヌを演じた佐々木典子さんは本当に素晴らしかったです。
ジュリエット・グレコの公演(オーチャードホール)は、座席の位置も前の方で彼女の一挙手一投足を凝視することが出来ました。実際、すでに老境にある彼女の様子を見ていると、あの美しくエレガントな姿を今のうちに目に焼きつけておくべきと思いました。前回の来日のときと比べても、歌うというよりは、語るという感じが多くなっている印象がありましたが、それもまたシャンソンの魅力です。
12月に入るとレ・ヴァン・フランセの演奏会がありました。フルートのエマニュエル・パユを擁するフランスの木管アンサンブルです。マルティヌー、ラヴェル、プーランクなどが演奏されました。