今日はジャンクファイルに邪魔されなかったので、アップします。下記の小論を読まれた方もいると思います。「緊急事態」法の持つ危険性について書いたものですが、現在の状況を踏まえ、また歴史的事実とも関連させて、色々示唆に富んでいて考えさせられた。民主主義の限界性を明確にしている。緊急事態が現実になると人々の基本的権利が大幅に制限されるので、戒厳令に近い状態になる。
さらに危険なのは、時の政府がテロを取り締まるのではなく、それを容認し、テロを口実にして治安強化(アメリカの9・11以降の状況を想起)を図り、情報管理を強化(秘密保護法が効力を発揮)し、マスコミの報道は大本営発表と変わらなくなる。
警察権力が強化され警察国家化という状態になる。
この小論は安倍内閣が改憲の優先事項に「緊急事態」条項を考えていることに対し危険性を明確に示した点で、意義のあるものであるが、問題点もいくつかある。一つは階級的視点がないので、戦前のドイツの事例では、ドイツ共産党のナチス台頭に対するスタンスが重要なポイントだが、それには触れていない。だから、このような状況に対し、何を武器に闘うのかが何ら提起されていない。
改憲反対だけでは、改憲を阻止することは難しいし、主体の危機を克服することはできないので、勝利の展望はない。
法治国家から安全国家へ
緊急事態は民主主義を守る盾などではなく、それどころか、 常に独裁者たちを伴っている。
ジョルジュ・アガンベン <イタリアの哲学者。1942年ローマ生まれ。ヴェネッツィ ア建築大学教授を務めたのち、現在はズヴィッツェラ・イタリアーノ大学メンドリジ オ建築アカデミーで教えている。最近の邦訳書に『身体の使用—脱構成的可能態の 理論のために』(みすず書房)>
訳=西谷 修 <1950年生まれ。立教大学大学院文学研究科特任教授。東京外国 語大学名誉教授>
(雑誌「世界」3月号)
フランスでは緊急事態が2月末まで延長されたが、そのことの真の狙いは、我々になじみの国家モデルのラジカルな変容というコンテクストに置いてみなければ理解できないだろう。まず何より、無責任な政治家たち(男も女も)の言うことの化けの皮をはがさなければならない。かれらによれば、緊急事態は民主主義を守る盾なのだそうだ。
それが真実と正反対だということを、歴史家たちは完全に知っている。緊急事態とはまさに、全体主義的権力がヨーロッパに腰を据えたときの手立てだったのだ。例えば、ヒットラーの権力掌握に先立つ数年間、ワイマールの社会民主主義政権は頻繁に緊急事態(ドイツでは例外状態と言う)に頼っており、そのためドイツは1933年以前にすでに議会民主制ではなくなっていたと言って良いほどだった。
ヒトラーが首相に任命されて最初にとった行為も、緊急事態を発令することだったが、それは2度と解除されることはなかった。ドイツでナチが数々の犯罪行為を何の処罰も受けずに侵しえたということに人は驚きもするが、驚くのはそうした行為が全く合法的だったということを忘れているからだ。というのも、国は例外状態に服し、個人的自由の諸々は停止されていたのだから。
フランスでこのような事態が起こり得ないとなぜいえるのか、私にはわからない。極右政権がみずからの目的のために緊急事態を活用するということは容易に想像できる。主秋党政権が今や市民をそれに慣れさせているのだから。長引き緊急事態のもとに置かれ、警察の取り締まり活動が徐々に司法権力にとって代わる国では、公共的諸制度は急速かつ不可逆的に変質してしまうことを覚悟しなければならない。
このことは今日、状況ではなおさら真実だ。というのも、緊急事態は今日、西洋民主主義諸国をいまや安全国家(アメリカの政治学者たちの語っている「セキュリチィー・ステート」だ)と呼ぶべき何ものかに向かって進化させているプロセスのなかに組み込まれているからだ。「安全(保障)」という語は政治的言説に広く浸透していて、「安全理性」はかつての「国家理性」の地位を占めてしまったと言っても間違う恐れはないだろう。とはいえ、政府のこの新しい形の分析はなされていない。「安全国家」は「法治国家」にも、ミッシェル・フーコが「規律社会」と呼んだものにも属していない以上、ここでありうべき定義のためのいくつかの目安を立てておくのがよいだろう。
我々の政治哲学に極めて深い影響を与えているトマス・ホブッスのイギリスモデルでは、主権者に権力を移譲する契約は、相互の恐怖と万人の万人に対する闘争とを前提にしている。つまり国家とはその恐怖を終わらせるべく到来するものなのだ。「安全国家」ではこのシェーマが逆転する。国家は恐怖の上に持続的に身を持しており、何としてでもそれを維持しなければならない。というのも、国家は恐怖からその本質的機能と正統性を引き出しているからだ。
フーコはすでに、「安全」という語がフランスで政治的言説に初めて登場したのは革命以前の重農主義政府の下においてであり、そこで問題になっていたのは災厄や飢饉の予防ではなく、それを起こるにまかせ、しかる後にそれを統御し都合の良いとみなされる方向に導くことだったと示している。
緊急事態は民主主義を守る盾などではなく、それどころか、 常に独裁者たちを伴っている。
ジョルジュ・アガンベン <イタリアの哲学者。1942年ローマ生まれ。ヴェネッツィ ア建築大学教授を務めたのち、現在はズヴィッツェラ・イタリアーノ大学メンドリジ オ建築アカデミーで教えている。最近の邦訳書に『身体の使用—脱構成的可能態の 理論のために』(みすず書房)>
訳=西谷 修 <1950年生まれ。立教大学大学院文学研究科特任教授。東京外国 語大学名誉教授>
(雑誌「世界」3月号)
フランスでは緊急事態が2月末まで延長されたが、そのことの真の狙いは、我々になじみの国家モデルのラジカルな変容というコンテクストに置いてみなければ理解できないだろう。まず何より、無責任な政治家たち(男も女も)の言うことの化けの皮をはがさなければならない。かれらによれば、緊急事態は民主主義を守る盾なのだそうだ。
それが真実と正反対だということを、歴史家たちは完全に知っている。緊急事態とはまさに、全体主義的権力がヨーロッパに腰を据えたときの手立てだったのだ。例えば、ヒットラーの権力掌握に先立つ数年間、ワイマールの社会民主主義政権は頻繁に緊急事態(ドイツでは例外状態と言う)に頼っており、そのためドイツは1933年以前にすでに議会民主制ではなくなっていたと言って良いほどだった。
ヒトラーが首相に任命されて最初にとった行為も、緊急事態を発令することだったが、それは2度と解除されることはなかった。ドイツでナチが数々の犯罪行為を何の処罰も受けずに侵しえたということに人は驚きもするが、驚くのはそうした行為が全く合法的だったということを忘れているからだ。というのも、国は例外状態に服し、個人的自由の諸々は停止されていたのだから。
フランスでこのような事態が起こり得ないとなぜいえるのか、私にはわからない。極右政権がみずからの目的のために緊急事態を活用するということは容易に想像できる。主秋党政権が今や市民をそれに慣れさせているのだから。長引き緊急事態のもとに置かれ、警察の取り締まり活動が徐々に司法権力にとって代わる国では、公共的諸制度は急速かつ不可逆的に変質してしまうことを覚悟しなければならない。
このことは今日、状況ではなおさら真実だ。というのも、緊急事態は今日、西洋民主主義諸国をいまや安全国家(アメリカの政治学者たちの語っている「セキュリチィー・ステート」だ)と呼ぶべき何ものかに向かって進化させているプロセスのなかに組み込まれているからだ。「安全(保障)」という語は政治的言説に広く浸透していて、「安全理性」はかつての「国家理性」の地位を占めてしまったと言っても間違う恐れはないだろう。とはいえ、政府のこの新しい形の分析はなされていない。「安全国家」は「法治国家」にも、ミッシェル・フーコが「規律社会」と呼んだものにも属していない以上、ここでありうべき定義のためのいくつかの目安を立てておくのがよいだろう。
我々の政治哲学に極めて深い影響を与えているトマス・ホブッスのイギリスモデルでは、主権者に権力を移譲する契約は、相互の恐怖と万人の万人に対する闘争とを前提にしている。つまり国家とはその恐怖を終わらせるべく到来するものなのだ。「安全国家」ではこのシェーマが逆転する。国家は恐怖の上に持続的に身を持しており、何としてでもそれを維持しなければならない。というのも、国家は恐怖からその本質的機能と正統性を引き出しているからだ。
フーコはすでに、「安全」という語がフランスで政治的言説に初めて登場したのは革命以前の重農主義政府の下においてであり、そこで問題になっていたのは災厄や飢饉の予防ではなく、それを起こるにまかせ、しかる後にそれを統御し都合の良いとみなされる方向に導くことだったと示している。
今日問われている「安全(保障)」もそれと同様で、テロリズムの予防を目指しているのではなく(それは不可能とは言わないが極めて困難だ、というのも、安全措置は事後にしか有効にならないが、テロリズムは定義からして一連の初発の攻撃だからだ)、人々との新しい関係の確立をねらっている。それは全般化した際限ないコントロールという関係だ—そのために、市民の情報通信データーの全般的コントロールを許すような措置、パソコンの中身全部を接収することもできるような措置がとりわけ求められる。
最初に指摘したい危険は、テロリズムと「安全国家」とのシステム的関係を作り出す方向への偏りだ。もし国家が自らを正統化するために恐怖を必要とすれば、その時には、最悪、恐怖を生み出さねばならなくなる。あるいは少なくとも、それが生じるのを妨げないことになる。だから諸国は、国内で戦うべきテロリズムをはびこらせるような外交政策をとり、テロリスト組織に資金を流しているとわかっている諸国と友好関係を保ったり、武器を売ったりさえするということになる。
第2の点—これを把握しておくのは重要だ—は、主権の保持者とみなされていた市民や民衆の政治的地位の変化だ。「安全国家」においては、市民がしだいに脱政治化と呼ぶべき状態に向かう抑えがたい傾向が生じることになり、政治生活への参加は選挙の世論調査だけになってしまう。この傾向はナチ法学者たちによって理論化されているだけにいっそう警戒を要する。彼らは、民衆を本質的に政治に向かない要素と定義し、国家はその保護と成長を保障すべきものとしている。
ところで、この法学者たちによれば、この政治に向かない要素を政治化する方法が一つだけある。出自と人権の同等ということだ。それが民衆を外国人と敵とから区別する。ここでは「ナチ国家」と現代の「安全国家」を混同せよと言っているのではない。理解すべきこと、それは、市民を非政治化すると、彼らをその受動性から出させるためには、異邦の敵に対する恐怖によってかり出すほかないということだ。ただし、その敵は国外にいるだけではない(ドイツのユダヤ人がそうであり、今日のフランスのムスリムがそうだ)。
二重国籍の市民の国籍を剥奪するという不吉な法案は、このような枠組みの中で考えなければならない。これは、1926年の「イタリア市民にふさわしからぬ市民」の国籍剥奪を決めたファシスト法やユダヤ人の国籍剥奪に関するナチの法を思い起こさせる。
第3の点—この重要性も過小評価してはならない—は、公共領域で真実と確かさを確立する指標が根本的に変わってしまうことだ。テロリスト犯罪の報告で注意深い観察者をまず驚かすのは、司法的確実性の立証が全く放棄されていることだ。
法治国家においては、犯罪はもっぱら司法的捜査によって立証されねばならないことになっているが、安全保障のパラダイムのもとでは、警察とそれに依拠するメディアの伝えることで満足しなければならない。それは二つとも、いつもあまり信用できないとみなされている機関だ。だから、輪郭のぼやけた信じがたいことや明らかな矛盾が出来事の拙速な再構成の中に紛れ込み、その再構成は検証や改竄のあらゆる可能性を承知でかすめているし、捜査というよりも噂話に似てしまう。ということは、安全国家にとっては、自ら保護を引き受けているはずの市民が、自分たちを脅かすものに関して不確かでいる方が都合が良いということだ。というのも、不確かさはテロルにつきものだからだ。
これと同じ不確かさは、11月20日の緊急事態に関する法文にもみられる。この法文は「その振る舞いが公共秩序と安全確保にとっての脅威であると考える確かな理由があるあらゆる人物」に関係している。「と考える確かな理由」という表現にいかなる司法的意味もないことは全く明らかで、それは「考える」者の自由裁量にかかっているからには、いつでもだれにでも適用することができる。ところが、安全国家ではこの不確定な言い回し、法律家たちが法の確実性の原則に反するとみなしてきたこの言い回しが規範となるのである。
同様の不確かさ、同様の曖昧さが、フランスはテロとの戦争のうちにあるとする政治家たちの表明のうちにも回帰している。テロとの戦争とは、用語上の矛盾なのだ。というのは、戦争状態とはまさに、闘うべき敵を明確に同定できるということによって定義されるのだから。安全という観点からは反対に、敵はあいまいなままにとどまり、かつ誰であれ—国内でも国外でも—敵として同定しうるのでなければならない。
最初に指摘したい危険は、テロリズムと「安全国家」とのシステム的関係を作り出す方向への偏りだ。もし国家が自らを正統化するために恐怖を必要とすれば、その時には、最悪、恐怖を生み出さねばならなくなる。あるいは少なくとも、それが生じるのを妨げないことになる。だから諸国は、国内で戦うべきテロリズムをはびこらせるような外交政策をとり、テロリスト組織に資金を流しているとわかっている諸国と友好関係を保ったり、武器を売ったりさえするということになる。
第2の点—これを把握しておくのは重要だ—は、主権の保持者とみなされていた市民や民衆の政治的地位の変化だ。「安全国家」においては、市民がしだいに脱政治化と呼ぶべき状態に向かう抑えがたい傾向が生じることになり、政治生活への参加は選挙の世論調査だけになってしまう。この傾向はナチ法学者たちによって理論化されているだけにいっそう警戒を要する。彼らは、民衆を本質的に政治に向かない要素と定義し、国家はその保護と成長を保障すべきものとしている。
ところで、この法学者たちによれば、この政治に向かない要素を政治化する方法が一つだけある。出自と人権の同等ということだ。それが民衆を外国人と敵とから区別する。ここでは「ナチ国家」と現代の「安全国家」を混同せよと言っているのではない。理解すべきこと、それは、市民を非政治化すると、彼らをその受動性から出させるためには、異邦の敵に対する恐怖によってかり出すほかないということだ。ただし、その敵は国外にいるだけではない(ドイツのユダヤ人がそうであり、今日のフランスのムスリムがそうだ)。
二重国籍の市民の国籍を剥奪するという不吉な法案は、このような枠組みの中で考えなければならない。これは、1926年の「イタリア市民にふさわしからぬ市民」の国籍剥奪を決めたファシスト法やユダヤ人の国籍剥奪に関するナチの法を思い起こさせる。
第3の点—この重要性も過小評価してはならない—は、公共領域で真実と確かさを確立する指標が根本的に変わってしまうことだ。テロリスト犯罪の報告で注意深い観察者をまず驚かすのは、司法的確実性の立証が全く放棄されていることだ。
法治国家においては、犯罪はもっぱら司法的捜査によって立証されねばならないことになっているが、安全保障のパラダイムのもとでは、警察とそれに依拠するメディアの伝えることで満足しなければならない。それは二つとも、いつもあまり信用できないとみなされている機関だ。だから、輪郭のぼやけた信じがたいことや明らかな矛盾が出来事の拙速な再構成の中に紛れ込み、その再構成は検証や改竄のあらゆる可能性を承知でかすめているし、捜査というよりも噂話に似てしまう。ということは、安全国家にとっては、自ら保護を引き受けているはずの市民が、自分たちを脅かすものに関して不確かでいる方が都合が良いということだ。というのも、不確かさはテロルにつきものだからだ。
これと同じ不確かさは、11月20日の緊急事態に関する法文にもみられる。この法文は「その振る舞いが公共秩序と安全確保にとっての脅威であると考える確かな理由があるあらゆる人物」に関係している。「と考える確かな理由」という表現にいかなる司法的意味もないことは全く明らかで、それは「考える」者の自由裁量にかかっているからには、いつでもだれにでも適用することができる。ところが、安全国家ではこの不確定な言い回し、法律家たちが法の確実性の原則に反するとみなしてきたこの言い回しが規範となるのである。
同様の不確かさ、同様の曖昧さが、フランスはテロとの戦争のうちにあるとする政治家たちの表明のうちにも回帰している。テロとの戦争とは、用語上の矛盾なのだ。というのは、戦争状態とはまさに、闘うべき敵を明確に同定できるということによって定義されるのだから。安全という観点からは反対に、敵はあいまいなままにとどまり、かつ誰であれ—国内でも国外でも—敵として同定しうるのでなければならない。
全般的な恐怖状態の維持、市民の脱政治化、あらゆる法の確実性の放棄、この3点が安全国家の特徴であり、この国家は人々を不安にするネタを持っている。というのも、それが意味するのは、一方で、我々が今そこに滑り落ちようとしている安全国家は、仮に安全というのが心配のないことを意味するとすれば、自らが約束するものの反対物であり、むしろ恐れとテロルとを維持するからだ。また他方、安全国家は警察国家であり、司法権力が消滅して、常態となった緊急事態においてしだいに主権者として振る舞うようになる警察の自由裁量の余地を全般化する。
市民がしだいに脱政治化し、いわば潜在的テロリストのようになると、安全国家はついに既知の政治の領域から出て、不確実なゾーンに向かって進むようになるが、そこでは公共的なものと詩的なものとが混ざり合い、そのゾーンの境界はもはや確定しがたい。
市民がしだいに脱政治化し、いわば潜在的テロリストのようになると、安全国家はついに既知の政治の領域から出て、不確実なゾーンに向かって進むようになるが、そこでは公共的なものと詩的なものとが混ざり合い、そのゾーンの境界はもはや確定しがたい。
*この小論は、昨年11月13日のパリ襲撃事件と、その直後のオランド政権による緊急事態発令及びその2月末までの延長、そして2重国籍者の国籍剥奪のための法案準備を受けて、アガンベンが『ルモンド』紙(12月23日付)に寄港したものである。
**「緊急事態」は「非常事態」ともいうが、ドイツでは「例外状態」と呼ばれ、カール・シュミットの主要テーマだった。アガンベンは同題の1書を『ホモ・サケル』シリーズに書いている。
***「安全国家」と訳したのは"I'E'tar de se'curite'"。英語風に言えば「セキュリティー国家」。「セキュリティー」は「安全保障」とも訳されるし、「安全確保」といってもよい。もちろん「集団的安全保障」の「安全保障」。ここでは簡便を期して「安全国家」とした。
**「緊急事態」は「非常事態」ともいうが、ドイツでは「例外状態」と呼ばれ、カール・シュミットの主要テーマだった。アガンベンは同題の1書を『ホモ・サケル』シリーズに書いている。
***「安全国家」と訳したのは"I'E'tar de se'curite'"。英語風に言えば「セキュリティー国家」。「セキュリティー」は「安全保障」とも訳されるし、「安全確保」といってもよい。もちろん「集団的安全保障」の「安全保障」。ここでは簡便を期して「安全国家」とした。












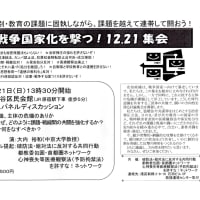





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます