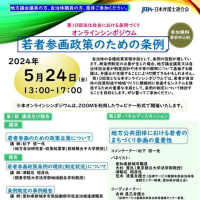ふるさと住民票という制度がある。
ふるさと住民票は、そのまちの出身者、ふるさと納税を行った人、複数地域で居住している人等に対し、ふるさと住民票を発行し、自治体広報、祭り・伝統行事の案内、公共施設の住民料金での利用、パブリックコメントへの参加等を提供するものである(日野町、三木町など)。
どの制度もそうであるが、住所を基準とする場合、どこか一つを住所と決めて、そこで行政サービス津を行う。地方自治では、民法の原則である、「生活の本拠」が住所であるという考え方に準拠して、選挙権などを決めている。その意味で、もともと便宜的なものである。
かつての農業を基本とする暮らしならば、その土地が暮らしの基本なので、住所は動かず、1個でよいが、今のようにサービス業が中心になると、様相が違ってくる。
うちのお兄ちゃんは、以前、キャノンの製品を売り込むために、ヤマダ電機やコジマ電機の店が新規開店になると、そこに乗り込んで、売り込む仕事をしていた。当時は、毎週のように新規開店していたから、毎週のように全国に行っていた。マイルが溜まって困ったといっていた。移動を全然、苦に市内しない様子は、「お父さんそっくり」と、連れ合いによく言われていた。
私も同じようなもので、大阪の大学に通っていたときは、月曜日の朝、新幹線で京都に行き、木曜日の午前中で授業が終わると、新幹線で三浦半島に帰ってきた。新幹線代だけで、JRにいくら貢献したのだろう。
そのうち、国勢調査があって、担当の方が、何度も、京都のマンションに来て、大変なご足労をかけたことは、もう書いたような気がする。
暮らしの基盤が変わったのに、地方自治制度は、昔のままである。地方自治法は昭和22年であるが、明治以来、連綿と続く仕組みである。人々の実態に合わせる仕組みを考えるのが域外住民政策で、地方自治制度を前提としつつ、実態を加味できるかがポイントである。
ふるさと住民票もその試みの一つである。
この制度の目的は、①自分の「ふるさと」だという気持ちと地域をつなぐ。②本来のふるさと納税の意義を高める。③複数地域居住者が、地域に溶け込みやすい環境づくりにあるとされている(続く)。
ふるさと住民票は、そのまちの出身者、ふるさと納税を行った人、複数地域で居住している人等に対し、ふるさと住民票を発行し、自治体広報、祭り・伝統行事の案内、公共施設の住民料金での利用、パブリックコメントへの参加等を提供するものである(日野町、三木町など)。
どの制度もそうであるが、住所を基準とする場合、どこか一つを住所と決めて、そこで行政サービス津を行う。地方自治では、民法の原則である、「生活の本拠」が住所であるという考え方に準拠して、選挙権などを決めている。その意味で、もともと便宜的なものである。
かつての農業を基本とする暮らしならば、その土地が暮らしの基本なので、住所は動かず、1個でよいが、今のようにサービス業が中心になると、様相が違ってくる。
うちのお兄ちゃんは、以前、キャノンの製品を売り込むために、ヤマダ電機やコジマ電機の店が新規開店になると、そこに乗り込んで、売り込む仕事をしていた。当時は、毎週のように新規開店していたから、毎週のように全国に行っていた。マイルが溜まって困ったといっていた。移動を全然、苦に市内しない様子は、「お父さんそっくり」と、連れ合いによく言われていた。
私も同じようなもので、大阪の大学に通っていたときは、月曜日の朝、新幹線で京都に行き、木曜日の午前中で授業が終わると、新幹線で三浦半島に帰ってきた。新幹線代だけで、JRにいくら貢献したのだろう。
そのうち、国勢調査があって、担当の方が、何度も、京都のマンションに来て、大変なご足労をかけたことは、もう書いたような気がする。
暮らしの基盤が変わったのに、地方自治制度は、昔のままである。地方自治法は昭和22年であるが、明治以来、連綿と続く仕組みである。人々の実態に合わせる仕組みを考えるのが域外住民政策で、地方自治制度を前提としつつ、実態を加味できるかがポイントである。
ふるさと住民票もその試みの一つである。
この制度の目的は、①自分の「ふるさと」だという気持ちと地域をつなぐ。②本来のふるさと納税の意義を高める。③複数地域居住者が、地域に溶け込みやすい環境づくりにあるとされている(続く)。