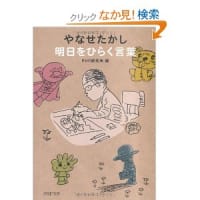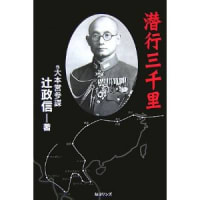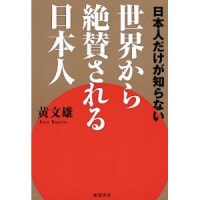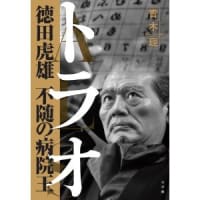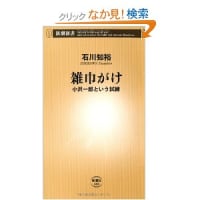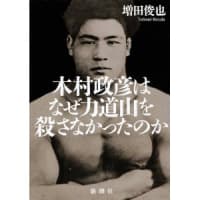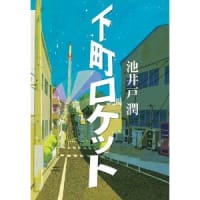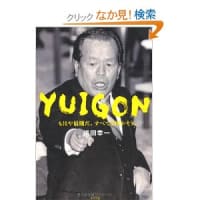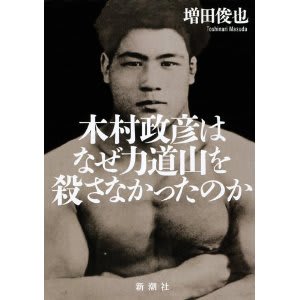
700頁の大作ですが、読み終えるのが惜しいくらい面白かった。
「昭和の巌流島」と言われた力道山との一戦に敗れた柔道家、木村雅彦の数奇な人生に迫った渾身の書。本書の中には、いくつかのテーマがある。
一つは、日本の柔道の歴史である。現在の日本の柔道は、講道館柔道とイコールである。しかし、柔道の源流は、武士が刀が折れても敵をねじ伏せる組討から発展した古流柔術にある。また、戦前、旧帝大を中心とした高専柔道の全盛期が寝技の発達をもたらした。しかし、戦後、GHQが武道を禁止したことで、講道館を中心にスポーツとしての柔道の発展がはかられ、現在の日本の柔道は一民間道場である講道館の独占状態になっている。そうした中で、古流柔術や高戦柔道の流れを汲む柔道家、木村雅彦の名は、戦前、13年連続日本一、天覧試合を制覇し、「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」と最強を謳われたにもかかわらず、柔道の正史からは消されているのである。さらに、昨今の総合格闘技ブームの中で注目を集めるグレーシー柔術に日本柔道が与えた影響やプロレス草創期の歴史、極真空手の大山総裁についての記述も興味深い。
柔道のスポーツ化は、時代の流れの中でしかたがないことだったのかもしれないが、本書に出てくる木村や師匠の牛島辰熊らの柔道家は、サムライである。この春から武道の必修化が始まるが、柔道の底流にある武士道精神について考えさせられた。
さらに、「歴史」とは、勝者によってつくられるものであることを痛感した。
二つ目のテーマは、敗者の生き方である。最強の柔道家と言われた木村が力道山に一方的につぶされたことで、転落していく。一方の力道山は、国民的英雄になるが、暴漢に刺されて、この世を去る。木村は、「負けたら腹を切る」という武道家としての矜持を持っていた。木村は、一時、力道山を殺して、切腹することも考えたと言われている。タイトルにあるように「なぜ、木村は力道山を殺さなかったのか」、なぜ、木村が簡単に負けたのか、本書は、その真相に鋭く迫っていく。力道山が殺された時、木村は「念力で自分が殺した」と言ったそうだ。木村がどんな思いを胸に抱いて、その後の人生を送ったのかを考えると胸をしめつけられる。
三つ目のテーマは、師弟関係。「鬼」の称号を持つ柔道家、牛島辰熊は、自らが制することができなかった天覧試合を勝つために、木村を見出し、全身全霊で自らの分身として木村を育て上げる。戦争という時代を経て、師弟関係に微妙な亀裂が入るが、その後もこの師弟の関係は生涯、特別なものだった。木村が同じように岩釣兼生という弟子を育てたことも因縁を感じる。
うまく、面白さを伝えられないのが悔しいが、絶対に面白いので、興味がある方は、ぜひ、読んでみてください。
「昭和の巌流島」と言われた力道山との一戦に敗れた柔道家、木村雅彦の数奇な人生に迫った渾身の書。本書の中には、いくつかのテーマがある。
一つは、日本の柔道の歴史である。現在の日本の柔道は、講道館柔道とイコールである。しかし、柔道の源流は、武士が刀が折れても敵をねじ伏せる組討から発展した古流柔術にある。また、戦前、旧帝大を中心とした高専柔道の全盛期が寝技の発達をもたらした。しかし、戦後、GHQが武道を禁止したことで、講道館を中心にスポーツとしての柔道の発展がはかられ、現在の日本の柔道は一民間道場である講道館の独占状態になっている。そうした中で、古流柔術や高戦柔道の流れを汲む柔道家、木村雅彦の名は、戦前、13年連続日本一、天覧試合を制覇し、「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」と最強を謳われたにもかかわらず、柔道の正史からは消されているのである。さらに、昨今の総合格闘技ブームの中で注目を集めるグレーシー柔術に日本柔道が与えた影響やプロレス草創期の歴史、極真空手の大山総裁についての記述も興味深い。
柔道のスポーツ化は、時代の流れの中でしかたがないことだったのかもしれないが、本書に出てくる木村や師匠の牛島辰熊らの柔道家は、サムライである。この春から武道の必修化が始まるが、柔道の底流にある武士道精神について考えさせられた。
さらに、「歴史」とは、勝者によってつくられるものであることを痛感した。
二つ目のテーマは、敗者の生き方である。最強の柔道家と言われた木村が力道山に一方的につぶされたことで、転落していく。一方の力道山は、国民的英雄になるが、暴漢に刺されて、この世を去る。木村は、「負けたら腹を切る」という武道家としての矜持を持っていた。木村は、一時、力道山を殺して、切腹することも考えたと言われている。タイトルにあるように「なぜ、木村は力道山を殺さなかったのか」、なぜ、木村が簡単に負けたのか、本書は、その真相に鋭く迫っていく。力道山が殺された時、木村は「念力で自分が殺した」と言ったそうだ。木村がどんな思いを胸に抱いて、その後の人生を送ったのかを考えると胸をしめつけられる。
三つ目のテーマは、師弟関係。「鬼」の称号を持つ柔道家、牛島辰熊は、自らが制することができなかった天覧試合を勝つために、木村を見出し、全身全霊で自らの分身として木村を育て上げる。戦争という時代を経て、師弟関係に微妙な亀裂が入るが、その後もこの師弟の関係は生涯、特別なものだった。木村が同じように岩釣兼生という弟子を育てたことも因縁を感じる。
うまく、面白さを伝えられないのが悔しいが、絶対に面白いので、興味がある方は、ぜひ、読んでみてください。