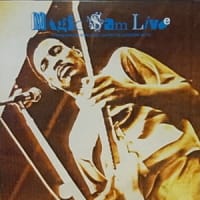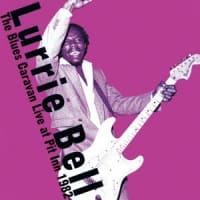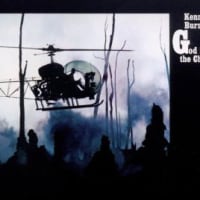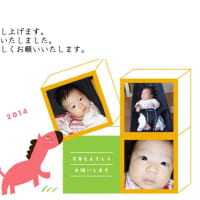前回紹介した記事のからみで今日はこれ、

『Pat Metheny Group/STILL LIFE (TALKING)』
(今、この記事を書いている最中に猫が家の廊下でゲロはいている音がする。
早く記事を書きあげて掃除をせねば…)
ところで、前回の記事では、このアルバムはメセニーの世界を180°変えた的な
発言をしたのだが、もちろんこのアルバムの以前からメセニーはメセニーであり、
彼のオリジナリティーは貫かれているわけで、ナシメントやらオーネット・コールマン
らとの邂逅の中で持続的に開花されていったものであることはいうまでもない。
そして、さらにいうならそういう状況においても、このアルバムはやはり衝撃的で
あった。パット・メセニーという人はデビューから常に己の世界を拓き続けている人
であり、それが彼が希代のミュージシャンとしての証明であろう。
彼のアルバムを俯瞰的に聴いてみるとギター・スタイルはある意味デビュー当時から
完成されていた感がある。
ただし、彼の方法論はどんどんつきつめられていったのがよくわかる。
そのひとつが「ターゲット理論」である。
端的にいうと、クロマティックに上行、下行をくりかえしながらターゲット音に
ラインが向かってゆくということなのだが、彼の場合はその「行き方」が精緻を極める
ものであり、言うは易し行うは難しである。
いうなれば、ヘタクソがやればヘタクソなりの、上手い人がやれば上手い人なりの
ラインどりが可能なわけだ。
まあ、彼のラインを分析したことがある人ならわかるけど、案外シンプルなんだよね。
だけど、TPOがすごいし、オリジナリティたっぷりなので、ちょっとでもそれをやろう
ものなら、出典がメセニーであることがバレバレである。
ああいった彼独自のラインを生み出すにいたった過程がすごいということなのだろう。
彼のインタビューを読むと、
・コード・トーン
・パッシング・ノート
を徹底的に訓練し、その後アプローチ・ノート(クロマティシズムを含む)
を研究したらしい。その過程で彼は普通の人がやらないような「不協和音」を
そこに盛り込んで行ったようだ。
彼のラインを聴くと、ダイアトニシズムをかなり逸脱していっているのが
わかるだろう。
上記の練習はギタリストなら多少はかじったことがあるはず。
ただし、それほど基本的な練習をそこまで徹底的にやっている人って少ない
気がする。
得てしてある程度弾けるようになるとギタリストはフレーズ主義に走るもの
だからである。特に日本のギタリストはその傾向が強い気がする。
もちろん「仕込み」のまったくないミュージシャンは絶対にいないのであるが、
それだけだといつまでたっても「どっかで聴いたような」感が抜けないでしょ。
まあ、その辺はさすがジム・ホールの愛弟子である。
私見では、パット・メセニーの「ターゲット理論」はジム・ホールの「モチーフ理論」
の範疇に入っていると思う。
いくらきれいなフレーズを数多く編み出したところで、なかなかオリジナリティには
いたらないのだなあ、と反省することしきりの今日この頃である(笑)。
がんばろう、東日本!!
翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト

『Pat Metheny Group/STILL LIFE (TALKING)』
(今、この記事を書いている最中に猫が家の廊下でゲロはいている音がする。
早く記事を書きあげて掃除をせねば…)
ところで、前回の記事では、このアルバムはメセニーの世界を180°変えた的な
発言をしたのだが、もちろんこのアルバムの以前からメセニーはメセニーであり、
彼のオリジナリティーは貫かれているわけで、ナシメントやらオーネット・コールマン
らとの邂逅の中で持続的に開花されていったものであることはいうまでもない。
そして、さらにいうならそういう状況においても、このアルバムはやはり衝撃的で
あった。パット・メセニーという人はデビューから常に己の世界を拓き続けている人
であり、それが彼が希代のミュージシャンとしての証明であろう。
彼のアルバムを俯瞰的に聴いてみるとギター・スタイルはある意味デビュー当時から
完成されていた感がある。
ただし、彼の方法論はどんどんつきつめられていったのがよくわかる。
そのひとつが「ターゲット理論」である。
端的にいうと、クロマティックに上行、下行をくりかえしながらターゲット音に
ラインが向かってゆくということなのだが、彼の場合はその「行き方」が精緻を極める
ものであり、言うは易し行うは難しである。
いうなれば、ヘタクソがやればヘタクソなりの、上手い人がやれば上手い人なりの
ラインどりが可能なわけだ。
まあ、彼のラインを分析したことがある人ならわかるけど、案外シンプルなんだよね。
だけど、TPOがすごいし、オリジナリティたっぷりなので、ちょっとでもそれをやろう
ものなら、出典がメセニーであることがバレバレである。
ああいった彼独自のラインを生み出すにいたった過程がすごいということなのだろう。
彼のインタビューを読むと、
・コード・トーン
・パッシング・ノート
を徹底的に訓練し、その後アプローチ・ノート(クロマティシズムを含む)
を研究したらしい。その過程で彼は普通の人がやらないような「不協和音」を
そこに盛り込んで行ったようだ。
彼のラインを聴くと、ダイアトニシズムをかなり逸脱していっているのが
わかるだろう。
上記の練習はギタリストなら多少はかじったことがあるはず。
ただし、それほど基本的な練習をそこまで徹底的にやっている人って少ない
気がする。
得てしてある程度弾けるようになるとギタリストはフレーズ主義に走るもの
だからである。特に日本のギタリストはその傾向が強い気がする。
もちろん「仕込み」のまったくないミュージシャンは絶対にいないのであるが、
それだけだといつまでたっても「どっかで聴いたような」感が抜けないでしょ。
まあ、その辺はさすがジム・ホールの愛弟子である。
私見では、パット・メセニーの「ターゲット理論」はジム・ホールの「モチーフ理論」
の範疇に入っていると思う。
いくらきれいなフレーズを数多く編み出したところで、なかなかオリジナリティには
いたらないのだなあ、と反省することしきりの今日この頃である(笑)。
がんばろう、東日本!!
翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト