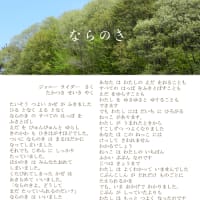私は仙台に行くまで、甲子園の高校野球で東北地方の学校が優勝したことがないことを知らなかった。大学に入学した昭和四十四年(一九六九年)の夏、私はラグビー部に入って初めての合宿に行ったが、移動中のバスの中で太田幸司投手の三沢高校が決勝戦をたたかうようすがラジオで実況されていた。部員には東北地方の出身者が多かったから、バスの中は騒然としていた。延長戦となり、満塁サヨナラのチャンスが二度もあった。先輩が「とうとう優勝旗が白河の関を越える」と大声で言ったとき、「え?一度も優勝していないのか」と驚くとともに、「白河の関を越える」という表現に違和感をおぼえた。そのことの意味は仙台に暮らすようになり、しばらくしてわかるようになった。
甲子園のことを続ければ、二〇〇四年には駒大苫小牧高校が優勝し、優勝旗は白河の関どころか津軽海峡を越えたのだが、そのことは東北人にさらに複雑な思いを抱かせることになった。
甲子園に象徴される「東北地方のもつビハインド感」、このことは仙台に住むまで気づくことができなかった。それは方言にも投影されている。ラジオやテレビで関西弁は聞かれたが、ほかの地方の方言は聞くことがなかった。ある時代からドラマなどでも方言であるほうがリアリティがあるということで使われるようになったが、多くは九州や中国地方の方言で、東北弁はわかりにくいことばの代表のような位置づけであるように思う。同じわかりにくさでも沖縄の言葉の場合とは受け取り方が違わないだろうか。東北弁はわかりにくい、汚いとされ、上京した東北出身者が肩身の狭い思いをするのはいまだに続いている。文化の多様さを評価するといいながら、このことについては明らかに公平でない空気がある。
ところで、私は自分が東京にすむことになるとは思ってもいなかった。山陰で生まれ、東北地方で大人になったから、東京に来ると疲労感があった。ところが人生はわからないもので、その東京に暮らすことになった。初めは違和感がずっとあったが、家族が定着するなかで時間とともに生活がなりたってきたという感覚をもてるようになってきた。そして東北地方がなつかしいという感覚でとらえる場所になってきた。そうしたときに東日本大震災が起きたのである。
そのときの東京人が何をしたか。物資の買いだめでガソリンスタンドにガソリンがなくなり、コンビニやスーパーからは品物が消えた。口で震災を憂いながら行動は利己的であった。私は東京の住民であることにいたたまれないような気持ちになった。もし、私が仙台に住んでいなければこういう気持ちは持たなかったかもしれない。
そのときに思ったのは、関東と東北のもつ構造上の不公平さということであった。日本政府は被爆国として最初は控えめに原発は安全だというキャンペーンをしながら、いつのまにか日本中に原発を建設してしまった。安全であれば地方に建設する必要はないというのは小学生でも考えることである。地方に建設するということ自体が原発が危険であることの証しなのである。ではなぜ危険である原発を地方が受け入れたか。私は漠然と人口密度が低いから一次産業以外の産業がなく、原発による雇用や保証などで経済的な恩恵があるからだと思っていた。概ねそれで正しいようだが、実際には昭和の三十年代から続く「金の卵」獲得のために強引な若い世代の引き抜きがおこなわれ、社会を担うべき世代が空白になるという状況が醸成されていたために、原発誘致以外の選択肢を奪うという形での構造的枠組みができていた結果なのだという。そのことが政治的意図をもって先見的におこなわれていたかどうかはわからない。単純に若い労働力が必要であり、東北の農家もそのことを希望したということはあるだろう。しかしそうすれば農村社会を維持できなくなることは予測できたはずであり、そのことのもつ深刻な意味を考えれば、責任ある社会が選択すべきことであったとは思えない。これは社会のリーダーがなすべきことがなされなかったこととして責任を問われることだと思う。
こうしたことは近代化を進めた明治時代から継続的におこなわれてきたことである。東北は農業地帯であり、都市に食料を提供した。戦時には兵隊を供給した。そういう実質的なところでの近代化に果たした東北地方の社会貢献ははなはだ大きい。にもかかわらず、それらは東北地方が当然すべきことのようにみなされたばかりか、つねに遅れた地方と見下されて来た。東北にはそのような鬱屈した気持ちがただよっている。
岩手県は人材を産む県であるが、そうした人材の代表である原敬は自分の号を「一山」とした。これは明治政府の権力を独占した薩長土肥の政治家が「白河以北一山百文」と蔑視したことに対するプロテストであるとされる。先の甲子園の「白河の関」もこのこととつながる。
そうした意味で、私は原発事故を、地理的ではなく、社会的な東京対東北という構造からとらえなければならないと思う。この百年あまり、東北地方はずっと東京に貢献してきた。あるいはさせられてきたというほうがふさわしいだろう。その結果、労働人口を奪われ、原発誘致を無理やり呑まされてきた。地震は天災である。だが上記の意味で、原発は人災である。食料にしても、エネルギーにしても、本来使う者が産み出すべきであろう。そのことを日本という国が怠り、国内では東京が怠ってきた。それどころか、消費することが豊かであるとし、供給する側に危険を押し付けさえした。これはどう詭弁を弄して正当化しようとも不公平である。
当時の首相菅直人が東京電力を強く叱責し、言動が強引であったという批判がある。さまざまな事情があったにせよ、私は国の責任者として立派な行動であったと思うが、しかしそれは「東京を守る」ためであったといえないだろうか。被害の当事者は東北の人だったのだ。
世界有数の豊かな国であるこの国が二年近くたっても被災地の復旧ができないでいる。あれほどさわいでいたマスコミも、震災のことはとりあげなくなり、東北地方以外の日本はもとどおり安穏(あんのん)とした日常にもどったかのごときである。
いつも「後進地域」とされ、いやなことを押し付けられ、それらを耐えることに慣れてしまったかのような東北地方が、心の中では恐れながら、これまでなかったのだからきっとないだろうと思っていた大震災にあい、ついに原発事故が起きてしまった。多くの犠牲者が出て、避難を余儀なくされ、先祖代々の土地を捨て、親しかった知人と離ればなれになった。自分の一生のうちに故郷に戻れないと感じている人がたくさんいる。「こんな老後を迎えるために生きて来たのではない」という思いを抱えながら泣いている人がたくさんいる。東京電力と原発建設を進めて来た日本政府の罪は計り知れないが、その背景には関東と東北の歴史的な関係があったのだと思う。