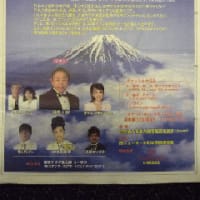ジェイコブズ・ピロー・ダンス・フェスティバルから招聘されて参加した室伏鴻とKo&Edgeメンバー。写真左はフェスティバルで開催されるコミュニティ向けアウトドアイベント“In & Out"での様子。客席から登場した銀塗りの舞踏ダンサーたちにお驚く観客。写真右は公演が行われたDoris Duke Theaterの楽屋口で、現地テクニカルスタッフと。(撮影:筆者)
海外で公演する方法は大きく2種類に別けられると思います。1つは自主事業としての海外公演、もう1つは招聘事業としての海外公演です。
自主事業とは、つまり大阪の劇団が手打ちで東京の劇場をレンタルして公演するのと基本的には同じです。劇場を借りて、自分たちで(あるいは専門家のサポートを受けて)宣伝活動も行い公演を実施する。あくまで、劇場をレンタルする費用も移動や宿泊も自己資金で負担しなくてはなりません。チケット代は自分たちのものですが、どこからも出演料は支払ってもらえません。
次に招聘事業とは、地方の劇場などに作品が買われて上演に赴くのと基本的には同じです。主催者は地方の劇場ですから、会場となる劇場も、受付や仕込の人員、そして集客も基本的には主催者である会館の負担で行われます。さらに移動や輸送、宿泊などの費用も基本的には負担されます。上演料も出たりします。
自主事業については、また改めて書くとして・・・
恐らくどのカンパニーも招聘で海外公演を行いたいと考えると思いますが、これはそんなに簡単なことではありません。例えばアメリカの場合、日本の演劇やダンスを専門的に1年を通して紹介している劇場・団体はNYのジャパン・ソサエティしかありません。(LAにJACCCという団体がありますが、招聘事業は近年あまり活発ではありません)そのジャパン・ソサエティですら、日本からダンスや劇団を招聘するのは、それぞれ年に1団体あるかないかです。リンカーンセンターやBAMなども日本の劇団などを招聘したりしますが、まあ年に1本。しかも規模が大きいので、招聘されるカンパニーもある程度、規模が大きくすでに評価を得ているものが中心になります。地方でもダートマス大学のホプキンスセンター、ミネアポリスのウォーカーアートセンター、オハイオのウェクスナーセンター、などなど、日本からの招聘経験のある劇場は多数ありますが、2、3年に1本といったペースではないでしょうか。
さらにアメリカの場合、日本からの渡航費も宿泊費も全部経費を負担した上で、公演料まで出してくれる劇場はそれほど多くありません。多くの場合、渡航費などはカンパニー側が日本で助成金などを獲得することを期待されることが多いです。あるいはとにかく経費であれ、上演料であれ、劇場が出せるのは幾らまで、といった条件の招聘もあります。しかし、アメリカでそれなりの地位にある劇場から招聘を受ければ、やはりなんらかの助成を取れる可能性はかなり高くなるようですが・・・。
では、どうすれば招聘されるのか。答えが分かっていれば苦労しませんが、資料を郵送で劇場に送付するだけで、劇場のプログラミング・ディレクターの目に留まる、ということはまずありません。恐らくちらっと目をやって棚に置かれてそのままというのがほとんどでしょう。単に郵送して目に留まるくらいなら、プロであるプログラミング・ディレクターはすでにそのカンパニーの評判をどこかで聞いているということです。逆に言うと、日本国内で話題になっていないカンパニーや劇団が資料を単に郵送で送りつけても、招聘がかなうことはまずない、ということです。
では、海外のプログラミング・ディレクターの目に留まるにはどうすれば良いのか。これも正解というものがない代わり、方法も1つではないと思います。模範解答は「海外のプログラム・ディレクターが招聘したくなるような作品を作って発表する。そして日本での活動を充実させ業界で話題となるようなカンパニーになる」です。そのまんまです。しかしそれでは身もふたもないので、制作的にできることがないか、ちょっと考えてみますと・・・
制作やアーティストが直接資料を持って海外の劇場のディレクターを訪問する、日本を訪れている海外のプログラム・ディレクターになんとかして作品を見に来てもらう、海外の劇場とコネのある制作者に作品を売り込んでもらう、海外のブッキング・エージェントを雇う、とにかく興味を持ってくれそうな資料を作成して根気良く送り続ける、ユーチューブやウェブ上での情報を充実させて手間を相手に掛けさせずに作品やカンパニーを知ってもらう、とにかく自主でもなんでも公演して現地のプレゼンターたちに公演を見てもらう。
あ、それから口コミですね。これが意外と有力だったりします。海外からプレゼンターが日本に作品を見に来たとき、あるいは日本の舞台芸術の専門家が海外に来たとき、日本ではどの作品を見るべきか、最近注目のカンパニーはどんなところがあるのか、必ずそういう話をします。ここで話題に上れば、とりあえず関心は持ってもらえるし、上手く行けば舞台を見に来たりします。
(他にあるでしょうか?アイデアのある方は提供していただけると嬉しいです。)
ここで、ちょっと考えたいのが、「なぜ海外で公演をするのか」です。実は、これが一番大事な質問です。海外に招聘されるカンパニーの中にも、「公演する場所が東京からNYに変わっただけ」ということがままあります。もちろん、招聘の目的は「現地の人たちに新しい、素晴らしい舞台芸術を見てもらう」ということですから、それだけでもメリットはあります。
でも海外に来て、現地のアーティストや関係者、観客、そしてその他街の人々と交わることなく、劇場とホテルを往復するだけでは、あまりにもったいない。公演をする、ということ以上に公演をすることで何を得るのか。このことは書いている以上に難しい命題ですが、ここを考えないと「ただやっただけ」ということにならないでしょうか。
そう考えると、招聘されたり委嘱されたりというのが1つの到達点としても、そこまでの道のりは様々あるのではないかと思います。FringeNYCのようなフェスティバルに参加して、現地のアーティストと交流し、様々な世界の舞台作品を見て、彼らの考えていることを聞く。その交流の先として、現地のアーティストと作品を作るというような機会が作れれば、違った広がりが持てるのではないでしょうか。