
みなさん、こんにちは
今日から3日間に渡って、
9/30なんでや劇場「生物史から学ぶ自然の摂理③ 有性生殖への道のり」
のレポートをお届けします。驚き の連続がたくさん詰まっていますので、お楽しみ下さい
の連続がたくさん詰まっていますので、お楽しみ下さい
興味を持っていただけたみなさん、今日もポチット×2、よろしくお願いします。


それでは早速本文に入っていきましょう。
レポート①『真核単細胞生物に進化したのはなんで?』
のサブテーマでお届けします。ますは原核細胞と真核細胞の構成の違いをおさえるところから、その進化の過程に迫っていきましょう!
①原核細胞と真核細胞の違い(特徴)
■原核細胞(約35億年前に誕生)

(基礎的な生物学用語の「なんでや的」解説-2より引用)
・大きさ:直径約10μm
・種類:バクテリア(大腸菌、乳酸菌、コレラ菌、シアノバクテリアなど)
・膜の構成:一重膜(細胞膜のみ)=染色体があるだけ(小器官はない)
☆地球上にある分子が寄り集まって、組織的に動ける状態
■真核細胞(約19億年前に誕生)

(基礎的な生物学用語の「なんでや的」解説-2より引用)
・大きさ:直径約100μm ※原核細胞の直径10倍、体積にすると1000倍
・種類:ゾウリムシ、ミドリムシ、アメーバ、粘菌、珪藻など
・膜の構成:二重膜(細胞膜+核膜)=小器官がある
☆組織が結びついて、更に上位の『統合』がされた状態
『統合』・・・各々の小器官の情報伝達、エネルギー伝達があり、それらを核が司令塔となって全体をまとめている。
というように、大きく特徴は分類できます。体積だけ見ても、真核細胞は原核細胞の1000倍 になっていてその進化の過程には劇的なドラマがあったに違いありません。次は、その16億年間の進化過程に迫っていきましょう!
になっていてその進化の過程には劇的なドラマがあったに違いありません。次は、その16億年間の進化過程に迫っていきましょう!
②原核生物→真核単細胞生物に進化したのはなんで?
1.約100回に及ぶ絶滅の危機=『逆境』
約35億年前の生物は、窒素・硫黄を主なエネルギー源としていて、酸素や光はとても有害なものでした。
しかし、酸素呼吸をする酸素生物「好気性細菌」や、光合成をして酸素を出す光合成生物「シアノバクテリア」といった原核生物の登場により、地球上には酸素が大量に増加していきました。
有害な酸素の増加で絶滅の危機に瀕した種の生物たちは、この逆境に対してどう適応したのでしょうか?
⇒2.『可能性収束』(各種原核生物との共生) 酸素生物、光合成生物等の取り込み
酸素の増加という逆境に対して、追い込まれた生物たちは適応するためにある賭けにでます。なんと、有害である酸素生物や光合成生物を飲食作用によって取り込み、共生を試みたのです!!生物は外圧に適応するためには、なんでもするんです。 こうして、光合成生物を取り込んで「葉緑体」を形成し、酸素を生成する。そして酸素呼吸で20倍のエネルギーを生み出せる酸素生物を取り込んで「ミトコンドリア」を形成し、大型化に必要なエネルギー生成の効率化を図ったのです。
こうして、光合成生物を取り込んで「葉緑体」を形成し、酸素を生成する。そして酸素呼吸で20倍のエネルギーを生み出せる酸素生物を取り込んで「ミトコンドリア」を形成し、大型化に必要なエネルギー生成の効率化を図ったのです。
⇒3.『分化と統合』(組織化) ※情報伝達機能が高まる⇒司令塔としての核
このように、逆境に適応するために細胞内に必要な小器官を、 「膜機能を使って形成しながら機能分化」すると同時に、それらの情報やエネルギーの伝達機能を高めることで「統合」をはかったんです。そして、その役割を担う『核膜』が形成されていったんですね。
=真核単細胞生物の完成!
こうして約16億年の進化の過程をたどっていくと、
原核生物誕生 『逆境』⇒『可能性収束』⇒『機能分化と統合』 真核単細胞生物誕生
という大きな流れがあり、真核単細胞生物の最大のポイントが
膜機能を利用した『機能分化』と、それを統合するための『核膜形成』にあったということが見えてきます。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました
明日は、引き続きレポート②をお届けしますので、楽しみにしていて下さい
by よっし~
□参考投稿
原核生物から真核生物への進化過程(るいネット)

今日から3日間に渡って、
9/30なんでや劇場「生物史から学ぶ自然の摂理③ 有性生殖への道のり」
のレポートをお届けします。驚き
 の連続がたくさん詰まっていますので、お楽しみ下さい
の連続がたくさん詰まっていますので、お楽しみ下さい興味を持っていただけたみなさん、今日もポチット×2、よろしくお願いします。

それでは早速本文に入っていきましょう。
レポート①『真核単細胞生物に進化したのはなんで?』
のサブテーマでお届けします。ますは原核細胞と真核細胞の構成の違いをおさえるところから、その進化の過程に迫っていきましょう!
①原核細胞と真核細胞の違い(特徴)
■原核細胞(約35億年前に誕生)

(基礎的な生物学用語の「なんでや的」解説-2より引用)
・大きさ:直径約10μm
・種類:バクテリア(大腸菌、乳酸菌、コレラ菌、シアノバクテリアなど)
・膜の構成:一重膜(細胞膜のみ)=染色体があるだけ(小器官はない)
☆地球上にある分子が寄り集まって、組織的に動ける状態
■真核細胞(約19億年前に誕生)

(基礎的な生物学用語の「なんでや的」解説-2より引用)
・大きさ:直径約100μm ※原核細胞の直径10倍、体積にすると1000倍
・種類:ゾウリムシ、ミドリムシ、アメーバ、粘菌、珪藻など
・膜の構成:二重膜(細胞膜+核膜)=小器官がある
☆組織が結びついて、更に上位の『統合』がされた状態
『統合』・・・各々の小器官の情報伝達、エネルギー伝達があり、それらを核が司令塔となって全体をまとめている。
というように、大きく特徴は分類できます。体積だけ見ても、真核細胞は原核細胞の1000倍
 になっていてその進化の過程には劇的なドラマがあったに違いありません。次は、その16億年間の進化過程に迫っていきましょう!
になっていてその進化の過程には劇的なドラマがあったに違いありません。次は、その16億年間の進化過程に迫っていきましょう!②原核生物→真核単細胞生物に進化したのはなんで?
1.約100回に及ぶ絶滅の危機=『逆境』
約35億年前の生物は、窒素・硫黄を主なエネルギー源としていて、酸素や光はとても有害なものでした。
しかし、酸素呼吸をする酸素生物「好気性細菌」や、光合成をして酸素を出す光合成生物「シアノバクテリア」といった原核生物の登場により、地球上には酸素が大量に増加していきました。
有害な酸素の増加で絶滅の危機に瀕した種の生物たちは、この逆境に対してどう適応したのでしょうか?
⇒2.『可能性収束』(各種原核生物との共生) 酸素生物、光合成生物等の取り込み
酸素の増加という逆境に対して、追い込まれた生物たちは適応するためにある賭けにでます。なんと、有害である酸素生物や光合成生物を飲食作用によって取り込み、共生を試みたのです!!生物は外圧に適応するためには、なんでもするんです。
 こうして、光合成生物を取り込んで「葉緑体」を形成し、酸素を生成する。そして酸素呼吸で20倍のエネルギーを生み出せる酸素生物を取り込んで「ミトコンドリア」を形成し、大型化に必要なエネルギー生成の効率化を図ったのです。
こうして、光合成生物を取り込んで「葉緑体」を形成し、酸素を生成する。そして酸素呼吸で20倍のエネルギーを生み出せる酸素生物を取り込んで「ミトコンドリア」を形成し、大型化に必要なエネルギー生成の効率化を図ったのです。⇒3.『分化と統合』(組織化) ※情報伝達機能が高まる⇒司令塔としての核
このように、逆境に適応するために細胞内に必要な小器官を、 「膜機能を使って形成しながら機能分化」すると同時に、それらの情報やエネルギーの伝達機能を高めることで「統合」をはかったんです。そして、その役割を担う『核膜』が形成されていったんですね。
=真核単細胞生物の完成!
こうして約16億年の進化の過程をたどっていくと、
原核生物誕生 『逆境』⇒『可能性収束』⇒『機能分化と統合』 真核単細胞生物誕生
という大きな流れがあり、真核単細胞生物の最大のポイントが
膜機能を利用した『機能分化』と、それを統合するための『核膜形成』にあったということが見えてきます。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました

明日は、引き続きレポート②をお届けしますので、楽しみにしていて下さい

by よっし~

□参考投稿
原核生物から真核生物への進化過程(るいネット)












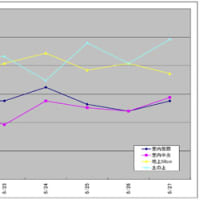
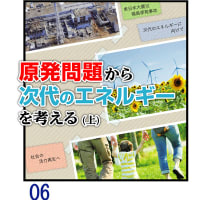




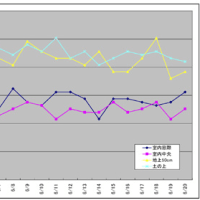
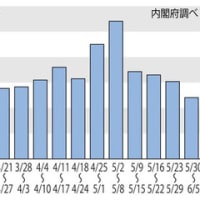
細胞の顕微鏡写真を見るとミトコンドリアとか葉緑体は、確かに2重の膜になってました
もとの嫌気性原核生物は、自らの膜を伸ばし、ミトコンドリア等を包み込むような感じで取り込んだんでしょうね。
やはり、逆境があることが実は進化の条件だったりして
生物史ってこうしてみると面白いですねー
のとこですが、ちょっと違和感あり。
太陽光⇒光合成生物の誕生・繁栄→酸素大量発生⇒好気性細菌の誕生・繁栄
なんじゃないですかね?
で、だんだん「生きる場所=酸素や太陽光が無い場所」がなくなってきた嫌気性細菌が、やむにやまれず光合成生物や好気性細菌を取り込んでいったんじゃないかと。
>酸素=毒を取り込んで適応したってのがすごいですねー(さーねさん)
『進化』はいつも、あらゆる可能性に向って命がけなんですね
>ちょっと違和感あり。
太陽光⇒光合成生物の誕生・繁栄→酸素大量発生⇒好気性細菌の誕生・繁栄
なんじゃないですかね?(オオモリ。さん)
ご指摘、ありがとうございます
確かに流れを細かく追っていくと、おっしゃるとおりですね
整理されました