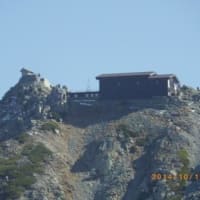昨日の集中豪雨とその被害の投稿で、東海「集いの会」創設20周年の続編が、大きく飛んでしまいました。記憶が確かの内に投稿・・・・・
舞台は、「ローズコートホテル」3階。勤行の後は記念式典。功労者表彰等があり、日頃お世話になっている名古屋別院さんに、感謝状と記念品の贈呈。記念品は、液晶テレビ?とか。自坊の本堂にも是非とも欲しい一品なのですが・・・・
写真 世話役の中西さんより、目録を名古屋別院輪番(東海教区教務所長)の三明浄信先生に。

その後は、楽しいレセプション。写真は、ビンゴゲームにて、リーチの皆さん。不思議なもので、リーチまではすぐにいくのですが、それからが大変。結局、前に並んだだけの人も。その後、「リーチ、一発ツモ」で私が「華葩(けは)の額(がく)」を頂くことに。

記念祝賀会の最後に、全員で中央仏教学院の校歌である「馮翊(ふよく)学園の歌」を合唱。役員さんと前学院長の北畠先生がひな壇に。

よく見ていただきたいのです。ただ一人、歌詞を持たずに歌っておられる方がおられます。そうです。北畠先生です。(左から二人目)
証明の拡大写真が下の写真

記念講演のなかで、先生は「私は、中央仏教学院のご縁により育てられました」とお話でした。中央仏教学院は、人材の育成と教学の発展のために91年前に設立。なかでも、布教伝道は宗門の生命です。その為の人材育成機関とも申せましょう。布教伝道の中心は法話。昔は、説法(せっぽう)という表現もありました。
説法に二種類あり。一つは、口業(くごう)説法。二つには、身業(しんごう)説法。
口業説法は、通常の口で行う法話。身業説法は、体で行う法話。難しいのは、身業説法。その人なり説法する。これが身業説法。これが難しい。でも、本質的には宗教とは、人から人へ伝わるもの。端的な例が、親鸞聖人を稲田草庵にて襲った山伏弁円(べんねん)の物語。弁円は、親鸞聖人から真宗の教えを聞かされて、親鸞聖人に帰依(きえ)し、明法房となった訳ではありません。襲う筈の親鸞聖人を見て、後悔の涙を流したとあります。(浄土真宗聖典註釈版1055頁)これが、身業説法なのです。私は、歌詞無しで歌われる北畠先生のお姿を拝見し、そのような事を思いました。
それにしても、素晴らしい20周年を企画実施された皆さんに感謝申し上げます。ご招待いただき本当に有難うございました。
舞台は、「ローズコートホテル」3階。勤行の後は記念式典。功労者表彰等があり、日頃お世話になっている名古屋別院さんに、感謝状と記念品の贈呈。記念品は、液晶テレビ?とか。自坊の本堂にも是非とも欲しい一品なのですが・・・・
写真 世話役の中西さんより、目録を名古屋別院輪番(東海教区教務所長)の三明浄信先生に。

その後は、楽しいレセプション。写真は、ビンゴゲームにて、リーチの皆さん。不思議なもので、リーチまではすぐにいくのですが、それからが大変。結局、前に並んだだけの人も。その後、「リーチ、一発ツモ」で私が「華葩(けは)の額(がく)」を頂くことに。

記念祝賀会の最後に、全員で中央仏教学院の校歌である「馮翊(ふよく)学園の歌」を合唱。役員さんと前学院長の北畠先生がひな壇に。

よく見ていただきたいのです。ただ一人、歌詞を持たずに歌っておられる方がおられます。そうです。北畠先生です。(左から二人目)
証明の拡大写真が下の写真

記念講演のなかで、先生は「私は、中央仏教学院のご縁により育てられました」とお話でした。中央仏教学院は、人材の育成と教学の発展のために91年前に設立。なかでも、布教伝道は宗門の生命です。その為の人材育成機関とも申せましょう。布教伝道の中心は法話。昔は、説法(せっぽう)という表現もありました。
説法に二種類あり。一つは、口業(くごう)説法。二つには、身業(しんごう)説法。
口業説法は、通常の口で行う法話。身業説法は、体で行う法話。難しいのは、身業説法。その人なり説法する。これが身業説法。これが難しい。でも、本質的には宗教とは、人から人へ伝わるもの。端的な例が、親鸞聖人を稲田草庵にて襲った山伏弁円(べんねん)の物語。弁円は、親鸞聖人から真宗の教えを聞かされて、親鸞聖人に帰依(きえ)し、明法房となった訳ではありません。襲う筈の親鸞聖人を見て、後悔の涙を流したとあります。(浄土真宗聖典註釈版1055頁)これが、身業説法なのです。私は、歌詞無しで歌われる北畠先生のお姿を拝見し、そのような事を思いました。
それにしても、素晴らしい20周年を企画実施された皆さんに感謝申し上げます。ご招待いただき本当に有難うございました。