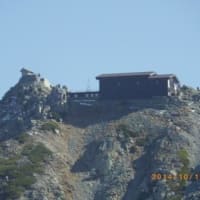前回の繰り返しになりますが、関東時代から書き始められた『教行信証』を別にすれば、前回に紹介したように兄弟子の本を見写し、門弟(もんてい)等に送られて念仏の法門を指導されていたようです。
法然上人門下の兄弟子・聖覚(せいかく)著『唯信抄(ゆいしんしょう)』は、58歳で見写(聖人の関東布教時代)。同じく法然聖人門下の兄弟子・隆寛(りゅうかん)著『自力・他力分別事(じりき・たりきふんべつごと)』を、親鸞聖人74歳で(京都帰洛後)写されています。老年期になってからです。
ただ、注意しなければならない事は、現在確認できる本に基づいた年齢であるという事です。つまり、聖人が写された本、又は著作にしても多くは失われてしまって現在まで伝えられはいないのではと思うのです。教化するのは、テキストがいります。いかに頭脳明晰な聖人といえども、テキスト無しでは到底無理の筈です。まして、60歳以降は聖人は京都、門弟は関東です。『唯信抄』にしても、関東門弟のテキストとして使われた筈なのです。勿論、鎌倉時代ですから文字を読み書ける人間はごく限られていました。しかし、親鸞聖人の有力な門弟は文字の読み書きができたようです。当時の知識階級なのです。そうであるが故に、より一層に知識欲に飢えるものなのです。本が溢れた現代とは根本的に違うのです。ご本山に上山しますと、ブックセンターには、聖人関係の本が山積みされています。時々に、ご本山にて本を購入いたしますが、そのせっかくの本も積読(つんどく)状態です。とても読み込みまではいきません。これが私の実情です。勝手に言わせていただければ、多くの僧侶も皆同じ状態では思うのですが・・・・お叱りをうけるかもしれません。
昭和56年の『本願寺年表』(浄土真宗本願寺派刊行)では、聖人が書き写された『唯信抄』でさえ、58歳を最初としますと、63歳、69歳、74歳に書かれた本が確認できるのみです。贈られた本を忠実に写して、まわし読みするのが当時鉄則。極めて本が貴重な時代、印刷・蔵版等は無い時代なのです。ですから、聖人の原本を書き写したので、これ以上は必要ないという意見もありますが、余りにも少ないと思うのです。
写真・・寛喜2年(1230年)5月25日奥書を持つ信証本(重文)高田専修寺蔵

上記の奥書(右)には、原本は承久(じょうきゅう)3年(1221年)9月14日、安居(あぐり)院法印(ほういん)聖覚(せいかく)作と書かれており、(左)には寛喜(かいき)2年(1230年)6月25日、その聖覚真筆(しんぴつ)の原本によって愚禿(ぐとく)釈の親鸞がこれを書き写したとあります。(聖人58歳)
聖人は、これらの『唯信抄』等を数多く書き写し関東の門弟に送られた筈なのです。それを物語る資料があります。親鸞聖人が、関東の門弟に送られたお手紙です。『ご消息』と呼びます。その『ご消息集』第8通(浄真宗聖典註釈版752頁)には、「たいていの人々は、『唯信抄』・『自力他力の文』・『後世(ごせ)物語の聞書』・『一念多念の証文』・『唯信抄文意』・『一念多念文意』、これらをご覧になりながら、慈信(関東に、聖人の名代として使われた聖人の長男である善鸞の事。善鸞事件として名高い)が説く法門にしたがって、大勢の念仏者達が弥陀の本願を捨ててしまったのです。(現代訳)」とあり、関東の門弟に京都から聖人が上記の書物を盛んに送られていたことがわかります。又、同一の『ご消息』第8通(浄真宗聖典註釈版751頁)には、もっと直接的に「慈信がごとき者の言うことをまにうけて、常陸・下野の念仏者たちの心がすべて浮ついてしまい、間違いのない証文を力をこめて数多く書き送りましたのに、それらをこぞって捨ててしまわれたとお聞きしたからには、もはや言うべき言葉もありません(現代訳)」と書かれています。証文を数多く書き送りましたとあります。ですから、現在存在する『唯信抄』だけではなく、数多く存在したのです。しかし、失われてしまったのです。残念でなりません。あれば、聖人の真筆ゆえに全て重文級の文書なのです。
続く・・・・・
法然上人門下の兄弟子・聖覚(せいかく)著『唯信抄(ゆいしんしょう)』は、58歳で見写(聖人の関東布教時代)。同じく法然聖人門下の兄弟子・隆寛(りゅうかん)著『自力・他力分別事(じりき・たりきふんべつごと)』を、親鸞聖人74歳で(京都帰洛後)写されています。老年期になってからです。
ただ、注意しなければならない事は、現在確認できる本に基づいた年齢であるという事です。つまり、聖人が写された本、又は著作にしても多くは失われてしまって現在まで伝えられはいないのではと思うのです。教化するのは、テキストがいります。いかに頭脳明晰な聖人といえども、テキスト無しでは到底無理の筈です。まして、60歳以降は聖人は京都、門弟は関東です。『唯信抄』にしても、関東門弟のテキストとして使われた筈なのです。勿論、鎌倉時代ですから文字を読み書ける人間はごく限られていました。しかし、親鸞聖人の有力な門弟は文字の読み書きができたようです。当時の知識階級なのです。そうであるが故に、より一層に知識欲に飢えるものなのです。本が溢れた現代とは根本的に違うのです。ご本山に上山しますと、ブックセンターには、聖人関係の本が山積みされています。時々に、ご本山にて本を購入いたしますが、そのせっかくの本も積読(つんどく)状態です。とても読み込みまではいきません。これが私の実情です。勝手に言わせていただければ、多くの僧侶も皆同じ状態では思うのですが・・・・お叱りをうけるかもしれません。
昭和56年の『本願寺年表』(浄土真宗本願寺派刊行)では、聖人が書き写された『唯信抄』でさえ、58歳を最初としますと、63歳、69歳、74歳に書かれた本が確認できるのみです。贈られた本を忠実に写して、まわし読みするのが当時鉄則。極めて本が貴重な時代、印刷・蔵版等は無い時代なのです。ですから、聖人の原本を書き写したので、これ以上は必要ないという意見もありますが、余りにも少ないと思うのです。
写真・・寛喜2年(1230年)5月25日奥書を持つ信証本(重文)高田専修寺蔵

上記の奥書(右)には、原本は承久(じょうきゅう)3年(1221年)9月14日、安居(あぐり)院法印(ほういん)聖覚(せいかく)作と書かれており、(左)には寛喜(かいき)2年(1230年)6月25日、その聖覚真筆(しんぴつ)の原本によって愚禿(ぐとく)釈の親鸞がこれを書き写したとあります。(聖人58歳)
聖人は、これらの『唯信抄』等を数多く書き写し関東の門弟に送られた筈なのです。それを物語る資料があります。親鸞聖人が、関東の門弟に送られたお手紙です。『ご消息』と呼びます。その『ご消息集』第8通(浄真宗聖典註釈版752頁)には、「たいていの人々は、『唯信抄』・『自力他力の文』・『後世(ごせ)物語の聞書』・『一念多念の証文』・『唯信抄文意』・『一念多念文意』、これらをご覧になりながら、慈信(関東に、聖人の名代として使われた聖人の長男である善鸞の事。善鸞事件として名高い)が説く法門にしたがって、大勢の念仏者達が弥陀の本願を捨ててしまったのです。(現代訳)」とあり、関東の門弟に京都から聖人が上記の書物を盛んに送られていたことがわかります。又、同一の『ご消息』第8通(浄真宗聖典註釈版751頁)には、もっと直接的に「慈信がごとき者の言うことをまにうけて、常陸・下野の念仏者たちの心がすべて浮ついてしまい、間違いのない証文を力をこめて数多く書き送りましたのに、それらをこぞって捨ててしまわれたとお聞きしたからには、もはや言うべき言葉もありません(現代訳)」と書かれています。証文を数多く書き送りましたとあります。ですから、現在存在する『唯信抄』だけではなく、数多く存在したのです。しかし、失われてしまったのです。残念でなりません。あれば、聖人の真筆ゆえに全て重文級の文書なのです。
続く・・・・・