

福井市街地の西方に、「花しょうぶの寺」として有名な臨済宗妙心寺派の萬松山・大安禅寺がある。この寺を創建した第4代福井藩主・松平光通の座像が、平成18年7月6日(木)、330年ぶりに外に運び出されるというニュースに接して、どんなところだろうと見学に行った。福井市立郷土歴史博物館で平成18年7月22日(土)から9月3日(日)まで、「越前松平家と大安禅寺」展が開催され、その目玉として松平光通座像がこの博物館に搬入されるというのである。
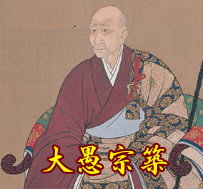
寺が創建される場合、僧から見た創建のことを「開山」という。大安禅寺の開山は、大愚宗築である。実際に資金を出した人から見れば、寺の創建は「開基」ということになる。開基は藩主・松平光通である。
大愚宗築は、天正12年(1584年)に生まれ、江戸谷中の南泉寺を開山するなど、臨済宗の高僧としてすでに著名であった。彼が治療のために山中温泉に滞在中に松平光通と親しくなり、同藩主に招かれて大安禅寺を開山したのである。万治2年(1659年)のことであった。以後、同寺は、歴代藩主の墓所となった。地元で、墓所は千畳敷と言われ、福井足羽地域の特産石・笏谷石(しゃくだにいし)が敷き詰められている。
しかし、この寺は、信長によって炎上させられた竜王山・田谷寺の跡地に創建されたものである。この田谷寺は真言宗であったらしい。創建は越前の泰澄大師であった。766年前後の年であった。この大師は、平泉寺(へいせんじ)、豊原寺、大谷寺も創建している。いずれも、庶民信仰の大道場であった。信長がこの寺を焼き払ったのは、天正3年(1574年)である。創建後、850年も続いた伝統ある寺が信長の越前攻めで廃墟にさせられたのである。田谷寺は福井の田ノ谷地区に建てられたものである。奈良時代の元正天皇の治下、養老年間、この寺は48坊をもち、賑やかな門前市が開かれていたという。しかし、1574年から1659年までの84年間、敷地は荒れ放題であった。
今度、330年ぶりに外に出ることになった松平光通座像は、光通没後、延宝5年(1677年)制作されたものである。その年、第5代藩主・松平昌親によって、開基堂が(福井県指定有形文化財)が建立され、光通のお抱え絵師であった狩野元昭の手になる肖像画を基に、当時の一流仏師・康乗が作成した光通座像が開基堂の厨子に安置されたのである。 座像が運び出された後、私は同寺に到着したのだが、非常に多くの寺関係者の方々が忙しく動いておられた。

この大安禅寺で、今年の4月12日、大変な発見がなされた。裏山から越前焼の甕(かめ)が発掘されたのである。甕からは木簡と古銭が入れられていた。古銭は、100枚前後の銭を1束として、紐で通していた。それには通し番号が着けられ、全部で1100束であった。つまり、約10万枚の通貨が出てきたのである。このお金は、おそらくは賽銭であったろうと思われる。甕が埋められた年が明応9年(1500年)7月吉日であったことが、木簡によって記されている。古銭は永楽通宝や洪武通宝などいずれも明銭で、数種類ある。現在価値に直せば800万円程度になると思われる。年代が確定できる中世の備蓄銭は福井県内では初めてであり、全国的にも珍しいという。年代が確定できるので、備前焼の歴史を知る上でも貴重な発見であったらしい。木簡は上の部分が三角形になっている祈願札である可能性が高い。
甕の中に備蓄金が入れられていたこと、甕が裏山に埋められていたこと、それも、信長の焼き討ちのはるか以前のことであったこと、真言宗らしいが、信長の憎悪を掻き立てる一大反抗勢力であったこと、浄土真宗ではないのに、一向一揆との関係があったらしいこと、そして、15~16世紀の日本で流通していた銭は、明銭であったこと、おうしたことをひとつひとつ検討して行けば、日本でも、マルク・ブロックに匹敵する古銭学が可能となるのかも知れない。写真は、甕の発見現場を示したものである。



















