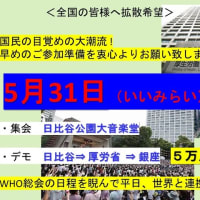スコット・マイナード氏
目下進行中の8.6%のインフレを阻止するため、米国連邦準備制度(FRB)は利上げなどの金融引き締め政策に転換しました。今回の紹介記事は、その先の展開を過去のデータを駆使して予想しています。当論考によれば、目下進行中のインフレは第一波にすぎず、いずれ第二波、第三波が、世界経済を襲います。加えて、その都度波はより高くなるとの由。
前途多難が予想される世界経済ですが、その荒波に呑み込まれることのないよう、共に先読みのセンサーを研ぎ澄ましましょう。
ちなみに、紹介記事に登場するスコット・マイナード氏は「ウォール街の3巨人」のひとりとされる米国金融界の超大物です。
***
マイナード氏: 株価暴落で金融引き締めが止まり物価高騰悪化へ
WWW.GLOBALMACRORESEARCH.ORG/JP/ARCHIVES/23397
2022年4月23日 GLOBALMACRORESEARCH
Guggenheim Partnersのスコット・マイナード氏がCNBCのインタビューで株価とインフレについて語っている。
景気後退懸念
市場では景気後退の前兆であるとされる長短金利の逆転が起こって以来、ようやく景気後退について話され始めている。
• 長短金利逆転を予測できた理由と今後の不況と株価暴落について
www.globalmacroresearch.org/jp/archives/22559
だが筆者にとってはこんな話は去年から明らかだったことであり、ここの読者も聞き飽きているだろう。
*長短金利逆転と株価暴落と景気後退の関係について、リーマンショックを例に挙げましょう。長短金利逆転が2006年2月、景気後退入りが2007年12月だから、2年弱の猶予期間がありました。株価暴落は景気後退の前に起こる場合が多く、リーマンショックの天井は2007年10月で、長短金利逆転から1年半後でした。
それを今回に単純にあてはめると、長短金利逆転が2022年4月、2023年10月が株価暴落、2024年2月が景気後退入り、となります。当論考の筆者は、今回それらが起こる間隔がもう少し狭くなると考えています。〔引用者 注〕
物価が高騰し、Fed(連邦準備制度)はインフレを抑えるために利上げなどの金融引き締め政策を行わねばならず、現在8.6%のインフレ率を抑制するためには金利は2018年に世界同時株安を引き起こした高金利を遥かに越えて上がって行かなければならない。
• アメリカの長期金利、2018年世界同時株安を引き起こした水準に近づく
www.globalmacroresearch.org/jp/archives/22889
そしてそれは株価も実体経済も破壊してしまうだろう。
最大のリスク
だがマイナード氏は興味深くも次のように言っている。
最大のリスクは景気後退ではない。最大のリスクは、株式や原油など何らかの資産クラスが暴落し、Fedが金融引き締めを止めなければならないと感じることだ。
だが金融引き締めを止めるのが早すぎた場合、Fedがインフレ抑制に本気だという信頼が失われるだろう。
何故引き締めを止めることがリスクなのか? 当然ながら現在8.6%のインフレ率が10%を遥かに越えて上がって行ってしまうからである。
もう一度ここからのシナリオを復習しよう。
まず、問題の根源は金融引き締めを行なった場合、インフレ率より先に株価が反応するということである。
金融引き締めは株価にも実体経済にも影響を与えるが、反応が早いのは株価の方である。インフレ相場でもまず金融市場で原油や小麦などの先物価格が上がり、それが時間差で消費者物価に転嫁されてくることは以前説明した。
この事実は金融引き締めを行うとどうなるかということに関係がある。何故ならば、実体経済よりも間違いなく株式市場が先に反応するからである。逆に株式市場に影響を与えない程度の金融引き締めでは間違いなくインフレを止められないだろう。
だから株価の暴落はインフレ阻止のための必要条件である。
株価暴落後のシナリオ
現在、米国株は次のように推移している。
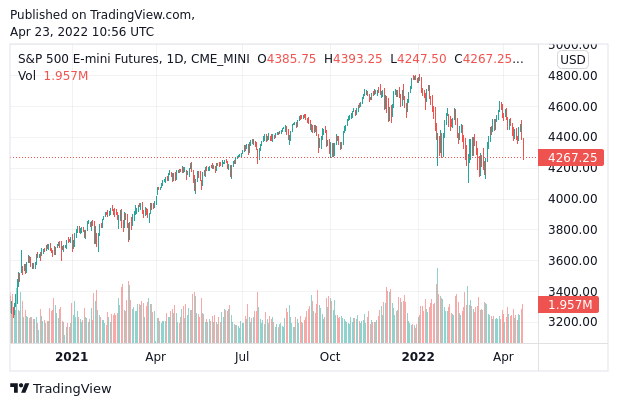
慌てている投資家も居るようだが、この程度では落ちた内にも入らない。1970年代の物価高騰では株価は60%下落したのである。
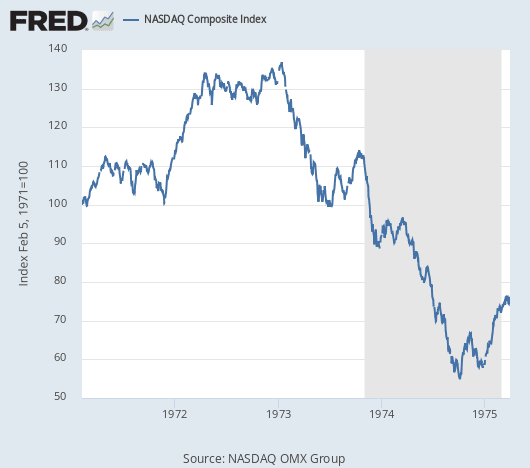
だが実際に株価が暴落した時、中央銀行はどうするだろうか?
マイナード氏は、この時に中央銀行が引き締めの手を緩めることが最大のリスクだという。何故ならば、株価が下落する程度にはインフレ率は下落しないだろうからである。
しかし中央銀行が甘い判断を下した場合、インフレが収まりきらない間に金融緩和が始まる。そうしてそれがインフレ第2波へと繋がってゆく。そして第2波のインフレ率は現在のインフレ率より酷いものになるだろう。
結論
実際、それが1970年代のアメリカの物価高騰時代に起きたことである。当時のインフレ率を再掲しよう。
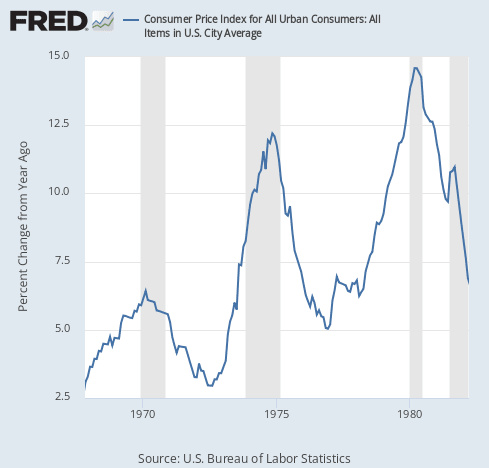
第3波まで来ていることが分かる。
現在のインフレも高確率で同じようになるだろう。筆者はこの「インフレ第2波」シナリオを去年から予想している。
• 現在のアメリカの物価高騰はインフレ第1波に過ぎない (2021/12/6)
www.globalmacroresearch.org/jp/archives/17958
それについてマイナード氏が話し始めたということである。
何度も言うがここではすべてを事前に書いているので、参考にしてもらいたい。もうインフレは手遅れなのである。
• 2022年の株式市場: パーティは終わっているのにまだ踊っている人がいる
www.globalmacroresearch.org/jp/archives/21985
***
当論者は別の論考で、おおむね次のように言っています。「コロナ後の株価上昇は大規模な現金給付と金融緩和政策によってもたらされた。いまやそれら2つの株価上昇の要因は消滅した。それゆえ株価が上昇する要因はない」と。目下の株価は、どうひいき目に見ても下落しやすい基本体質を有しているとしか言いようがないのです。