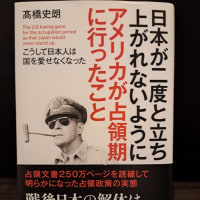はじめのことば
人間は何事にせよ、自己に適した一能一芸に深く達してさえおればよい
与謝野晶子「人間礼賛」
無縁遺骨
毎年、増えていく火葬後も引き取り手がいない遺骨が増えていき、保管場所に困るという記事が目に止まりました。また、火葬場がいっぱいで、火葬待ち遺体のことも話題に上がっています。少子高齢化社会で、高齢者が増え続け、これからもピークを迎えます。わたしもいずれはあの世行き、国に遺骨を保管してもらうことになるのかもしれません。
無縁遺骨の原因の一つは、戦後、核家族化が進み、戦前の長子家族制度が崩壊したことです。「貧乏人の子沢山」という言葉がありました。大正生まれの私の父の兄弟は12名、母の方は8名、合計20名の叔父と叔母がいましたた。今では考えられないことです。家父長制度で、長男が家を継ぐのがそれまでの日本のしきたりになっていました。財産を引き継いだ人が、その家の柱となり、親、兄弟を面倒みました。そこには、先祖からの血脈が永遠と続いてきた縦のキズナで、とても強いものでした。戦後になり、「自由と平等」の甘い誘惑に陥った日本人は、親と子は平等なんだ、そんなはずはありません。勘違いしてしまいました。なぜならば、親は子を養う義務があります。そのこと一つみても、平等なんてことはありえません。本家と分家があり、前者を大黒柱としてピラミッドの頂上に位置し、後者が底辺まで続きます。その象徴が家系図でした。私が結婚して1年後、母と家内と、新潟にある両親の本家を訪問し、墓参り、そして線香を手向けました。それほどまでに、戦前の家制度は、分家は本家を大切にし、逆に本家は分家の面倒をできるだけみました。その縦のつながりがくずれてしまったのが原因で、核家族化になり、独居老人等が増えたために、無縁遺骨も比例して増えるのは当然の帰結です。
葬祭扶助とは
「遺族が葬祭費を支出できない場合や身寄りがない故人について、家主や病院長など第三者が執り行うと申請すれば、行政が費用を一部負担する仕組み。都市部で1件21万円と規定されている」
2022年度
件数 5万2561件
費用 110億円
公費で葬祭費負担、過去最多 資産や身寄りない人 昨年度5.2万件110億円 https://www.asahi.com/articles/DA3S15773460.html
無縁遺骨、保管に苦慮 骨つぼ2千個、引き取り「年に数人」 https://www.asahi.com/articles/DA3S15773470.html
きょうはこれでお仕舞です。ご訪問くださいましてありがとうございました。