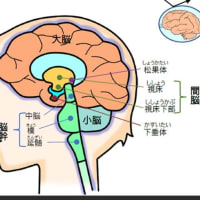今回は、女性の方が読まれていれば石を投げられるかもしれない(旧約時代当時の刑罰の一つで石で撃ち殺すというのがあった)。それは、表題の女性(※)については、学生時代から本はあったが、どうしてもしっくりいかない。女性特有の気質みたいなものを感じてしまう。ペラン神父への手紙を読んでも、果たして哲学者であるから、人間の言葉を屈指しるためにもその言葉というものを信じている人なのだろうな・・・というそこで限界を僕は感じてしまうからなのだ。1900年代の前半を生きた人であるにもかかわらずなのだ・・・。ブログの開始の方にこのヴェーユがカトリックではなく、プロテスタントであればおそらく全く異なった見解になったのになぁと思ったものだ。しかし、その前にそもそも宗教自体は語るはいいが、信ずるものではないと考えていただろうから。
(※:フランスで同名の方が憲法裁判所の判事となられている政治家がおられるのですが、この方もガンガンものを言う(347回参照)フランス女性です。)
◆女性特有の強い思い込み、自分を相対化できにくいこと。そして、対象を内面ではなく、外部に求め精神的優位、しかもその基準は思い込みの中にあるので普遍性が問われていないということがままある。それで、自分の思考の意味つけのために、精神的優位を保つためにと言えばいいか不幸をさがし歩くのだ。これは女性特有の気質のようなものではないだろうか。自己肯定のためにそれ以上は実は考えない。先の回のプロテスタントの自己認識云々とはずいぶんと大きな開きがあるのである。それであるから、フランスはカトリックが強かったのすが1900代にしても、他のプロテスタントからしてずいぶん、同じキリスト教でも内容はずれがあるなと考えさせられる。しかし、けれどやっぱり彼女のような哲学者は出て来なければいけなかったのだろうな。その彼女の人間的気質の一端・・・
◆「・・・14歳の時、私は思春期の底なしの絶望の一つに落ち込みました。自分の能力の凡庸さに苦しみ、真剣に死ぬことを考えました。パスカルの才能に比較されるほどの少年期、青年期を持ったわたしの兄の才能が、どうしてもわたしに自分の凡庸さを意識させずにおかないのでした。・・・」(この兄さんは、日本に来られたことがあるらしい)
◆これが彼女の気質のすべてを語るスタートラインです。であるから、不幸を求めて(そもそもこの基準はどこから引き出すのかだが)精神的優位に実際的に立とうとする自分には心理的に自覚されない動機になっていたのではないだろうか。上の文章は『神をまちのぞむ』に入れられた「精神的自叙伝」と題する長い手紙の中の一部ですが・・・ここで、プロテスタントの僕はそもそもこの著作名がいただけない。神は既に来ているのだから・・・。
◆「全体主義的ローマ帝国が崩壊の後、アルビジュワ戦争後の13世紀のヨーロッパには初めての全体主義の下ごしらえをしのたのは教会(カトリック)であったのだ。」といい、だから彼女は、教会の外に立ち続け、ただ待ち続けたい(「エン・ヒュポモネー」というギリシャ語が使われている=ここから『神をまちのぞむ』が著作名となった)という。
◆「わたしはいかなる場合にも、服装によって大多数の人間から自分を引き離さないために、宗教的組織の中には入らないだろうと思います。」それは「巨大な不幸な不信仰者の集団から自分を引き離す」ことになるからというのだった。
◆・・・しかし、僕が彼女の著作でしばしば止まってしまうのは、言葉のアプリオリ(先んじているその意味と理解、つまり基準)は何に基づいているのかということなのだ。それは、彼女自身が、女性特有の自己を相対化できない、偏頭痛に悩まされたこともあるだろうが、その自己の肉体にて不幸を体験して、そう、それはおそらく彼女のいう不幸の自己体験、基準を自ら体験として確認したいというまさに不幸な自己欲求でもあったろうと思ってしまう・・・。
◆自分の言葉でイエスと会話をすることを、その組織はあまりに歴史があり巨大であったから依存することを嫌い、聖書そのものに対する思考を棚上げしてしまったのだろうと・・・。聖書には、そもそも人間側がいかようにもその判断基準を持ち得る「不幸」という言葉は出てこないのだ。・・・
(※:フランスで同名の方が憲法裁判所の判事となられている政治家がおられるのですが、この方もガンガンものを言う(347回参照)フランス女性です。)
◆女性特有の強い思い込み、自分を相対化できにくいこと。そして、対象を内面ではなく、外部に求め精神的優位、しかもその基準は思い込みの中にあるので普遍性が問われていないということがままある。それで、自分の思考の意味つけのために、精神的優位を保つためにと言えばいいか不幸をさがし歩くのだ。これは女性特有の気質のようなものではないだろうか。自己肯定のためにそれ以上は実は考えない。先の回のプロテスタントの自己認識云々とはずいぶんと大きな開きがあるのである。それであるから、フランスはカトリックが強かったのすが1900代にしても、他のプロテスタントからしてずいぶん、同じキリスト教でも内容はずれがあるなと考えさせられる。しかし、けれどやっぱり彼女のような哲学者は出て来なければいけなかったのだろうな。その彼女の人間的気質の一端・・・
◆「・・・14歳の時、私は思春期の底なしの絶望の一つに落ち込みました。自分の能力の凡庸さに苦しみ、真剣に死ぬことを考えました。パスカルの才能に比較されるほどの少年期、青年期を持ったわたしの兄の才能が、どうしてもわたしに自分の凡庸さを意識させずにおかないのでした。・・・」(この兄さんは、日本に来られたことがあるらしい)
◆これが彼女の気質のすべてを語るスタートラインです。であるから、不幸を求めて(そもそもこの基準はどこから引き出すのかだが)精神的優位に実際的に立とうとする自分には心理的に自覚されない動機になっていたのではないだろうか。上の文章は『神をまちのぞむ』に入れられた「精神的自叙伝」と題する長い手紙の中の一部ですが・・・ここで、プロテスタントの僕はそもそもこの著作名がいただけない。神は既に来ているのだから・・・。
◆「全体主義的ローマ帝国が崩壊の後、アルビジュワ戦争後の13世紀のヨーロッパには初めての全体主義の下ごしらえをしのたのは教会(カトリック)であったのだ。」といい、だから彼女は、教会の外に立ち続け、ただ待ち続けたい(「エン・ヒュポモネー」というギリシャ語が使われている=ここから『神をまちのぞむ』が著作名となった)という。
◆「わたしはいかなる場合にも、服装によって大多数の人間から自分を引き離さないために、宗教的組織の中には入らないだろうと思います。」それは「巨大な不幸な不信仰者の集団から自分を引き離す」ことになるからというのだった。
◆・・・しかし、僕が彼女の著作でしばしば止まってしまうのは、言葉のアプリオリ(先んじているその意味と理解、つまり基準)は何に基づいているのかということなのだ。それは、彼女自身が、女性特有の自己を相対化できない、偏頭痛に悩まされたこともあるだろうが、その自己の肉体にて不幸を体験して、そう、それはおそらく彼女のいう不幸の自己体験、基準を自ら体験として確認したいというまさに不幸な自己欲求でもあったろうと思ってしまう・・・。
◆自分の言葉でイエスと会話をすることを、その組織はあまりに歴史があり巨大であったから依存することを嫌い、聖書そのものに対する思考を棚上げしてしまったのだろうと・・・。聖書には、そもそも人間側がいかようにもその判断基準を持ち得る「不幸」という言葉は出てこないのだ。・・・