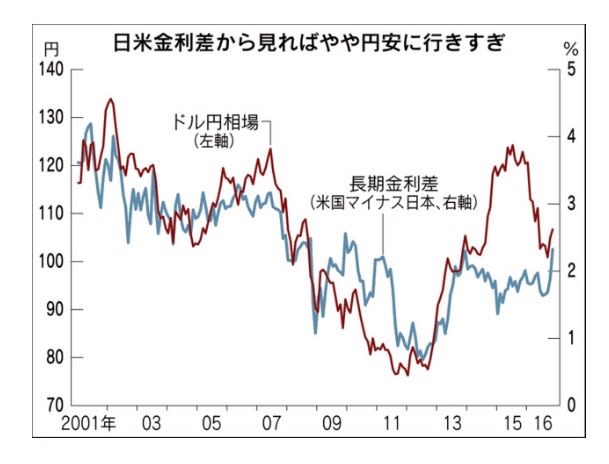日立、IoTで街づくり 駅の混雑緩和や店舗開発支援
2016/11/28 1:30 日経
日立製作所はあらゆるモノがネットにつながる「IoT」を使い、便利で安全な街づくりを支援するサービスに乗り出す。国内企業でほぼ唯一、カメラやセンサー、人工知能(AI)、ネットワーク技術など必要な技術を全て自前でそろえる強みを生かし、駅の混雑緩和などのサービスを提供する。専門部署を設け、2020年度に年1千億円の受注獲得を目指す。
不動産開発会社や鉄道会社向けに売り出す。画像解析技術などで集めた年齢と性別、同行者の有無といったデータ以外はすべて匿名にしてプライバシー保護を徹底する。
日立は通常の監視カメラから熱や音を検知するセンサー、AI、ネットワーク監視技術まで自前で手がける。世界でも一気通貫でこれらの事業を本格的に手がけるのは独シーメンスや米ゼネラル・エレクトリック(GE)など大手に限られる。日立は陣容を整え、先行する両社を追撃する。
例えば、鉄道駅の開発では、駅構内に物体の大きさや距離、速度を測定できるレーザーセンサーなどを増設する。監視カメラによる画像解析と組み合わせ、構内を行き交う人の数や通行ルートを分析。頻繁に通行人が滞留する場所を割り出した上で、構内設備の再配置や運行ダイヤの見直しなどを助言する。
駅ナカなどの店舗開発にも役立てる。通行人の年齢や性別、同行者の有無を解析し、効果的なテナント配置を模擬実験して集客策を指南する。店舗や設備の稼働情報から省エネや機器の故障予兆診断も可能になる。
交通改善や電力安定、住宅街の保安などにも応用が可能で海外市場の開拓にも注力する。日立はサービス利用企業のコスト削減分や増収分の一部を収入として、継続的に受け取る。
日立は今年5月、IoTのサービス基盤「ルマーダ」を立ち上げた。ビッグデータ解析やAIを使って顧客企業の課題を浮き彫りにし、具体的な業務改善を指南する事業の育成を急ぐ。
米調査会社のガートナーによると、世界のIoT市場は20年に3兆100億ドル(約330兆円)と15年の3倍に拡大する見通しだ。カメラやセンサー、データ管理システムなど関連機器の需要が増える。
2016/11/28 1:30 日経
日立製作所はあらゆるモノがネットにつながる「IoT」を使い、便利で安全な街づくりを支援するサービスに乗り出す。国内企業でほぼ唯一、カメラやセンサー、人工知能(AI)、ネットワーク技術など必要な技術を全て自前でそろえる強みを生かし、駅の混雑緩和などのサービスを提供する。専門部署を設け、2020年度に年1千億円の受注獲得を目指す。
不動産開発会社や鉄道会社向けに売り出す。画像解析技術などで集めた年齢と性別、同行者の有無といったデータ以外はすべて匿名にしてプライバシー保護を徹底する。
日立は通常の監視カメラから熱や音を検知するセンサー、AI、ネットワーク監視技術まで自前で手がける。世界でも一気通貫でこれらの事業を本格的に手がけるのは独シーメンスや米ゼネラル・エレクトリック(GE)など大手に限られる。日立は陣容を整え、先行する両社を追撃する。
例えば、鉄道駅の開発では、駅構内に物体の大きさや距離、速度を測定できるレーザーセンサーなどを増設する。監視カメラによる画像解析と組み合わせ、構内を行き交う人の数や通行ルートを分析。頻繁に通行人が滞留する場所を割り出した上で、構内設備の再配置や運行ダイヤの見直しなどを助言する。
駅ナカなどの店舗開発にも役立てる。通行人の年齢や性別、同行者の有無を解析し、効果的なテナント配置を模擬実験して集客策を指南する。店舗や設備の稼働情報から省エネや機器の故障予兆診断も可能になる。
交通改善や電力安定、住宅街の保安などにも応用が可能で海外市場の開拓にも注力する。日立はサービス利用企業のコスト削減分や増収分の一部を収入として、継続的に受け取る。
日立は今年5月、IoTのサービス基盤「ルマーダ」を立ち上げた。ビッグデータ解析やAIを使って顧客企業の課題を浮き彫りにし、具体的な業務改善を指南する事業の育成を急ぐ。
米調査会社のガートナーによると、世界のIoT市場は20年に3兆100億ドル(約330兆円)と15年の3倍に拡大する見通しだ。カメラやセンサー、データ管理システムなど関連機器の需要が増える。