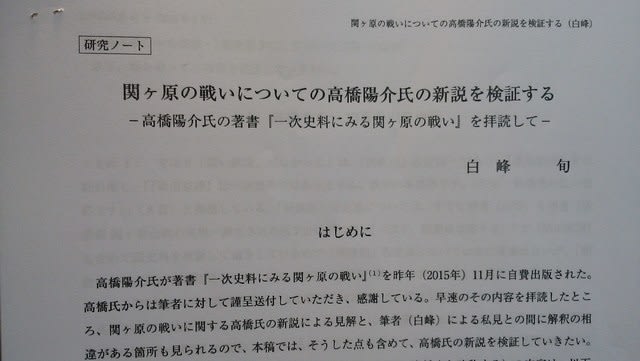兜掛石案内板 不破関庁舎跡
兜掛石 兜掛石
靴脱石 靴脱石
不破関跡 東山道左側「中山道」
藤古川説明板 合戦場所跡
壬申の乱説明板 合戦場所付近
自害峯案内板 黒血川説明板
自害峯 三本杉
自害峯 三本杉碑
*壬申の乱は弘文元年(672年)天智天皇(中大兄皇子)の後継を巡って起きた,
「天下分け目」の戦い!
当時の兄弟継承という慣習を無視し、近江朝廷の政権を握ったのは、
天智天皇の息子である「大友皇子」。
これに対して天智天皇の実の弟大海人皇子が、反乱を起こしたと言われています。
まず「大海人皇子」は「村国男依」らを美濃へ遣わし交通の要所である不破道を抑
え東国を掌握。野上行宮へと進んだ「大海人皇子」は軍を指揮し、
不破関の藤下(とうげ)を挟んで「大友皇子軍」と「大海人皇子軍」が対立。
弘文元年(672年)7月1日には玉倉部邑で壮絶な戦いが繰り広げられました。
7月22日に大津(滋賀県)の瀬田橋の戦いで最終決戦がおこなわれ、
「大海人皇子軍」が勝利し、翌日「大友皇子」は自害し、三本杉の下に眠っている
と言われています。

不破の関付近*自害峯・三本杉
(大友皇子首塚・25歳)