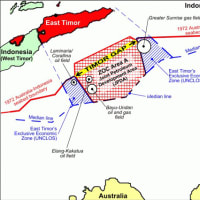アルマンドの車は真っ暗な山中でパンクした。すぐ先の道路には民兵によって殺された大勢の遺体がいまだ打ち捨てられている。そこには女性や子供の遺体さえある。二〇〇mほど先のその地点は、東ティモール併合民兵の待ち伏せ場所だった。しかし、そんなところでパンクしたとはアルマンドは知る由もなかった。
一九九九年九月。
東ティモールはインドネシア国軍、警察、そして併合派民兵の殺戮と破壊と略奪の真只中にあった。ディリの街のいたるところに殺害された遺体があった。路上にころがる遺体。家屋内、商店内にはガソリンを撒かれ焼かれた遺体。井戸の中には折り重なるように投げ込まれていた。特に海岸には多くの遺体が打ち捨てられていた。地方のある街では、多くの住民が生きたまま、高さ数百メートルの崖から突き落とされた。東ティモール全土で一〇〇〇~三〇〇〇人あまりの市民が虐殺されたというが、いまだ正確な数字は判然としない。海に流された遺体やワニのいる川に流された遺体もあるからだ。
インフラの八十%は破壊され、ビルといえるものはすべて炎上した。一般家屋も破壊、焼打ちを免れたものは少ない。破壊を免れた家屋も全ての財産を略奪された。車、バイク、電化製品あらゆるものが消えた。
あれから二年(二〇〇一年当時)近くたった今でも、インフラのほとんどは破壊されたままである。どの街を訪れても、破壊され炎上した建物や民家ばかりが目につく。地域によって差はあるが、現在でも電気、水道の供給すら完全ではない。
九九年九月一七日、その殺戮と破壊の真只中の街から、アルマンドは単身、車を運転してディリを脱出した。この車は、民兵の略奪を恐れた彼の友人が、西ティモールのクパンまで運んでくれるよう依頼したものだった。ティモールでは車はたいへんな財産である。
<暗闇>
左前輪がパンクしていた。西ティモールとの国境まであと数十キロの山の中である。もっとも危険な地帯だ。速やかにタイヤを交換し、出発しなければならない。
しかし、パンクした車を前にアルマンドは途方にくれていた。車にはタイヤのボルトを外す工具がなかった。工具と呼べるものはジャッキ、ペンチ、ドライバーにプラグレンチくらいだった。あとはゴムのり、ハサミ、ヤスリ、ビニールホース、針金、そして壊れたプラグ。これだけで一体どうすればいいというんだ。
"こんなところでもたもたしていたら民兵に見つかってしまう"
アルマンドは恐怖した。すぐそばには民兵に襲撃されたものであろう一台の焼かれた車があった。
パンクした車の前でアルマンドは知恵をしぼった。
とにかく車をジャッキアップした。
どうやってタイヤをとめている四つのボルトを外すか。ペンチなどでは緩まない。タイヤレンチの代わりになるものはないか。しかし車にはそんなものはない。
"考えろ!考えれば、なんとかなる。"
アルマンドは普段から、何でも工夫することが好きな質だった。
一般に途上国の人々は、あるだけの道具、あるだけの材料で、物を修理することに長けている。車種に合わないフロントガラスをばっちりはめ込んだりもする。工夫次第でたいていのものはなんとかなるものなのだ。
アルマンドはジャッキをポンプアップするためのステンレスパイプに目を付けた。幸いパイプの内経はボルトよりも大きかった。彼はパイプの端を石で叩いた。タイヤのボルトに合わせて、また叩いた。ボルトにはまるように狭めるためだ。ボルトにがっちりはまるまで叩いた。それが完了すると、そのパイプを傍らの焼かれた車の頑丈な部分に差し込み、ゆっくりL字型に折り曲げた。
タイヤレンチができあがった!
即席レンチをボルトに差し込み、力いっぱい回すと、きしみ音をたててボルトは緩んだ。急いで、四つのボルトを外し、パンクしたタイヤを車から取り外した。アルマンド安堵した。あとは、スペアータイヤを取り付れば脱出できる。アルマンドはトランク・ルームからスペアータイヤを取り出した。
しかし、スペアータイヤはぺしゃんこに空気が抜けていた。
午前一時。アルマンドは暗闇の中にひとり呆然と立っていた。
<ディリ>
アルマンドが脱出してきたディリの街では、この世の地獄が続いていた。
彼は、民兵が女性を殺す現場さえ目撃している。しかし助けたくともどうすることもできなかった。見つかれば自分も殺される。隠れて、ただ見ているしかなかった。
しかし彼もついにインドネシア国軍兵士に見つかってしまう。 が、幸い、アルマンドは西ティモールのフローレス生まれだった。
西ティモール生れで東ティモールに移住してきた者は、すなわち併合派(支持)と単純に受け取られていた。彼は六才の時に両親に連れられて東ティモールに移り住み、以来二七才の今日まで東ティモールの人間として生きてきた。ただし独立を指示する人間として。彼は独立派ゲリラ・ファリンティル(現国防軍)に多量の弾薬を寄付したことさえある。国連が来てからはUNAMET( United Nations Mission in East Timor)のセキュリティ・ガードとして働いた。
国軍兵士はアルマンドが独立支持だとは夢にも思わなかった。しかし、西ティモールに去らねば、撃ち殺すと脅かした。虐殺と破壊の中、併合派の市民はすべて強制的に西ティモールに送られていた。併合派の家屋も容赦なく破壊された。強制避難に従わなければ併合派でも容赦はなかった。アルマンドはディリ退去をよぎなくされた。しかし、ディリに留まるのも、退去するのも、同じくらい危険に満ちていた。
<暗闇>
アルマンドは役に立たないスペアータイヤを前に途方にくれていた。
どうすればいいのか・・・タイヤレンチを自作して、ようやくタイヤを外したというのに。
そのときディリの方角から車のライトが近づいてきた。アルマンドはその車を止めた。家族を乗せ同じくディリを脱出してきた車だった。事情を説明した。その車にはスペアータイヤが積まれていた。が、無情にも、彼はそのタイヤをアルマンドに与えることを拒否した。しかし無理もない。家族まで乗せているのだ。スペアータイヤを失ったあと、今度は彼の車がパンクするかも知れない。アルマンドは、相手を恨む気にはならなかった。
スペアータイヤは諦めるしかなかった。しかしアルマンドは彼に五分だけ待ってくれるように頼んだ。先を急ぐ相手は苛々しながらも、なんとか聞き入れてくれた。
アルマンドは急いでパンクした前輪と、スペアータイヤをヘッドライトで照らされた路上に並べた。
彼はこれからパンクしたタイヤのチューブを修理するしかなかった。タイヤからチューブを取り出す作業は一見単純だが、人力で行うのは容易ではない。ホイールのリムにがっちりはまっているタイヤの縁を一度リムの内側に外す必要がある。人力で行おうと思えば、大型の鉄のハンマーでもない限り不可能だ。どうやって外せばいいのか。それをアルマンドは思い付いたのだ。
路上に並べた二つのタイヤ。それを車のタイヤでゆっくり踏んでもらった。車の重みでタイヤの縁はリムの内側に外れた。タイヤを踏んでしまうと車はそのまま去って行った。
アルマンドはヘッドライトの明かりの中に、またひとり残された。
彼は次のことを考えなければならなかった。
チューブを取り出すためには、いったんホイールのリムの内側に外したタイヤの縁を、今度は逆に外側へ外さなければならない。これも本来専用の金属の板二枚がなければ容易にはいかない。
が、当然そんなものはここにはない。
"丈夫な金属の板はないか!"
アルマンドは闇夜の中で恐怖と闘いながら、次から次へと考え続けなければならなかった。
板状の丈夫な金属・・・。
アルマンドは焼かれた黒焦げの車を見た。そこに板状の金属を発見した。彼は車の下にもぐった。そしてそれを取り外した。
サスペンション用の板バネだった。
専用の工具より幅も厚みもはるかに大きい。それ自体ではとてもリムとタイヤの縁の間に入るしろものではなかった。彼はドライバーを取り出し、リムとタイヤの縁の間に差し込んで、こじあげた。なんとか分厚い板バネを差し込む隙間ができた。板バネをその隙間にねじ込み、力一杯こじあげた。タイヤの縁はリムの外側に外れていった。これでチューブが取り出せる。ヘッドライトの明かりの中で
黙々と作業を進めた。
ふたつのタイヤからチューブを取り出し、チェックした。前輪のタイヤのチューブは裂けていた。パンクというとり破裂したのだ。スペアータイヤの方のチューブは穴が空いているだけだった。チューブの修理をはじめた。穴の修理は簡単だ。裂けた方のチューブをハサミで切り取った。ハサミは小さく切れない代物だったが、あるだけでありがたかった。切り取ったチューブ片にヤスリをかけた。
チューブの穴のあいた部分にもヤスリをかけ、両方にゴムのりを塗り一〇分待った。張り合わせたあとを石で叩いて密着させた。修理の完了したチューブをタイヤの中に戻した。そしてホイールの外側にはずしたタイヤの縁を、再度板バネを使って、ホイールのリムの内側にもどした。
終わった・・・
これであとは空気を入れるだけだ。
そこまでを恐怖と闘いながら、必死になって考え続け、アルマンドはやり遂げた。
しかし、彼は最後の段階になって呆然自失となった。
"どうやってタイヤに空気を入れたらいいんだ!"
続けざまにおとずれる目の前の難問を、一つずつ解決するのに必死だったアルマンドは、先のことなど考える余裕はなかった。ここまでやり遂げながら、空気を入れられなければ、何の意味もないではないか!風船をふくらますのとはわけがちがう。コンプレッサーかポンプがなければどうにもならない。こんな山の中にそんなものがあるわけがない。いままでの努力は一体何だったんだ。
アルマンドは泣き崩れた。
泣きながら神に祈った。
"生まれたばかりの子供の顔をもう一度見せてください。妻の顔を見せてください"と。
民兵がいつやってくるかもしれない。そう思うと気が狂いそうになった。アルマンドは絶望感で泣き続けた。
漆黒の闇夜だけが彼の味方だった。
<ディリ>
そもそもアルマンドは、いったん西ティモールのクパンに避難していたのだ。それをわざわざ殺戮と破壊の真只中の東ティモールのディリに舞い戻ってきたのだ。「給料」を受け取るために。
併合派民兵が大暴れする混乱の中で、彼は国連(UNAMET)のセキュリティ・ガードとしての給料を受け取れないまま西ティモールに避難した。先にクパンに避難していた妻は子供を出産していた。クパンで彼は無一文に近い状態だった。それで彼はディリに戻って、UNAMETから未払いの給料を受け取ろうと決心した。無謀といえばあまりにも無謀な行為だ。安全な西ティモールのクパンから、わざわざ殺戮の街にやってくるとは。しかし、それほど金に困っていた。まさにミルク代もなかったのだ。西ティモールには金を借りられるような友人、知人はいなかった。たよりはUNAMETの給料だけだった。
しかし、危険を冒してディリに着いてみると、国連の姿はどこにもなかった。いったい何のために舞い戻ってきたのか・・・。
<暗闇>
アルマンドは泣き続けた。
そして祈り続けた。
"生まれた我が子の顔を、妻の顔を見せてください"
そしてアルマンドは何度も自分に言い聞かせた。
"考えるんだ!あきらめるな!考えろ!"
"生きてここを脱出するんだ!"
しかし、ポンプもコンプレッサーもないこの山の中で、どうやってタイヤに空気を入れることができるのか。不可能だ。いくら工夫することに長けたアルマンドでも、もはや答などないことは明白だった。
彼は絶望の淵にいた。
それでも、彼は自分に言い続けた。
"考えろ!あきらめるな!"と。
泣き、祈り、考え続けた。
考える続けることだけが、恐怖から逃れる唯一の方法だった。
長い時間が経ったように感じた。
そしてアルマンドの頭に、ひとつのイメージが浮かんだ。
"やってみる価値がある!"
アルマンドは、トランクに転がるスパークプラグに飛びついた。古びて壊れ、使いものにならない代物だった。彼はペンチと釘を使ってスパークプラグに細工をしはじめた。それが完了したら、車のボンネットを開け、四気筒のエンジンからスパークプラグをひとつ取り外した。そしてそこに細工したスパークプラグを取り付けた。
<ピックアップ>
このとき、ディリの方向から車のライトが近づいてきた。そしてアルマンドの車の後方で止まった。ピックアップトラックだった。アルマンドはスペアータイヤを持っているか尋ねようと思った。運転席に三人、荷台に一人の男がいた。男たちが降りてきた。二人はアルマンドの右側に、一人は左側に、残る一人は車の後方に立った。四人の内三人はAK四七自動小銃を持ち、一人だけ拳銃だった。
ついに恐れていたことがおこった。
「ここで、何をしている」
男の一人が冷たい声で言った。
アルマンドの心臓は高鳴った。
「パンクの修理をしている・・・」
アルマンドは答えた。心臓は高鳴り続けた。
男たちは冷たい目でアルマンドを見続けた。
彼らは制服は着ていなかったが、インドネシア国軍兵士に違いなかった。四人そろってアーミーカットだった。民兵はどちらかといえば長髪が多い。
アルマンドのズボンのポケットには国連のセキュリティ・ガードのIDと国連旗があった。国連で働くものは独立派であるとみなされる。ボディ・チェックされれば、まちがいなく命はない。
男たちは、アルマンドを見定めるように、黙ったまま睨み続けていた。そして、
「ここに長居するな・・・死にたくなければ・・・」
と低い声ですごんだ。
それだけを言うと男たちはピックアップで走り去った。
アルマンドは胸をなで下ろした。
兵士のピックアップには略奪してきたものであろう様々な物品が満載されていた。彼らは先を急いでいたのだろう。
我が身の好運を喜んでいる暇はなかった。もはや一刻も早くここを去りたかった。第二第三の略奪兵士や民兵が来るかも知れない。
アルマンドは急いで作業の続きに入った。
<暗闇>
彼は、トランクにある一メートルほどのビニールホースを取り出した。そして、兵士が来る前に、エンジンに取り付けた”細工をしたスパークプラグ”に、そのホースをかぶせ、はずれないように針金できつく巻いた。ホースの反対側を、パンク修理をすませたタイヤの空気注入口にかぶせ、おなじく針金でしっかりと巻いた。エンジンとタイヤがホースでつながった。
そしてアルマンドは運転席に飛び込み、キーを回した。エンジンをかけると、アクセルをめいいっぱい踏み込んだ。
夜の静寂を打ち破りエンジンが唸る。
ポンプはあったのだ。エンジンとはすなわちポンプそのものではないか。
ペンチと釘を使って中身を引き抜き「中空」にしたスパークプラグを通り、シリンダー内の混合気はビニールホースからタイヤへ送られた。
三分ほどエンジンを吹かし続けた。長い時間に感じた。そして運転席から飛び出し、タイヤの圧を確かめた。すでに十分入っている。完璧ではないが、走るのに問題はない。もはや一秒も長居したくはなかった。アルマンドはホースを引きはずした。細工をした中空のプラグを外し、正常なプラグを取り付けた。そしていまや「混合気」で膨らんだタイヤを、手製タイヤレンチで車に取り付けた。
時計は午前三時を差していた。二時間かかった。いや、たった二時間でやってのけたのだ。
<脱出>
アルマンドは車を走らせた。
二〇〇メートルほど走ると、車は急な登りの右カーブに差し掛かった。アルマンドの車のヘッドライトは道路脇の多くの遺体を照らし出した。二〇~二十五体。殺害され、血にまみれた男性、女性、老人、若者、そして子供の遺体。信じられない光景だった。アルマンドはそこが民兵の待ち伏せ場所だったことを悟った。
アルマンドは涙を流しながら、ハンドルを握った。
夜が明ける前に、彼は危険地帯を抜けた。
そして、生まれたばかりの我が子と妻の待つ、クパンに着いた。
クパンを出た時と同様、無一文で。
車の所有者である友人は、車を受け取ると礼を言っただけで、何の謝礼も支払わなかった。
------------------------------------------------------------
これはインタビューをもとに構成した真実の物語である。
中司達也