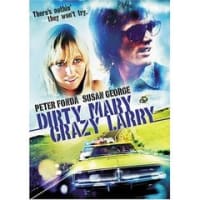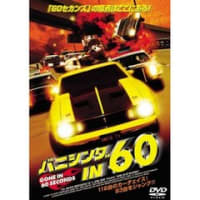もし、特殊な禁固刑にでもなって、残りの一生にたった一本の映画しか見る事を許されないなら、私はこの作品を選びます。
それは、骨董品の第二次世界大戦時のドイツ航空機が実際に飛行する姿を空中カメラで撮影した最後の作品だと思うからです。現在は CG でしかそれを表現できません。
英米の航空機ならばファンが保存・補修したものが僅かながら稼動状態で残っていますが、敗戦国ドイツの航空機を実際に飛ばして撮影するのは非常に困難なのです。その撮影秘話は、一冊の本になるくらい多くのエピソードで彩られています。
<この動画のシーン>
一人だけ白い派手な将校服を着ているのは、空軍大臣ゲーリングです。彼はいつまでたっても英国空軍を封じる事が出来ず、英国上陸作戦を始められないとヒトラー総統から叱責されていたので、部下の無能に怒っています。
爆撃隊の責任者は「英国戦闘機が大群で襲ってくるのに、護衛戦闘機が近くに居ないので損害が多いのです。」と愚痴を言います。
戦闘機隊の責任者は「戦闘機は(爆弾を積んでいるので重くて遅い)爆撃機に速度を合わせて飛んでいては敵機を狩る事は出来ません。」と言います。長年の経験に基づいて高速での一撃離脱戦法を採用していたドイツ戦闘機パイロットにとっては「速度こそ攻防一体の武器」であり、メッサーシュミット戦闘機はその目的の為に改良・特化した機体だったのです。
逆に、英国のスピットファイアは最低速度が低く格闘戦が得意な機体でした。ちなみに日本の零戦はもっと軽量&低速で、より格闘戦に特化していました。
元は戦闘機乗りのゲーリングですが、「ゆっくり飛ぶのが怖いのか?臆病者め!これは命令だ。爆撃機の傍を離れずに飛べ!」と無茶な要求を戦闘機隊に押し付けます。
叱責したあとでゲーリングは「私は怒りに来たのではない。君たちを助けに来たのだ。支給が必要な装備が有るなら、何でも言ってくれたまえ。」と懐柔の言葉をかけます。
そこで戦闘機隊の責任者は「我が飛行隊にスピットファイアを支給してください。」と言います。敵国の最新鋭戦闘機を購入出来る訳が無く、これは痛烈な皮肉です。しかし技術論で言うと、「用途に応じた装備の要求」という意味では全く正論であるところがミソです。
実行不可能な要求を受けたゲーリングは、顔を真っ赤にして、怒って帰ってしまいます。この瞬間にドイツ空軍の運命は「敗北」に傾きました。もしドイツ空軍に日本製の零戦が支給されていたら、違う結果が出たはずです。
<メッサーシュミット>
敗戦時に残っていたドイツ機は、少数の博物館や研究機関に送られたもの以外は全てスクラップにされました。製造設備や冶具も全部壊され、設計図は焼かれてしまいました。エンジンは、ただ博物館に置いておくだけで定期的に整備していなければ、樹脂部品の劣化と金属部品の錆びで動かなくなります。
ドイツは戦争中に、同盟国以外に中立国であるスイスとスペインに最新型のメッサーシュミット戦闘機とハインケル爆撃機を(正式な外交ルートで)輸出していました。
でもドイツの敗戦で交換部品が入荷しなくなり、外国軍のドイツ機は稼動数が減ってゆきました。スイスは中古ドイツ機をスペインに(部品取り用に)売却して米英の航空機に切り替えましたが、スペインは財政的に新型機調達が出来ませんでした。
いよいよエンジンの修理・維持が困難になったとき、スペイン空軍は戦勝国イギリス製のロールスロイスエンジンを輸入して、改修したドイツ機に積みました。He111爆撃機のエンジン室は余裕があったので、外観的な変化は「排気管片側6本の位置が下から上に変わった」程度で済みました。
Bf109戦闘機の機首は上部両側に大きな長いコブ状の張り出しを追加する改造が必要で、それによって操縦士の視界が悪化しました。
また、倒立v12気筒のダイムラーエンジンを正立v12気筒のロールスロイスエンジンに変えると、プロペラ軸が上に移動し、機体の重心も上に移動してしまいました。
結果として「スピットファイアの機首とメッサーシュミットの胴体を合体した、非常に乗りにくい戦闘機」が出来上がりました。
つまり、この映画で飛んでいるメッサーシュミットBf109とハインケルHe111のエンジン始動音は、スピットファイアと全く同じなのです。その音を聞くと、私はこの骨董品の機体が歩んだ数奇な運命を思い浮べてしまいます。
こうしてスペイン空軍が長期にわたって古い機体を使い続けたために、この映画撮影時に残存機体(と経験豊富なOBパイロット)を集める事が出来たのです。いや、むしろ「この機会を逃したらスペイン空軍がジェット機を導入するから、プロペラ機はスクラップにされてしまい、もう永久に実機の飛行を撮影できない。」という事情が映画関係者の資金集めや撮影交渉を必死にさせたと言うべきでしょう。
<語学>
Get your brain a chance !
フランス戦線で負けつつある英仏連合軍の新米パイロットが避難民の上で「勝利の旋回」を行ったことを飛行隊長が叱る言葉。「良く考えて行動しろ!」と上品に和訳すると「お前は脳味噌を使っていない白痴だ。」というニュアンスは伝わりません。
Stick me like Glue and keep your eyes open.
新米パイロットを実戦教育する編隊長の言葉。「俺に糊で貼ったようにピッタリ付いて来い。そしてしっかり目を開けて観察しろ。」これだけでは意味が判りません。
命がけの戦場では、敵も味方も教科書通りには動いてくれません。牽制のフェイントや欺瞞行為(フェイク)が乱れ飛びます。そんな中で上手に(頭を使って)立ち回らないと、命がいくつ有っても足りないのが現実です。
最初は隊長に付いて行くだけで精一杯で、見た事の意味を考える余裕など皆無です。何度もそれを続けていると、そのうちに周囲の全体像を把握できるようになります。「さっきの行動の意味は何だったのか?」「全体の中での我々の役目は何だったのか?」が判るようになって初めて一人前の行動がとれるようになります。そうなる前に隊長を見失って迷子になってしまうような者は、残念ながら敵の餌食となって死んでしまいます。