2012.12.1 のエントリー「情報リテラシー研修で言えなかったこと。OPACという用語を段階的縮小へ」
http://blog.goo.ne.jp/kuboyan_at_pitt/e/a503d2bbe4107af1bf5171579b2059aa
に反響が大きかったので、追記します。
はてブが29件、ツイートが30件というのは控えめな僕のブログにしては驚異的です(いずれも2012.12.31時点)。
ツイートを拝見したり、知人からのメール等からこんなことが言えるのではないかと思いました。
・「OPAC」という言葉を顧客に提示するのに違和感を感じている人は一定数いる。しかし、メインストリームではない。だから、僕の記事に反応があった。
("いまさら何を?" だったら、普通はスルーするでしょうから)
中には、
・顧客には「パソコンで検索」とかいう言い方をしている
という、とても参考になることを教えてくれた方もいます。
そして、当初から違和感があったという方は、
・「OPAC(蔵書検索)」という表記、括弧書きが取れない。十何年も使っているのに定着していない。
というご指摘。
まさしく。
自分たちの用語をそのまま(時には「利用者教育」という文脈で)顧客に提示する業界。その問題に多くの人が気付いているのに、なぜ変わっていかないのでしょうか。
気付いた人は各自、次のステップを考えるべきですが、ほんとになぜ?
情報リテラシー研修では、図書館目線を離れるという話をさせてもらったりしましたが、顧客視点が皆無だから? マーケティングに配慮がほとんどないから?
狭い世界で仕事をしている人が多いから? そういう人事構造になっているから?
そういう指向の人が入ってくるから? そういう指向が職場でさらに強化されるから? 図書館学教育も問題? 採用時の戦略の欠如? ・・・
少し話がそれるかもしれませんが、自分たちのサービスを顧客に提供するとき、その名前をどうするかって、どれくらい真剣に考えるものでしょう?
単なる自己満足とかノリじゃなくって、ちゃんと受け入れられるようにと。
今、紀要の原稿にも「プレゼン入門:話す基本技術」の報告を書いたところですが、ネーミングのことにワンパラグラフ使いました。
多少、ネーミングは考えました。
数日前の日経新聞に、大学でのピアサポートのことが取り上げられ、図書館等での取り組みも紹介されてました。そんな記事に「○○○」と表記されて、何となく意味が通じるような名前じゃないといかんなぁとも思いました。
http://blog.goo.ne.jp/kuboyan_at_pitt/e/a503d2bbe4107af1bf5171579b2059aa
に反響が大きかったので、追記します。
はてブが29件、ツイートが30件というのは控えめな僕のブログにしては驚異的です(いずれも2012.12.31時点)。
ツイートを拝見したり、知人からのメール等からこんなことが言えるのではないかと思いました。
・「OPAC」という言葉を顧客に提示するのに違和感を感じている人は一定数いる。しかし、メインストリームではない。だから、僕の記事に反応があった。
("いまさら何を?" だったら、普通はスルーするでしょうから)
中には、
・顧客には「パソコンで検索」とかいう言い方をしている
という、とても参考になることを教えてくれた方もいます。
そして、当初から違和感があったという方は、
・「OPAC(蔵書検索)」という表記、括弧書きが取れない。十何年も使っているのに定着していない。
というご指摘。
まさしく。
自分たちの用語をそのまま(時には「利用者教育」という文脈で)顧客に提示する業界。その問題に多くの人が気付いているのに、なぜ変わっていかないのでしょうか。
気付いた人は各自、次のステップを考えるべきですが、ほんとになぜ?
情報リテラシー研修では、図書館目線を離れるという話をさせてもらったりしましたが、顧客視点が皆無だから? マーケティングに配慮がほとんどないから?
狭い世界で仕事をしている人が多いから? そういう人事構造になっているから?
そういう指向の人が入ってくるから? そういう指向が職場でさらに強化されるから? 図書館学教育も問題? 採用時の戦略の欠如? ・・・
少し話がそれるかもしれませんが、自分たちのサービスを顧客に提供するとき、その名前をどうするかって、どれくらい真剣に考えるものでしょう?
単なる自己満足とかノリじゃなくって、ちゃんと受け入れられるようにと。
今、紀要の原稿にも「プレゼン入門:話す基本技術」の報告を書いたところですが、ネーミングのことにワンパラグラフ使いました。
多少、ネーミングは考えました。
数日前の日経新聞に、大学でのピアサポートのことが取り上げられ、図書館等での取り組みも紹介されてました。そんな記事に「○○○」と表記されて、何となく意味が通じるような名前じゃないといかんなぁとも思いました。















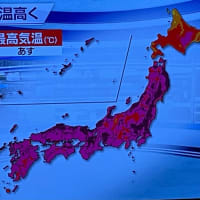
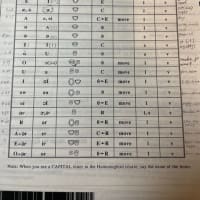









OPACに関する疑問をはじめとして図書館に対する様々
な意見を興味深く拝読しております。
図書館が図書館学(現在では図書館情報学という方が
通りが良いようです)という実学(学問)を基板とした
活動であることには,もう少し関心を向ける方がよいと
感じています。そのことが業務に即効性があるかどうか
は明言できませんが,現場にいる人たちの「基板」に
対する関心の薄さは,現在の図書館の弱体化の
ひとつの要因であることは間違いなさそうです。
(あなたが弱体化ととらえているかどうかはわからない
のですけれど。)
記事の書き様からは整ったお方であろうと推察いたし
ますので細かな指摘をすることはいたしませんが,
IT的技術の大きな効果に目を向けるだけでは図書館
活動が発展するとは思えないのです。
(おそらくそれは,「伝統的図書館の段階的縮小」と
なろうかと……)。
幾分不明瞭のままで投稿いたします。気まぐれに
投稿していますので放置してください。
失礼しました。