my耳袋#6「人魂観察」
私が大学四年の時、母方の祖父が胃癌で死にました。
私は、その祖父の事が大好きでした。
私の一家は、私の小学校の卒業とほぼ同時期に東京都下の武蔵野市吉祥寺というところへ引越しました。
その頃の吉祥寺は小学校時代に住んでいた文京区と違って、畑とかいっぱいあって何だかのどかな田舎めいた雰囲気がありました。
私は吉祥寺の、その田舎っぽい感じが好きでした。今の吉祥寺は変わってしまって、特に近年の人混みの多さには辟易としてしまいます。
今の吉祥寺は余り好きではありません。
でも、私はそれからも東京都内を転々とし、結局、今現在は、吉祥寺に戻って住み着いているのです。
私にとって吉祥寺という町は妙に吸引力のあるところで、又、どこかへ転居しても舞い戻ってきてしまうような気がします。
その吉祥寺に母方の祖父の家がありました。母の実家です。
最初に私の一家が吉祥寺に引越してくる以前にも、私は両親に連れられて幾度か祖父の家を訪れた事がありました。
でも、吉祥寺に引越してからは、同じ町で近いので一人で、しょっちゅう遊びに行くようになりました。
だいたいチャリを飛ばして行ってましたね。中学の時も高校の時も大学の時も、特に用が無くても、よく行ってました。
祖父の家は井の頭公園から水道道路方向へ坂を登って行く途中にありました。
古い日本家屋でとても風情がありまして、私は大好きでした。
祖父も祖父の家も何ともいえない懐かしいような心がホッとするような良い香りがしました。
祖父は以前、呉服店をやっていたのですが、その頃は、呉服店(水道道路沿いにあった)の方は息子(私の伯父)がやってまして、祖父は呉服の卸しの仕事を、その家でやっておりました。
時々、私は祖父の仕事を手伝いました。とは言っても伝票書きくらいでしたが。
祖父は私が遊びに行くと、いつも大変喜んで、仕事をやめて私の相手をしてくれました。
たいてい、祖父特製の目玉焼きを作ってくれまして、これが美味しいのなんの!
卵の中味が見事にぴったりと納まる小さな陶器がありまして、その陶器の底にバターを適量入れまして、その上に卵を割って入れ、ちょこっと醤油を垂らして、蓋をします。
その蓋は、その特製目玉焼き製造陶器専用のもので、小さな穴が数箇所、開いていました。
さて、蓋をしたら、後は、角砂糖のような発火剤を陶器の下部にある隙間に入れて火をつけるのです。
超弱火です。それで、約20分間、グツグツと煮、焼くのです。
蓋の穴からほんわりと湯気が昇り、いい匂いが立ち込めて、約20分後にその蓋を取ると黄身も白身も絶妙な感じで固まって下が薄~く焼けていて、そこにバターが、これまた絶妙にしっくりと染み込んでおり、世界一美味しい目玉焼きが出来上がっているのです。
私が美味しい美味しいと言って大喜びして食べていますと、祖父はとても嬉しそうに笑うのです。
その祖父が私が大学四年の就職活動中に胃癌になって寝込んでしまいました。
私は就職がなかなか決らず、忙しい毎日でしたが、何度も祖父の見舞いに行きました。
行くたんびに祖父は、
“おじいちゃんは、こんなになっちゃったよ・・・”
と言って、寝巻きを脱いで、私に自分の上半身の裸を見せるのです。祖父はけっこうがっしりした体格のいい人でしたが、私が行くたびにやつれて痩せていき、最後の頃は干からびたミイラみたいになってしまいました。
祖父は、どんどんやつれて萎んで黒ずんでゆき、何だかその変わり様が私には余りにもグロテスクに見えて、けっこうショックでした。
そうして、とうとう祖父は、1982年の年明けに死んでしまいました。
まだ正月があけたばかりの頃でした。
私は、依然として就職活動中で、その時までに、手帳につけていただけでも200社くらいは回ったのですが、全て面接で落とされて、まだ就職先が決らず、決る見込みもまるでなく、留年でもするか、と思っており、ボロボロな感じでした。
その日も何社か面接に行きまして疲れ果てて、家に帰ると、祖父が死んだと知らされ、すぐにお通夜に行きました。
もう夜になっており、親戚が集って寝っ転がってダベったりしてました、酔っぱらって祖父の悪口を言ってる人がけっこういて、私は何だか非常に不快になり、祖父の死体の置いてある部屋に行き、そこにいる後妻で私とは血が繋がっていない祖母や叔母やいとこたちに挨拶をして、線香をあげ、手を合わせ、しばらく祖父の死に顔を眺めてから、一旦、家に帰りました。
次の日は葬式で、朝からとてもあわただしく過ぎていきました。
祖父の家には凄く沢山の人が来ていて、久し振りに会う人もたくさんいて、まるでお祭りのようにわいわいがやがやと何もかもが超スピードで進んでゆき、火葬場へ行って、昼食の弁当を食べ、祖父は焼かれ粉々の骨になり、再び祖父の家に帰ってきて、やっと落ち着いた頃には、もう、部屋に骨ツボが置いてありました。
あっと言う間に夕暮れになり、相変わらず、祖父の家は騒がしく、さらに事もあろうに親戚たちが祖父の遺産相続の話でもめ出したので、私は嫌になって、祖父の家から出て、坂下の井の頭公園に向かいました。
祖父の家のある坂をまっすぐ下りて、井の頭公園に入り、左側(井の頭線の井の頭公園駅のある方)へ行くと砂場や滑り台のある小公園がありまして、私は、その小公園のブランコに乗って、しばらくボケっとしていました。
冬なのに、やけにきつい夕陽が、ギラギラした感じで辺りを赤く染めていました。
そうして夕陽の中でブランコをこいでいると、火の玉が飛んでいました。
夕焼け空の中、ちょうど高架線の上あたりを、火の玉がスーッと飛んでました。
そして、私は思考停止状態に陥り、ブランコをこぎながら、その火の玉を見ていました。
すると、その火の玉は、高度を下げ、あっと言う間に私の目の前にやってきました。
子供の頃、路地を曲がったら、いきなりオニヤンマが目の前にいた事がありました。
その火の玉が急に私の目の前にやってきた時、その路地を曲がっていきなりオニヤンマと出合った時と同じような感覚に陥りました。
何だ?何だ?これは・・・と、私と私の見てるモノ以外のなにもかもが、ピタリと停止してしまった・・・そんな感じですか。
何もかも、全ての現象が、ピタッと止まって、私は、ただただ、ギョっとしているのです。
オニヤンマに子供の頃、突然遭遇した事ってあるでしょうか?あんな感じです。オニヤンマってでかいんすよねぇ。アッケにとられるほど。
私の思考は停止し、ただただ、その火の玉を見つめていました。
火の玉は私の目の前で宙に浮いて停止していました。
まん丸の球体で、普通の野球の軟式のボールより一回りほど大きい感じでした。
ただ球体の表面には、動物の毛のような感じで、細かい火がたくさん付いてましたので遠くで見た時はもっと大きく見えました。
でも、あれは火なのかどうか。砕かれて細かくバラバラになったシャーペンの芯の残骸のようなものが、たくさん、球体の表面全体に浮いていて、火の玉の本体を層のように覆っている感じでした。
色は赤に近い橙色でしたが、思うに、おそらく夕陽のせいでそういう色に見えたのだと思います。
本来は白なんでしょう。こんなギラギラした強い夕陽の差す状況ではなく、普通の昼か夜に見れば、たぶん、白いんじゃないかと思えました。
そして、球体の本体をよく見ていると、「ういろう」に似てると思いました。
名古屋の「ういろう」です。
そういう質感なんです。球状の白い「ういろう」に夕陽が差せば、この火の玉だ、そう思いました。
本体の表面も、そのつるつる具合が、やはり「ういろう」に似てるんじゃないかと思えました。
何となく、美味しそうでした。ちょっと食べてみたくなりました。が、止めておきました。
食べたら、私は、どうなったでしょう?何だか、碌な事にはならない気がしました。
ずいぶん長い時間、その火の玉は私の目の前に浮いていたような気がしましたが、後から思えば、きっとほんの数秒です。
ずっと観ていたかったんですがね。
何だか周りの世界が動き出したような気がしたと思ったら、その火の玉は、すでに私の目の前から離れ、どんどん上昇していました。
そして、ギラギラした夕焼け空をギラギラした夕陽の差す方角へ、スゥ~~っと飛んでいってしまいました。
西の彼方へ。
私は、ポカンとしたまま、祖父の家に戻りました。
喪服を着た母がいたので、つい、今の出来事を話してしまいました。
“かあさん、今、オレ、火の玉見たよ。火の玉!”
すると母は言いました。
“へぇーへぇーへぇ~~~、ほぉ~ほぉほぉ~”
私は母がまるっきり信じてないなと思い、さらに強く言いました。
“マジ、見たんだよ!火の玉!信じてないだろ!おれ、見たの!”
すると母は言いました。
“バカ。あたしも見たんだよ、子供の頃。あたしのかあさんが死んだ時、下の公園のブランコに乗ってたら火の玉が飛んでいったんだよ!”
私は目を大きくしました。
“マジ?おれも、下の公園、ブランコこいでて、見た”
母は言いました。
“へぇーへぇーへぇ~~~、ほぉ~ほぉほぉ~”
母の母と言うと、私の祖母だ。母の母は、母が幼い頃病死して、母の父は昨夜病死して、母は母の母の葬式の時に、下の公園のブランコで火の玉を見て、私は母の父の葬式の時に、同じく、下の公園のブランコで火の玉を見た。
私は何だか、親から子へ、親から子へ、という感じの血の繋がりというものを実感し、同じ血をひくものの運命みたいなものを感じたものでした。
私はちょっと母に確認してみました。
“かあちゃん、じゃ、おれが見た、あの火の玉は何?やっぱ、おじいちゃん?”
母は言いました。
“さあね、隕石でもみたんでしょ。じゃなきゃ、たぶん錯覚でしょ。あんなのが人魂かねぇ”
何だ、人魂って自分で言ってるじゃん、と思いながらも、私には、さっきの火の玉が祖父だという事はとっくに分かっていたのです。
あれは間違いなく祖父でした。祖父の人魂でした。
だって、火の玉が私の目の前から去って行った後、ブランコの周りの空気に、
なんとも、かぐわしい祖父の香りが漂っていたのです。
終
This novel was written by kipple
(これは実体験なり。フィクションではない。・・・が、妄想かもしれない。)










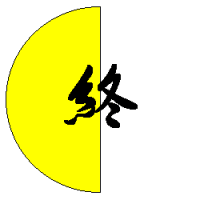
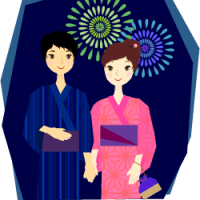
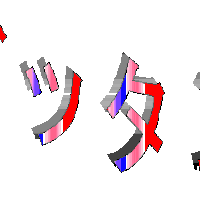


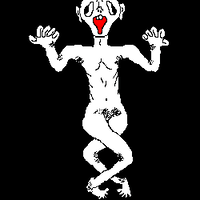
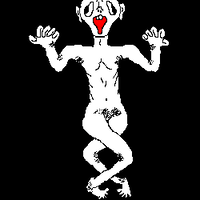
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます