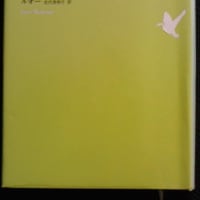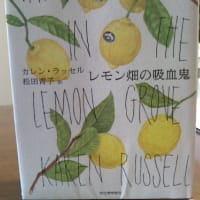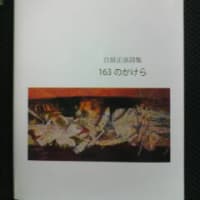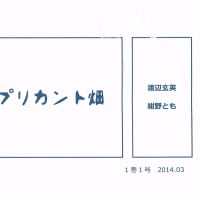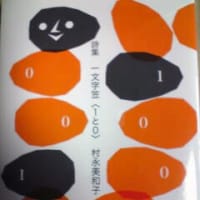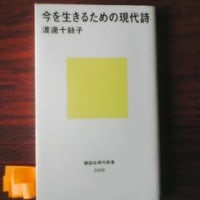円城塔という名前が気になっていた。で、「文学界」11月号を借りて、読んだ。題名は「つぎの著者につづく」。とても小説の中身を示唆している題名だ。わけわかんなくても面白い小説というものがあって、なんだか、よくわかんないんだけれど、読めてしまうし、読後感がいいのだ。
物語ることそれ自体が物語るものを創りだしていると言ったらいいのだろうか。
「ベコス」という発語が出てくる、ヘロドトスの『歴史』の二章冒頭(?)の部分から小説は始まる。「原初の民と起源の言葉」を求めて、二人の嬰児を羊飼いに預け、二人の間に最初に発せられた言葉で、それがわかったという話だ。作者は、この実験の不備を指摘しながら、話はあの有名な、海を見て「う」を発したという話しに行き、スカラベから『哲学探究』、さらに「プラハの図書館」が出てきて、カフカの影が横溢し出す。そして、この物語の「私」の書き物は「リチャード・ジェイムス氏」=R氏の剽窃があると批評されたという話から、R氏捜しの物語になっていく。と、書きながら、こんな流れとして書いていいのかなとボクは疑問に思う。と、いうくらい、いろんなものが溢れているような感じなのだ。そう、読者の知識の量と感性の質によって、謎が解けるのだろうと思わせるパロディ化引用化が推察できるのだ。
なんだか、原子モデルを思い出した。私とR氏という陽子と中性子。その周囲を引かれながら飛ぶ電子のような、様々なテキストたち意匠たち。このズレ方というか、こぼれ方というか、ライプツィヒが構成の鍵、あるいは構成への動機付けを行っているような気がするし、ウィトゲンシュタインが挑戦相手のように思えてくるし、カフカの「オドラデク」が作品の手触りを語っているようだしで、何だか読み終わってしまう。長い小説ではないので。
ボクら、広大な知の伽藍の中で、「つぎの著者につづく」ように手渡された膨大な螺旋構造の中にいて、その継続が物語を次へ手渡していく。その快感があった。
それから、この作品の魅力は、文章の言い回しの可笑しさ、諧謔にもある。それと、ラストに向かう際の高揚感。なんだか、クライマックスがありそうなドラマの謎解きの予感に震えさせるものがあった。
物語ることそれ自体が物語るものを創りだしていると言ったらいいのだろうか。
「ベコス」という発語が出てくる、ヘロドトスの『歴史』の二章冒頭(?)の部分から小説は始まる。「原初の民と起源の言葉」を求めて、二人の嬰児を羊飼いに預け、二人の間に最初に発せられた言葉で、それがわかったという話だ。作者は、この実験の不備を指摘しながら、話はあの有名な、海を見て「う」を発したという話しに行き、スカラベから『哲学探究』、さらに「プラハの図書館」が出てきて、カフカの影が横溢し出す。そして、この物語の「私」の書き物は「リチャード・ジェイムス氏」=R氏の剽窃があると批評されたという話から、R氏捜しの物語になっていく。と、書きながら、こんな流れとして書いていいのかなとボクは疑問に思う。と、いうくらい、いろんなものが溢れているような感じなのだ。そう、読者の知識の量と感性の質によって、謎が解けるのだろうと思わせるパロディ化引用化が推察できるのだ。
なんだか、原子モデルを思い出した。私とR氏という陽子と中性子。その周囲を引かれながら飛ぶ電子のような、様々なテキストたち意匠たち。このズレ方というか、こぼれ方というか、ライプツィヒが構成の鍵、あるいは構成への動機付けを行っているような気がするし、ウィトゲンシュタインが挑戦相手のように思えてくるし、カフカの「オドラデク」が作品の手触りを語っているようだしで、何だか読み終わってしまう。長い小説ではないので。
ボクら、広大な知の伽藍の中で、「つぎの著者につづく」ように手渡された膨大な螺旋構造の中にいて、その継続が物語を次へ手渡していく。その快感があった。
それから、この作品の魅力は、文章の言い回しの可笑しさ、諧謔にもある。それと、ラストに向かう際の高揚感。なんだか、クライマックスがありそうなドラマの謎解きの予感に震えさせるものがあった。