
聴覚障害児に対する早期支援教育のサイトを見ると、親は子供の人工内耳装用で聴者になることの期待があると言う。教育関係者は人工内耳が聴者になれるものでもないことを知っているが親はそうではないと。
教育関係者側はろう者として生きることがもう一方の選択肢と考えているのだろうか。
人工内耳に失敗した割合から問題点を論じるもあちこちで散見するが、「失敗」というのは聞こえるようになった「成功例」に対する考えではないのか。失敗の問題点を論じる時点で1か0かの立場のように見える。
別に失敗ではないと言う考えは持てないのか。人工内耳で聞こえるようにならないと「失敗」とされたら、難聴者はみな「失敗者」だ。
難聴者は体験的に自分の聞こえが環境にも心身の状況によっても大きく変わることを知っている。聞こえる場合も聞こえない場合もありなのだ。
難聴者は、気候に例えて言えば、暗闇の中を歩いている時に猛烈な風が吹き付け、足元すらぐらぐらする状態、周囲の明るさが絶え間なく変化し、時にはちょっと先も見えない濃霧が発生し、明るくなったと思ったら幅60センチもない両側が断崖絶壁の尾根を歩いていたという感じではないのか。
こうした厳しい環境の中でを生きている難聴者を中途半端な障害だなんて言うことは許されない。周囲からも理解されず、自分でも認識できない難聴という障害に立ち向かっている難聴者はなんとけなげでまた勇気ある人なんだと思う。
難聴者は、補聴器や人工内耳を装用することで、幅60センチの道を2メートルに広げ、前に立って吹き付ける風を避ける傘を差して先導してくれる人をたてたりしながら生きている。
聴覚障害を持つことは「個性」と言われるが日本語ではキャラクター、性格のようにとらえられてしまいがちだ。そうではなく、人は皆まちまちで多様な存在と言うことを指している。多様と言うことには、聞こえ方だけではなく価値観、生き方、人生観も含めて多様と言うことだ。
この多様性がダイバーシティだ。今の社会はこのダイバーシティが許容されない社会だ。しかし障害者権利条約が人類の意識の到達点として、現実の政治のレベルに提起されている今、東日本大震災でこれまでの競争と差別と効率主義の社会のあり方が見直されようとしている今こそ、ダイバーシティな教育を実現する好機だ。
聴覚障害を持つ子供の親に、価値観の多様性を見いだす学習の場が必要ではないか。教育の現場で真のダイバーシティを実現することが問われている。
ラビット 記
※メガディスカウントストアのセルフレジの端末
教育関係者側はろう者として生きることがもう一方の選択肢と考えているのだろうか。
人工内耳に失敗した割合から問題点を論じるもあちこちで散見するが、「失敗」というのは聞こえるようになった「成功例」に対する考えではないのか。失敗の問題点を論じる時点で1か0かの立場のように見える。
別に失敗ではないと言う考えは持てないのか。人工内耳で聞こえるようにならないと「失敗」とされたら、難聴者はみな「失敗者」だ。
難聴者は体験的に自分の聞こえが環境にも心身の状況によっても大きく変わることを知っている。聞こえる場合も聞こえない場合もありなのだ。
難聴者は、気候に例えて言えば、暗闇の中を歩いている時に猛烈な風が吹き付け、足元すらぐらぐらする状態、周囲の明るさが絶え間なく変化し、時にはちょっと先も見えない濃霧が発生し、明るくなったと思ったら幅60センチもない両側が断崖絶壁の尾根を歩いていたという感じではないのか。
こうした厳しい環境の中でを生きている難聴者を中途半端な障害だなんて言うことは許されない。周囲からも理解されず、自分でも認識できない難聴という障害に立ち向かっている難聴者はなんとけなげでまた勇気ある人なんだと思う。
難聴者は、補聴器や人工内耳を装用することで、幅60センチの道を2メートルに広げ、前に立って吹き付ける風を避ける傘を差して先導してくれる人をたてたりしながら生きている。
聴覚障害を持つことは「個性」と言われるが日本語ではキャラクター、性格のようにとらえられてしまいがちだ。そうではなく、人は皆まちまちで多様な存在と言うことを指している。多様と言うことには、聞こえ方だけではなく価値観、生き方、人生観も含めて多様と言うことだ。
この多様性がダイバーシティだ。今の社会はこのダイバーシティが許容されない社会だ。しかし障害者権利条約が人類の意識の到達点として、現実の政治のレベルに提起されている今、東日本大震災でこれまでの競争と差別と効率主義の社会のあり方が見直されようとしている今こそ、ダイバーシティな教育を実現する好機だ。
聴覚障害を持つ子供の親に、価値観の多様性を見いだす学習の場が必要ではないか。教育の現場で真のダイバーシティを実現することが問われている。
ラビット 記
※メガディスカウントストアのセルフレジの端末










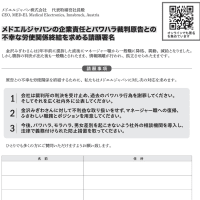

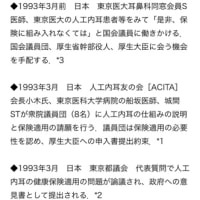






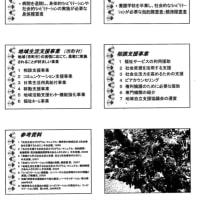
文章にある【難聴者を気候に例えると…】について根本的に疑問です。
音がない=暗闇という時点で認識違いを感じてほしい。
補聴器がなければ一人で立つのもやっとなのか!?
人工内耳について、難聴について語るなら、まずろう者と関わってください。
多様性を説くには文章が偏りすぎです。
例えの説明が足りなかったかもしれません。
ろうであることが物理的に「暗闇」ということではなく、何も音声情報が入らない状態を「光が入らない」状態と例えました。時々聞こえたり、あいまいに聞こえる状態を「光が点滅したり、ボーっと明るくなったり暗くなったりする」状態、情報が入らずどっちに歩けばいいのか分からない状態を「足元がぐらぐらする」状態に例えました。
その心は、見た目には普通に見えても、とても厳しい環境の中で足を踏ん張って耐えていることを表したかったのです。それは、ろう、難聴者とも同じです。
どこかでお目にかかりましたら、お話したく思います。Facebookでもよろしくお願いします。