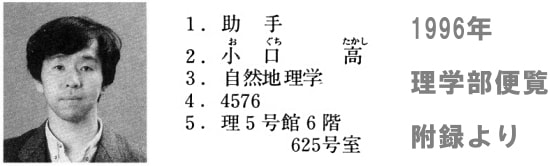パリの学会の後,レバノンのベイルートにやってきました.目的は,レバノン人の地形学者,ラニア・ブヘ(Bou Kheir, R.)との議論です.中近東では,イスラエルを除くと国際的に活躍している地形学者がとても少ないのですが,ラニアは例外です.彼女は多数の論文を国際誌に執筆しており,デンマークの大学の客員教員でもあり,フランスやアメリカの研究者とも共同研究を行っています.とても貴重な人材です.
そんなラニアも,かなり苦労してきたことが今回わかりました.彼女はイスラム教徒ではなく少数派のキリスト教徒で,かつ女性であるため,レバノンでは不利な扱いを受けることが多いそうです.そこで彼女は,国内よりも国外で理解されることを目指してきたそうです.実に共感する話でした.
ラニアはGISを用いた侵食地形の研究を行っています.今回,ベイルートの郊外の山地に連れて行ってもらい,侵食の実態を見ることができました.写真の斜面には全面的に人の手が加わっており,多数の段々畑が分布しています.しかし農業の従事者が減ったため,写真の手前側の斜面や,奥側の斜面の左側のような放棄された畑が増え,侵食の原因になっています.彼女の論文には,この問題に関する記述があり,僕はそれを事前に読んでいました.しかし今回現場を見て,初めて具体的なイメージを得ました.フィールド調査の大切さを再認識しました.
レバノンというと,ヒズボラの存在やイスラエルとの争いが報道される機会が多いため,危険な国というイメージがあるかもしれません.しかし現地はすこぶる平和です.また,僕は2004年まではシリアに頻繁に行っていたので,久しぶりに味わう本場の中東料理に感激しました.ただし,ベイルートの海岸を歩いていた時には,古い建物の壁に,内戦の時代の銃撃でできた多数の穴や窪みがあるのを見ました.また,2006年にイスラエルがレバノンを空爆した際には,ベイルートも標的になりました.平和の時代は決して長くないといえます.
This-ism, that-ism, ism ism ism.
All we are saying is give peace a chance.
(Give Peace a Chance / John Lennon)
そんなラニアも,かなり苦労してきたことが今回わかりました.彼女はイスラム教徒ではなく少数派のキリスト教徒で,かつ女性であるため,レバノンでは不利な扱いを受けることが多いそうです.そこで彼女は,国内よりも国外で理解されることを目指してきたそうです.実に共感する話でした.
ラニアはGISを用いた侵食地形の研究を行っています.今回,ベイルートの郊外の山地に連れて行ってもらい,侵食の実態を見ることができました.写真の斜面には全面的に人の手が加わっており,多数の段々畑が分布しています.しかし農業の従事者が減ったため,写真の手前側の斜面や,奥側の斜面の左側のような放棄された畑が増え,侵食の原因になっています.彼女の論文には,この問題に関する記述があり,僕はそれを事前に読んでいました.しかし今回現場を見て,初めて具体的なイメージを得ました.フィールド調査の大切さを再認識しました.
レバノンというと,ヒズボラの存在やイスラエルとの争いが報道される機会が多いため,危険な国というイメージがあるかもしれません.しかし現地はすこぶる平和です.また,僕は2004年まではシリアに頻繁に行っていたので,久しぶりに味わう本場の中東料理に感激しました.ただし,ベイルートの海岸を歩いていた時には,古い建物の壁に,内戦の時代の銃撃でできた多数の穴や窪みがあるのを見ました.また,2006年にイスラエルがレバノンを空爆した際には,ベイルートも標的になりました.平和の時代は決して長くないといえます.
This-ism, that-ism, ism ism ism.
All we are saying is give peace a chance.
(Give Peace a Chance / John Lennon)